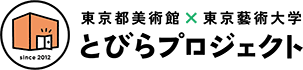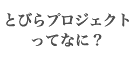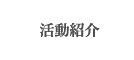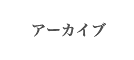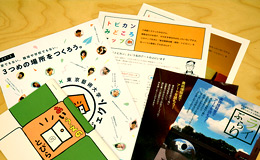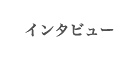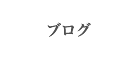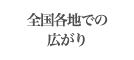※会場でインタビューを収録したため、一部音声が聞き取りづらい部分があります。イヤホンでの聴取をお勧めします。
展覧会の感想や、今回のテーマ「アートと共に生きていく」から感じた「私たちの人生もアート」なんだという思いを、親子で話してくれました。
日常的な話はよくするけれど、アートに対する思いについて話す機会はないそうで、美術館でこのような対話が生まれてよかったと思います。
展覧会のテーマ「アートと共に生きていく」からみなさんは何を感じますか?
全文要約
「ずっとアートと生きていく」ラヂオ、この回では都内にお住まいの60代と20代の親子のお話しをお送りします。上田葉子さんとお付き合いのあるお母様が、写真を撮るのが好きだという娘さんを誘って来館してくれました。
ー展示についての感想を聞かせてください
60代のお母さん:葉子さんは普段は、生徒さんと出品されることが多いけど、今回は彼女の作品だけ並んでいて、本当に素晴らしい作品を数々残されているんだな改めて感じました。
ー葉子さんとはお付き合いがあると伺いましたが、薫さんとは面識はありますか?
薫さんの作品を初めて見たのは、教科書に掲載されていたものです。葉子さんと出会った時に、「主人は作家なんです」と言われ、どんな作品ですか?と聞くと卵の作品と言われ、この作品が!と思いました。
今回、作品を間近で見てみて、離れると写真だけど近くで見ると絵なのだなとよくわかって、最近描かれた、虫の絵やご夫婦の絵とか。特にポットに写った作品が大好きで、夫婦を表していて、薫さんは奥さんのことが本当に好きなのだなとよくわかる作品だなと思いました。認知症があっても作品に向かっている姿は画家で、本当に素晴らしい2人だなと思っています。
今回のテーマ「アートと共に生きていく」で、私たちの人生もアートかなと思ったのです。彼女は、全てをアートで生きていて、私たちも自分たちの人生は色々あるけど私たちもアートを生きているのだなと思いました。これからどんなアートを生きていくのかが楽しみです。
20代の娘さん:お母さんは大きいことを言っているけど、作品を作る人・作らない人ではなく、どんな絵を描こうかと構造をイメージして作品を作るのと同じように、自分の生活も自分の選択で作っていくものだから、お母さんの言う「人生がアート」というのには納得ができます。私は今回の展示のテーマを見た時に、上田薫さんが90代になっても自分の好きなことを続けられているのが素晴らしいなと感じて、やりたいように思ったままに生きたいと思いました。
普段は日常的な話はよくするけれど、アートに対する思いについて話す機会はなかったということでした。美術館でこのような対話が生まれてよかったと思います。
ーどんなふうにアートと生きていきたいですか?
60代のお母さん:時間がなかったり、期間が決まっているものが多いので、有料でも映像視聴ができると来場しにくい方も見ることができるのではないかと思いました。情報のキャッチのしやすさがあるとより、参加しやすくなるかなと思います。展覧会のアーカイブとして、載せてもらえるともっと届くのかもと思いました。
ー最後に、アートとどう付き合っていきたいかを伺いました。
60代のお母さん:自分の生活を豊かにしてくれて、ホッとできる時間で切り離せないものです。
20代の娘さん:子供と関わる仕事をしていて、作りたいものを作っている子供達に対して、日常としてではなくしっかり見ていきたいなと感じました。美術館以外でも、作品を見るときは、興味を持って見て、相手の表現しているものしっかり感じていきたいと思いました。




※会場でインタビューを収録したため、一部音声が聞き取りづらい部分があります。イヤホンでの聴取をお勧めします。
展覧会の鑑賞から話は、アートとの関わり方について向かっていきました。
家族から反対をされながらも、アートの道に進むため家を出たこと、新聞配達のアルバイトで感じた地域との繋がりやご自身の経験を語ってくれました。
また、目の見えない友人に作品について伝えながら観たデ・キリコ展での体験や認知症のご家族と訪れた美術館でのエピソードなど、たくさんのお話をお聞きしました。
全文要約
「ずっとアートと生きていく」ラジオこの会では、アート関連のお仕事をしている女性にお話しを伺いました。
アートの世界に進んだきっかけ、目の見えない友人と観たデ・キリコ展、認知症のご家族と訪れた美術館でのエピソードなど、たくさんのお話をお聞きしました。
ー展覧会はどうでしたか?
ダイナミックで大胆な色彩や構成が印象に残りました。特に、キルトの作品が印象に残っていて、布にも筆致というか筆使いのような表現ができるんだなと感じました。
ー普段からアートを見ていますか?
アート系の学校で、ミクストメディアという色々な画材や技法を1つの作品に使い、油絵や水彩、立体を組み合わせて一つの作品にするというジャンルを学んでいました。当時から、コミュニティアートやソーシャルアートに興味があり、実は、学生時代は新聞配達をしていていました。新聞を配るという行為が、誰かに毎日同じ時間に何かを受け渡すということが、ある地域の中に生きているという感覚を得たりしていて、配っている時にできたご縁を写真として記録したりしていました。
ーどうして新聞配達を選んだのですか?
アートの道を志した時に、家族からの賛成を得られず半ば飛び出してきたんです。地元で勉強ばかりしていて、自分のやりたいことはなんだろうと悩んでいた時に、ストリートアーティストの壁画家さんに出会い、その方に一緒に描こうよと言われ、地域の方々や、バックグラウンドが違う・名前も知らない人とその日あって絵を描いて、それぞれが会話するよりもアートという媒介があった方がより仲良くなれるんです。アートってコミュニケーションを生むメディアとしてとても興味があるんです。
多様な感覚や身体を持つ方との鑑賞にも興味があり、目の見えない友人と「デ・キリコ展」と鑑賞をしました。
ーデ・キリコの作品を説明するのは難しくなかったですか?
超現実の世界なので、見たままをディスクライブしても、目の見えない友人にとっては、センセーショナルな説明になってしまうので、言葉で表現する難しさを感じました。
作品を言葉で表現しないと一緒に鑑賞できないので、目に見えたものを説明しながら、そこから受けた印象を友人に話して、私が紡いだ言葉に対してフィードバックをくれて「なんでそう感じたの?」とか「それはこういうこと?」というキャッチボールを繰り返していくうちに、最後の展示室に行く手前で友人が「手塚治虫の火の鳥みたいな印象を受けた」という言葉をくれて、とてもハッとしたんです。
「火の鳥」の内容として、全部ことはないのですが、転生していくある人の人生で、悪いこともいいことも必ず繰り返す。という内容になっていて、諸説あるのですが、ニーチェの「永劫回帰」という哲学に影響を受けていたという一徹があって、作品の説明をする中で「永劫回帰」という言葉は出していなくて、2人の新しい共通の鑑賞体験がそこで生まれたというか、繋がった体験があってすごく面白かったです。




※会場でインタビューを収録したため、一部音声が聞き取りづらい部分があります。イヤホンでの聴取をお勧めします。
それぞれ、美術館との関わり方や思い出を語ってくれました。
その場で出会ったばかりの2人でしたが、直接会話をしてとても和やかな場となっていきました。
台湾の博物館処方箋、各国の美術館で行われているシニア向けの取り組みを見た感想から、社会的処方箋の話題に変わっていきました。
劇場と舞台芸術とケアのシンポジウムに参加された、60代の女性は、誰もが行きやすい美術館にするためには、特定の誰かではなく全ての人にとって、安全であることが重要で、スタッフとお客さんが自分らしく、生き生きとその場にいられることが重要なのではないかなと語ってくれました。
全文要約
「ずっとアートと生きていく」ラヂオ、この回では、社会的処方箋に興味を持ち来館した60代の女性と20代の大学生、お二人の話をお届けします。
ー1番印象に残った作品はなんですか?
20代の大学生:「bloom」という作品。赤いピンクのお花のキルティングが大きくてインパスとがあって目を引きました。実際に見てみると、細かに布を合わせているのが印象的でした。
60代の女性:別の展示をメインで見にきたので、まだ、こちら側の作品は見れていないんです。
ー美術館は1人で来ることが多いですか?
20代の大学生:1人か家族と行くことが多いです。両親とも美術館が好きで、企画展を見に上野に行ったり、旅行先で美術館に行くこともあります。特に、岡山の倉敷にある大原美術館が印象的で、建物がどっしりしていて、展示作品も近代画が集まっていて魅力的でした。
60代の女性:幼少期に美術館に行く機会がなく、大人になってから自分が展覧会に行く時は、子供と一緒に美術館に行っていたのですが、ある時、子供から行くことを憚られ、押し付けてしまっていたかも、、、と反省し、それからは少し一緒に行くのを控えて行きたいかどうか確認するようにしました。今では、30代になった2人の娘は美術館に行ったり お芝居を見たりしているので、幼少期の記憶が影響しているのかなと思っています。
ー今のお話を聞いて家族と美術館に行く時に行かされてる感はありませんでしたか?
20代の大学生:私は、自分で言うのもなんなんですか、素直に行くタイプで、弟がいるのですが、弟はあまり美術館に好んでいくタイプではなくて、家族で博物館に行った時に両親と私は興味津々で見ていたのですが、弟は「なんで僕は、興味を持てないんだろう。せったくここまで来たのに」と言っていたことを思い出しました。
60代の女性:興味が持てないとわかったと言うことは、興味の範囲ではないと言うことだから、自分を知る機会にはなっているはずですよ!
その場で出会ったばかりのお二人でしたが、直接会話をしてとても和やかな場となっていきました。
台湾の博物館処方箋、各国の美術館で行われているシニア向けの取り組みを見た感想から、社会的処方箋の話題に変わっていきました。
ー社会的処方箋についてどう思いますか?
60代の女性:大まかな情報は知っていますが、展覧会としてどう展開するか、どんな資料があるのかに興味があってきました。芸術文化と地域・社会を繋ぐアートマネジメントを大学で教えているので、パフォーミングアーツの方面で文化的処方箋を実現できないかなと考えてます。
ーとびラーはアートと人のコミュニケーションについて考えているのですが、その点いかがですか?
20代の大学生:アートと繋げるというよりは、美術館と社会が繋がったらいいなと思っていて、アートに限定してしまうと敷居が高くなり、自分には関係ないかもと思う人も多いと思うので、もう少し美術館と社会が繋がるといいなと思ったりしました。
ー東京都美術館のミッション(美術館に来館しずらい方・足を運べない方・興味を持てない方)について、どうしたら敷居が低くなると思いますか?
60代の女性:昨日参加した、劇場と舞台芸術とケアのシンポジウムで、イギリスの劇場での取り組みで、特定の誰かではなく全ての人にとって、安全であることが重要で、スタッフとお客さんが自分らしく、生き生きとその場にいられることが重要なことなんだと思いました。




※会場でインタビューを収録したため、一部音声が聞き取りづらい部分があります。イヤホンでの聴取をお勧めします。
この日は子ども連れなど多くの方が来場し、にぎやかな会場でした。
外出が難しくなったお母さんと車椅子でゴッホの「ひまわり」を鑑賞した際のエピソードです。
体が不自由になったお母さんに何もしてあげられなかったという女性。
「これなのね」と何度もつぶやいた母の様子を語るご自身にとっても、アートによって心が満たされた時間だったのかもしれません。
また、アートの楽しみ方について伺いました。
行きたいと思った時にふらっと行って、日常から離れてアートの中で自由に心を遊ばせる・・」
そんな「心がおいしくなる場所」が美術館なのだ、とお話を聞いて感じました。
あなたにとって「心がおいしくなる場所」は、どこですか?
全文要約
「ずっとアートと生きていく」ラヂオ、この回では 展覧会に立ち寄ってくださった女性の話をお届けします。
この日は子ども連れなど多くの方が来場し、にぎやかな会場でした。
まずは展覧会の感想そこから思い出したエピソードを伺いました。
ー無理のない範囲でかまないので、お母様についてお話しいただけますか?
体が不自由になってしまってどこにも出掛けられなかったので、最後に新宿の美術館にあるゴッホのひまわりを見に行ったんです。それで、「これ本物なんだね」と言っていました。これが最後に一緒に見た絵で、最後のお出かけでした。そのあと、急に亡くなってしまったんです。
本物を見る機会があるといいですよね。そんなに好きではなくても本物を見にいくって、演劇だと時間も長いので、、、体調もその日に決めていかないといけないですが、美術館なら期間も長いので体調がいい日に行けるし、天気もいい日を選んでいくことができるので。
母は元々田舎にいたのですが、体が不自由になって一緒に暮らし始めました。「田舎にもこういうのがあるといいよね、1枚の絵でも展示して」と言っていました。1枚の絵でも、デイケアのみなさんで見れたらいいのにと思いました。作品を見て、「これなのね」と何度も言っていて、ひまわりは買ったときにすごいニュースになった作品じゃないですか。なので「これなんだ」と言っていたのかもしれません。
ーお母様は美術館によく行ったりしていましたか?
あまりなくて、歌が好きだったのでよく聞きに行っていました。体が不自由になって、見にもいけなくなってしまいまして。
今回作品を一緒に見ることができてよかったです。他は何もできなくて、親不孝だったけど。
あの展示室は、新しくなってからなんかそこだけはすごい万全の状態でやってるので、そこだけはケースの前まで行けてでこうやって、こうやっても見れたから、しっかり恩返しができたかなと思います。
ーアートってどういう存在ですか?
旅行に行っているような、物語の中に入っていけるというか、、、美術館の企画展に行くと、自分が主役になれるというか、とても楽しいです。
美術について、勉強していないからこそ自分の見方で楽しめて、その作家を繰り返し見ることでその作家について知っていける。1人でも来られるし!
ー最後にあなたにとってアートはなんですか?
行きたいと思った時にふらっと行って、日常から離れてアートの中で自由に心を遊ばせる・・」
そんな「心がおいしくなる場所」が美術館です。