
3
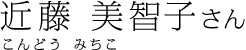
とびらプロジェクト コーディネータ、
立ち上げスタッフの一人
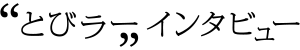

3
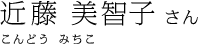
とびらプロジェクト コーディネータ、
立ち上げスタッフの一人
「一緒につくっている感覚の面白さ」
近藤 肩書きは「とびらプロジェクト コーディネータ」で、東京藝術大学側からかかわっているスタッフです。藝大での立場は特任助手。

「とびらプロジェクト」は、東京都美術館と東京藝術大学の連携プロジェクト。双方のスタッフが都美館で一緒に働いている。
近藤 2012年4月の「とびらプロジェクト」のスタートからたずさわって、まずは1期の「とびラー」たちと、「美術館を通じてなにができるか」を一緒に考えてきました。
けど2年目、3年目と人数が増えてくる中、彼らの活動や話し合いのプロセスに十分にかかわりきれていない気がしていて、それが悩ましい。「とびラー」は最初の年は90名で、次の年に126名になり(注:3年目は150名)。3年制だから、このまま増えつづけるわけではないのだけど。
プロセスをともにしてゆくのは、いちばん大事なことだと思っているんです。
でも、1人と話すと1時間くらい使ってしまって、そのあと別の2人と3時間くらい話してしまい…とやっているともう本当に時間がない。仕事も沢山あるし。この悩ましさについては、任期を終えた「とびラー」たちと、4年目以降どんなふうにやってゆけるかがポイントになるんじゃないかなあ。
近藤 多摩美術大学を卒業して、藝大の修士課程を経て、その研究科の助手として働きながら作品制作をつづけていました。たとえば、お爺さんが一人で暮らしているような集落に入っていったりして。
つくるからには多くの人の共感を得たい。けど「そのお爺さんのためだけでもいいじゃない」と思う自分も同時にいて。そんな制作の時間を重ねていると、自分と社会の接点がちょっとわからなくなるときもありました。一人でつづけてゆくことの難しさも感じていて。
ちょうどそんなときに同じ研究科で助教をつとめていた伊藤さん(「とびらプロジェクト」プロジェクト・マネージャ)から声がかかって、「自分が必要とされるのなら、やってみたい」と思ったんです。

近藤 「とびらプロジェクト」は本当になにからなにまで手探りで。とくに1年目は誰にとっても初めてのことだらけで。「とびラー」はスタッフに答えを求めてくるけれど「持ってないよ(笑)」と答え、一緒に飲みに行くと「そんなんじゃ駄目だよ(笑)」と言われ。そんな時間を共有しながら、でもなんだか常にワクワクしていて、家に帰っても「とびラー」のことばかり考えていたし、働き過ぎだと思ったけれどまったく苦ではなくて。
近藤 というより、一緒につくっている感覚の面白さです。
中でも自分にとって大きかったのは、2年目に始まった「Museum Start あいうえの」の、「のびのびゆったりワークショップ」での体験ですね。

「Museum Start あいうえの」は、東京都美術館と藝大を推進役に、上野公園に集まる9つの文化施設が連携して進める、子どものミュージアム・デビューを応援するプロジェクト。「とびらプロジェクト」につづく形で、その翌年(2013年)から始まった。
そのプログラムのいくつかで子どもたちは、半年間ほど、都美館を拠点に上野の森に通って約2時間をすごす。ここでの「とびラー」の立ち位置は、子どもたちの「冒険の仲間」。スタッフからの呼びかけに応じた有志の「とびラー」が、「とびらプロジェクト」と併行して参画している。
<つづく>
「子どもたちと、いかにつないでゆくか」
近藤 「のびのびゆったりワークショップ」は、障害のある子どももない子どもも、いろんな小学生が一緒に進んでゆく全6回のワークショップで、わたしが主担当をつとめました。
参加した子どもは21名。7割が障害のある子で、3割が障害のない子ども。事前に「耳が聴こえません」とか「発達障害と診断されています」と教えていただいて、その上で抽選で選ばせてもらいました。1年目(2013年度)の倍率は約2倍です。

参加している子どもの一人と、手話で話を交わす「とびラー」。
近藤 そこが問題で。子どもの人数に対して、1.6〜1.7倍の人数が要るんです。
1期の「とびラボ」の中に「障害のある子どもたちとのワークショップをやりたい」という活動があって、「のびのびゆったりワークショップ」が始まる半年以上前に、そのメンバーと一緒に、白梅学園大学・こども学部の杉山貴洋先生の現場を見学させてもらったんです。
行く前はほかのワークショップと同じく、子どもより大人の数が少ないイメージを持っていました。けど、一人ひとりの子どもの状況が異なるので、大人の方が多くないと成り立たないということがわかった。
あと、環境が変わるとパニックを起こしてしまう子も多いので、関与する「とびラー」はなるべく同じ顔ぶれにしたい。
これらが他のプログラムと圧倒的に違うところです。「とびラー」が集まる日は、年間を通じて最低限のポイントだけ設定されていて、それ以外は本人の都合の範囲内で活動している。でも「のびのびゆったりワークショップ」には、全6回必ず参加してもらう必要があるわけですから、とてもハードルが高い。
近藤 わたしが難しいと思ったのは、彼らのモチベーションです。たいていのプロジェクトがそうなのだけど、スタッフ側で全部準備して「はい。これをやってください」と渡すようなやり方では、やっぱりうまくいかないんですね。
みんながモチベーションを持ってかかわってゆくには、企画や準備のプロセスを十分に共有してゆけるといい。でも、プロジェクトを実施するまでの時間が十分にはとれなかった。
ひとまず8月にプログラムの開始を伝え、秋から3ヶ月間、隔週ペースで参画できる「とびラー」に手を挙げてもらい、子どもたちの情報と照らし合わせながら「この子とこの『とびラー』にペアになってもらおう」という素案から考え始めたのだけど。
近藤 やっぱり難しくて。最初にお話しした慢性的な時間の足りなさがあった上で、プログラムをご一緒していただくことになった杉山先生との企画作業にも時間が欲しい。先生がいつもなら学生としていることを、初めて会う「とびラー」と協調的に行えるように、いろいろ調整しなければならない。
一部の「とびラー」は前の年に先生の現場を見学している。けど、ほかの大半の人たちは初めてだから、急に当日をむかえたら多分びっくりしてうまく動けなくなってしまうだろう。
あらためてどこかへ見学に行きたい。けど都合を合わせる余裕もない。という具合に、時間はなくなってゆく一方で。
少なくとも、当日からでなく準備段階から「とびラー」とプロセスを共有してゆこう。そこで「とびラー」の気持ちも温まって、モチベーションを上げてゆけるようにしようと考えました。
杉山先生から、「子どもたちに事前に『東京都美術館の入り口の丸い銀の玉のところで待っているよ』というような手紙を送っておくといい」と聞いていたので、「僕が書くよ」と言ってくださっていたけど、「それを『とびラー』とやらせてください」とお願いしたんです。都美に集まって自分の担当の子にお手紙を書いて。そんなところから「とびラー」と歩き始めて、「来週から始まるんだね」と心の準備ができていって。

近藤 初日に集合場所にやって来て、嬉しそうに「お手紙ありがとうございます」と話しかけてきた子どもたちと会って、「とびラー」も実感をもってかかわり始めることができたんじゃないかと思う。

「のびのびゆったりワークショップ」には、約40名の「とびラー」が参画。
近藤 わたしの役割は、子どもたちと「とびラー」をいかにつないでゆくか、ということだったと思います。それを本当に模索しつづけた約1年間でした。事前の準備を一緒にやり、「とびラー」の方からもアイデアが出てきたり。

杉山先生のアイデアを受けて「とびラー」たちが形にした、保護者との連絡帳。
近藤 館内で開かれている展覧会を見に行くときには、杉山先生にお願いして、その前に20分、「とびラータイム」を加えてもらいました。展覧会場に入る前の子どもの気持ちづくりを、すべて「とびラー」に任せてもらうようにお願いしたんです。

近藤 「とびラー」たちは毎回プログラムが終わるたびに、「こうした方がいいんじゃないか」「ああした方が」とすごく考えてくれた。
障害を抱える子どもたちの中には、自閉症であるとか、ダウン症と診断されている子がいたり、耳が聴こえなかったり、状態も年齢も一人づつ違う。その一人ひとりに合う伝え方を「とびラー」が常に工夫していって。
わたしもそうだったし「とびラー」もどうすればいいのか、自分たちのかかわり方がいいのか悪いのかわからないまま、ともかく一所懸命やって、そうしたら結果がついてきた。という実感があります。

近藤 最後の日は子どもも「とびラー」もなんだか泣きそうだったりして。達成感がありました。終わってから先生も、「『とびラー』はここ(都美館)の財産だね」「ファシリテーターが40名いたプログラムだった」と言ってくださって。<つづく>
「いま生きている人に、興味がある」
近藤 とても不思議なんです。わたしは、とくに1年目は毎晩遅くまで働いていたし、いつも「とびらプロジェクト」のことばかり考えていたけれど(笑)、それでも形式上はこの仕事は週5日で、残り2日間はお休みです。
でも「とびラー」は普段ほかの仕事をしていたり、家庭や生活もある中で本来お休みのはずの時間にここに来ている。しかも「のびのびゆったりワークショップ」のような、本当に気の抜けない活動にもかかわっている。

近藤 無償・有償で「ボランティア」と「仕事」をわける意識は、わたしにはありません。そもそも「とびラー」はボランティアと呼ばれていないし、わたしたちスタッフにも「美術館のボランティア運営」というような意識はない。
「とびラー」はサポーターではなくプレイヤーで、アート・コミュニケータで、やっぱり「とびラー」なんですよね。
近藤 考えたこと、なかったですね。…適切でないかもしれない。「とびラー」にちゃんとかかわってゆきたいけど、整理したり管理したいわけじゃない。プロジェクトと「とびラー」の調整役ではあるけれど、それがすべてとも思っていなくて。
…なんて言えばいいんだろう。本当に「一緒に考えている」というか。
近藤 そうですね…コーディネータよりはその方が。っていうか、いっそのこと「とびラー」になりたい(笑)。「とびラー」の一人である方が、みんなのことがもっとわかると思うんですよ。
でもスタッフなので、わたしがどんなに「みんなと一緒だよ」と言っても、彼らは「近藤さん、いつもお疲れ様です!」っていう感じじゃないですか。それはどう頑張っても払拭できないんですよね。お給料もいただいているし、同じ立場にはなり得ないのだけど、「コーディネータ」よりは「とびラー」の方がわたしはいい。
「とびラー」の活動は金銭面では無償だけど、「ボランティア」とは違う感じがするし、もちろん労働でもなくて、わたしはこれは〝仕事〟だと思っています。主婦の日々の事々が〝仕事〟であるように。
それぞれ意味や価値を感じているし、責任も担って、かかわり合っていると思うんです。
でもいまここで起きているのが、決してあたり前のことであるとは思えない。「どういうことなんだろうね?」って、ほかのスタッフともよく話すんです。すごく有り難いのと同時に「とびラー」は不思議な存在で、わたしにもまだよくわからない。彼らはなにかを共有していて、そこに可能性を感じながら「やってみよう!」と動きつづけているんですよね。

近藤 以前は大学で働きながら作品づくりをしていたと話しましたけど、「とびらプロジェクト」が始まってからは、もっぱら都美館にいて、ここで開催されている展覧会の作品を目にしていたのだけど、このあいだ久しぶりに藝大に行って学生や助手の展示作品を見てきたんです。
そのときハッ!としたんですよね。なんだかひさしぶりに「生きている人の作品を見たな」と思って。やっぱりわたし、いま生きている人に興味があるんだな(笑)って。あらためて、すごく実感したんです。<おわり>
聞き手・文:西村佳哲
撮影(クレジットのない写真):後藤武浩
* 「Museum Start あいうえの」には、「のびのびゆったりワークショップ」の他にも
「放課後の美術館」など複数のプログラムがあります。
→田中進さんのインタビュー参照



〝ゼロ期〟とびラー、主婦、2度目の大学生
2014-10


1期とびラー、区民ホール勤務、デザイナー経験あり
2014-10


とびらプロジェクト コーディネータ、立ち上げスタッフの一人
2015-01


2期とびラー、家庭と会社と3本柱
2015-01

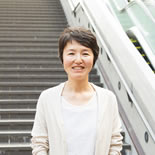
1期とびラー、家族で会社運営、もとテレビ局勤務
2015-02


大学で刑法を学び、広告業界を経た学芸員
2015-06


子育て中の1期とびラー、言葉にしない“共感”の名人
2016-02


2期とびラー、経験を持ち帰りながらテーマパークの運営会社に勤務
2016-05


3期とびラー、就活を経て出版社に入社1年目
2016-07


4期とびラー、美術館めぐりが趣味の仕事人。
2016-11


3期とびラー、タイでボランティアを8年間したクラフト好き
2017-01


現役藝大生の4期とびラー
2018-04


「幹事大好き」の4期とびラー
2018-04


最年長の70代。5期とびラー
2019-05


「とにかくやってみる」ことを楽しむ5期とびラー
2019-06


人と人をつなぐ回路をつくる、プログラムオフィサー
2020-01


私にできることってなんだろう?「関わること」を大切にする6期とびラー
2020-10


「障害のある方のための特別鑑賞会」の先に、美術館の未来をみる6期とびラー
2020-11


「より創造的な体験」をとびラーと一緒に作り上げる、とびらプロジェクト コーディネータ
2021-04


7期とびラー。「笑顔」を絶やさないお茶目な伴走者
2021-06


「できないことじゃなくてできることをやる」転んでもただでは起きない7期とびラー
2021-07


誰の意見も素直にきける「コミュ力」抜群のバランス系7期とびラー
2021-08


「生みの親」がプロジェクトとともに歩んだ10年
2022-07


Museum Start あいうえのから「循環した学び」を得た直感の人。8期とびラー
2022-08