
33
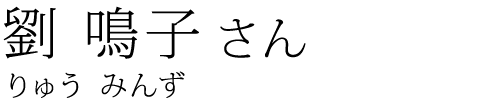
言語について考える、ポジティブ思考の11期とびラー
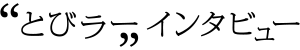

33
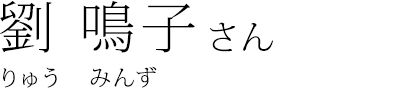
言語について考える、ポジティブ思考の11期とびラー
「やるしかない!」
劉 そうなんです。電車の中でスマホを見ていたんです。たぶん展覧会の情報か何かを調べていたんだと思うんですが、そこに偶然流れてきたのが「とびラー募集」でした。
アート、コミュニケーション、美術館、人、つながる、場づくり……。並んでいたキーワードを見て「何これ?私の好きなワードばかりじゃない?」と驚きました。そして、直感的に「やるしかない」と思いました。
もう、募集締め切りの直前でした。気づくのがあと1週間遅れていたら、その年の応募には間に合わなかったですね。

劉 そうですね。ちょうど、新型コロナのパンデミックが起こって、人生というのは何があるか分からないものだな、なんて、あたりまえのことを痛感していて。だったら自分が興味や関心を持っていることに、もっと向き合おうかなと考え始めた時期でした。
私は中国・北京に生まれ、1992年に7歳で日本の東京に来ました。日本語が全くしゃべれない状態で荒川区の公立小学校に編入し、周囲の人に助けられて育ちました。そのまま都立の高校に進み、卒業後はカナダ・バンクーバーのカレッジで3年半英語やアートを勉強しました。その後は日本に戻って、語学教育の講師、翻訳・通訳など、得意の英語と中国語を使った仕事をしています。
やりたいことや楽しいことを求めて、いろんな仕事を転々としてきたのですが、小さい頃から好きだったアートはずっと続けています。20代後半の頃、美術大学の通信課程で油絵を学びました。現在は、アクリル絵の具と紙、布などを使った立体感のある抽象画作品をつくっています。

劉さんの作品 展示風景(ギャラリー檜) 本人撮影
コロナ禍では、人と人とのつながりやコミュニケーションの大切さを日々再確認していました。アートの世界でも、街中のギャラリーや世界中の美術館で、困難な状況でも芸術文化の力を信じて活動している人たちがいることを知り感動していました。そんな時だったから、「つながり」とか「場づくり」といったとびらプロジェクトのキーワードにビビッと反応したのではないかと思います。
…と、今振り返ってみるとそう思いますが、実際はもう、勢いでした。
とびらプロジェクトのホームページで、フォーラムの動画を急いで視聴しました。
私も時々ギャラリーで絵を展示していますし、美術館は大好きだけど、美術館の「あり方」までは考えたことはなかった。そうか、ここはそういうことを学べる場なんだと、自分のなかでしっくりくるものがあったので、すぐに応募書類を書きました。

劉 まず「とびラーにはいろんな人がいるなあ」「みんな楽しそうだなあ」と思いました。選考のグループ面接のときから、すでにそれは感じていたのですけど。基礎講座では、数人がグループになって話すワークでみなさんと話して、ますますそう思いました。
ところで、とびらプロジェクトは、振り返りの時間を大切にしますよね。
毎回講座のあとすぐに、振り返りを記入するための簡単なフォームがメールで届くのですが、これがとても便利でした。振り返って記入したことが自分のメールアドレスにも返信されるので、あとから見直すことができるんですよね。
3つの実践講座のうちアクセス実践講座を1年目と3年目に選択したのですが、同じテーマの講座に対して前回の私はどう書いているのかなと振り返ることもできました。私、実はこの振り返りという作業があまり得意ではなかったんですが、このフォームのおかげで無理なくできたので、本当に助かりました。

劉 そうですね。アクセス実践講座で扱う多文化共生というテーマは、外国にルーツを持つ私にとって、特に身近なものですから。
私が日本に来たのは1992年で、外国ルーツの子どもはまだ珍しい存在でした。日本語がまったくできない外国ルーツの児童は学校で私ひとりだったらしく、担任にはベテランの先生が配置され、学級委員の子がお世話役をしてくれました。日常の中でコミュニケーションが難しい場面はありましたが、周囲のみんなが助けてくれました。
今は時代が変わり、外国ルーツの子どもは珍しくなくなりました。地域によっては、クラスに何人も外国ルーツの子がいることがあたりまえです。日本人と外国ルーツの方との接し方も多様化しています。30年前は、私がマンションのエレベーターに乗っていたら、「何階に住んでる鳴子(ミンズ)ちゃんだよね」とそのあたりの大人たちはみんなわかっていたんですが、今はそういうわけにはいきません。外国ルーツの子どもたちがあたりまえの存在になった分、かえって付き合い方が難しくなってきているのではないか、と思っています。
それと、誰よりも外国ルーツの子どもたち自身は、言葉ができないという苦しい環境の中で日々暮らしているわけです。出身国も多様化していますから、母語もバラバラですよね。だから、言語を介しないコミュニケーションが何かしら必要なのではないかと考えていたのです。

Museum Start あいうえの 美術館でやさしい日本語プログラム「わたしの線を見つけよう!」(2022年)に参加する劉さん
撮影:中島祐輔
<つづく>
「あえて中国語は使わずに」
劉 はい、これは「やさしい日本語」(※文法・言葉のレベルや文章の長さに配慮し、わかりやすくした日本語のこと)を使った、外国にルーツを持つ子どもたちを対象としたプログラムです。「やさしい日本語」を用いながら、言葉だけではなく音や身体も使って、目の前にあるアートを楽しむ活動をします。
「展覧会 岡本太郎」展(会期:2022年10月18日〜12月28日)では「わたしの線を見つけよう!」と題して、まず岡本作品の中に見られる線を探し、その後、実際に自分でカラフルな墨汁を使って線を書いてみました。
「永遠の都ローマ展」(会期:2023年9月16日〜12月10日)では、「からだで楽しむ!ローマ展」というタイトル通り、作品のポーズを実際にやってみるという活動をしました。
子どもたちが日本社会で日々感じている「言葉がわからない」「どうしよう」という大きなストレスから離れて、日本のコミュニティの中で何か楽しいことができる。それは、これから日本に暮らしていく子どもたちにとっては、とても意味がありますよね。そして、美術館は安心して来られるところなんだよ、ということを伝えることができます。そういう場で、とびラーとして子どもたちと一緒に楽しいことができればいいなと思って、毎年参加していました。

Museum Start あいうえの 美術館でやさしい日本語プログラム「わたしの線を見つけよう!」(2022年)にて
とびラーは保護者の活動にも伴走する 撮影:中島祐輔
劉 2年目だったかな。プログラムに参加したこどもたちの中に、とても元気な中国人の少年たちがいたんです。
その子たちが、展示室に入るとすごく真剣に作品を見ている。その姿に感動しました。教科書に載っているものの実物を見て、そこから受けた刺激は子どもたちのクリエイティビティにつながっていく。ここではそういう体験をさせてあげられるんだ、これがミュージアムの役割の大事なところだよなあ、と感じながら見ていました。
実はこの時、展示室に入る前に少年たちがちょっと騒いでいたので、私は、思わず中国語で「静かに!」って言いそうになったんです。でも、ぐっとこらえました。
劉 そうですね。もちろんそれもあるんですが、私、やさしい日本語プログラムでは、中国語も英語も使わないようにしていました。
劉 「やさしい日本語プログラム」ですから、その趣旨に合わせようと思って。
日本に来た子たちが、日本で頑張っていくことを応援するための場にせっかく参加しているのに、「今日は美術館で中国の人と楽しく喋ってきたよ」というのはもったいない気もしました。「やさしい日本語」で、コミュニケーションに必要な基礎的な部分は押さえているわけですから。
以前、日本語教師として中国からの留学生が多くいるクラスを教えたことがあるんですが、その時に私が中国語を話せないという設定のほうがうまくいったという経験もありました。

Museum Start あいうえの 美術館でやさしい日本語プログラム「からだで楽しむ!ローマ展」(2023年)にて
とびラーは多様な外国ルーツの子どもたちの活動に伴走する 撮影:あいうえのスタッフ
逆に、中国語を積極的に使ったこともあります。学校プログラムで来館した小学校の子どもたちの中に、日本に来たばかりの中国人の女の子がいました。プログラムは日本語で進められていたので、その子は明らかに情報を得られていない状態。だからこの時は横について、中国語への通訳をしました。

Museum Start あいうえの 学校プログラムにて
学校のこどもたちの鑑賞をサポートする劉さん 撮影:あいうえのスタッフ
劉 私自身が子どものころに日本に来て、何もわからないところに日本語を浴びせられて育ちました。これって、母国を離れた子がみんな通る道ですよね。それで鍛えられて強くなっていく子もいるし、しんどいままの子もいる。
そういういろんな外国にルーツを持つ子たちと、学校ではないところでかかわる。子どもたちの姿に過去の自分を重ねあわせることもありましたし、時代の違いを感じたりしながら、自分のこれまでの人生を振り返ることにもなりました。私にとっては、すごくありがたい時間でした。
美術館が、外国にルーツを持つ子たちに目を向け、ミュージアムに来るきっかけづくりをしているんだ、ということにも感動しました。
劉 アクセス実践講座でも紹介された「やさしい日本語」を、実際に使ってコミュニケーションしてみようと思ったのです。私自身が日本語を教える現場で実際に何が起きているのか、自治体が外国ルーツの方へどんな対応をとっているのか、興味がありました。
とびラボでは「昨日の出来事を『やさしい日本語』を使って話してみよう」などの活動をしました。この活動では、「話す」という行為において、自分が何を伝えたいのか、どの部分について話したいのかを見極めることが何より重要だと改めて感じました。

劉さんが呼びかけてはじまったとびラボ「やさしい日本語を使ってみよう」のミーティングにて
撮影:とびらプロジェクトスタッフ
劉 2024年の「アート・コミュニケーション事業を体験する2024」展(以下、AC展)では、中国人ファミリーとの印象的な出会いがありました。展示をすごく熱心に見ている中国人がいたので話しかけてみると、北京からの観光客で、ドキュメンタリー映像をつくっている人だったんです。
会場のとびらプロジェクトの英文の説明文をしっかり読んで、「このプロジェクトはすばらしい、市民が美術館にかかわっているんだね」と心を動かされた様子。そこで、とびラーの活動を「単なるボランティアではなくて…」「とびラボというしくみがあって、そこでは自分たちがやりたいプロジェクトに取り組むことができて…」と詳しく説明したら、さらに感動してくれました。
「ラボで好きなことをやる、それがひとりひとりのウェルビーイングにつながり、最終的には大きなウェルビーイングになっていくんだね。大事にしているのは一人一人の心、一つ一つの会話なんだね」と。
「つながった!」と思いました。私たちの活動を理解して、思いを汲み取ってくれた。結局、1時間半くらい立ち話をしていたような気がします。あの人たち、日本にいたら絶対とびラーになっていると思います(笑)。
AC展には、アジアをまわっているという外国人の美大生など様々な人が来てくれました。英語ネイティブの藝大生にインタビューした時にも思ったのですが、言葉ができてよかったなと。こういうふうにいろんな人とつながっていきたいから、私は英語を好きになったんだな、と実感しました。

「アート・コミュニケーション事業を体験する2024」展示風景 撮影:中島祐輔
<つづく>
「笑い飛ばすしかないじゃないか」
劉 まずは大掃除です。資料が捨てられない性格なので、3年間の大量の資料がたまっています。それを整理してファイリングしながら、振り返っていきたいです。振り返りは苦手なんですけど(笑)。
とびラーの仲間とは、これからもつながって、地域で活動していく場所を探していこうと思っています。まだ、こういう活動、という決まったものはなくて、まずはゆるい感じでつながりながら、情報交換をしていく。ネットワークがあれば、それぞれが自分の地域に戻って何かをやるときにもとびラー同士で相談しあうことができます。一緒に考えていく仲間がすでにいるわけですから、その関係を、絶やさずに育てて行きたいと思っています。

劉 作家としてつきあいのあるアートギャラリーがいくつかあるので、そういうところでワークショップやイベントをやっていければいいなと思っています。みんなで絵を見るとか、何かをつくるとか、気楽に参加できることを。
今まで私は、ひとりで絵を描いてきたんですけど、せっかくだから展覧会の場を使って誰かと何かをやってみたい。それを一緒に盛り上げてくれそうな仲間も、とびらプロジェクトでいっぱいできたので。この仲間の存在は、作家活動を続ける上でも、すごく励みになると思います。
私の作品は、キャンバスや木製パネルに紙や布などの素材を貼り付けて、それを繰り返して制作するので、凹凸があるんです。今までも「面白いね」と見てくださる方には、「どうぞ触って」と言うことがあって、「触れるアート」っていいな、とずっと思ってきました。
私がとびラー3年目の年に、目の見えない方がとびラーに参加しました。その方とも話していくうちに、キャンバスに貼りつけた素材によっては硬くてとがっていたりして危険があるということに気づきました。特に目の見えない人には危ない。だからこれからは単なる「触れるアート」だけではなく、安全に触れるシリーズを作ってみたいと思っています。

劉さんの作品(部分) 本人撮影
劉 もっともっととびラボに出たかったです。もっといろんな人と喋りたかったし、活動もしたかった。体力が続けばもっとできたのに、と思うところはあります。とびラーのみなさん、体力も自己管理もしっかりされていて、家庭や仕事との両立もできていて、ちゃんと自分のエネルギーの割り振りができている。いつもみなさんすごいな、と思っていました。
思ったように進まないミーティングももちろんありました。でも私は性格的に、みんなが考え込んで黙ってしまうような雰囲気があまり好きではなくて。「大丈夫だよ!希望はあるよ!」、「これが難しいならこっちをやってみない?」と、ポジティブに持っていきたくなる癖があって。
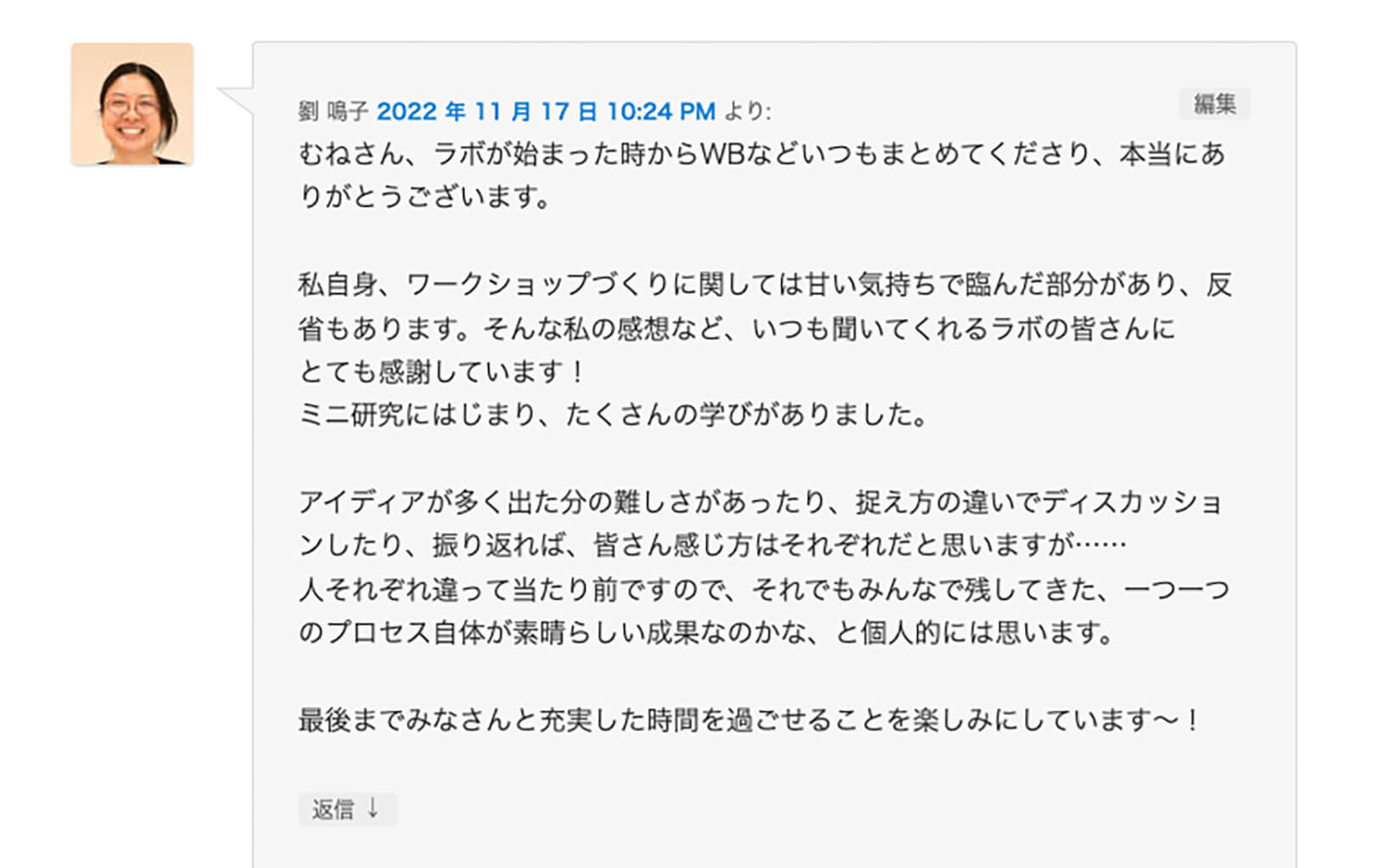
とびラーの活動は専用のオンライン掲示板で全員に共有されている。
とびラボミーティングの報告がアップされる「本日のホワイトボード」で、劉さんが投稿したコメント。
「今、世界はこんなにも大変なんだから、困ったことがあっても笑い飛ばすしかないじゃないか」みたいに思っていました。楽観的すぎてそれは大人としてはどうなの?と自分では思うこともあるんですけど(笑)でも、最終的には笑って終わりたいですよね。苦労したとびラボも、今はいい思い出です。

劉 はい、直感は正しかったです。
さっき、開扉後はみんなそれぞれの地域で活動していくと言いましたが、私は引っ越しが多い人生を歩んできたので、実は土地や地域というものにこだわりがありません。住んでいる場所でなくてもコミュニティは存在できると思うし、離れていてもつながれると思っています。とびラーの皆さんとはそうやって付き合っていけると思うし、そういう関係ができたのは、やはりとびらプロジェクトだったからだと思います。
とびラーは、相手の存在に関心を寄せて話を聞くというベースを基礎講座で学んでいます。お互いの話を聞きあう、尊重しあうことができている。とびラボでも実践の場でも。いつ来ても、アートスタディルームから帰るときにそう感じていました。
人間はひとりひとり違うから面白い。そして共通点もあるから面白い…。そんなことを、自分のなかでずっと、ぐるぐると感じていた3年間でした。

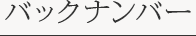


〝ゼロ期〟とびラー、主婦、2度目の大学生
2014-10


1期とびラー、区民ホール勤務、デザイナー経験あり
2014-10


とびらプロジェクト コーディネータ、立ち上げスタッフの一人
2015-01


2期とびラー、家庭と会社と3本柱
2015-01

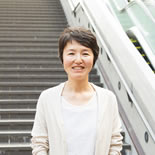
1期とびラー、家族で会社運営、もとテレビ局勤務
2015-02


大学で刑法を学び、広告業界を経た学芸員
2015-06


子育て中の1期とびラー、言葉にしない“共感”の名人
2016-02


2期とびラー、経験を持ち帰りながらテーマパークの運営会社に勤務
2016-05


3期とびラー、就活を経て出版社に入社1年目
2016-07


4期とびラー、美術館めぐりが趣味の仕事人。
2016-11


3期とびラー、タイでボランティアを8年間したクラフト好き
2017-01


現役藝大生の4期とびラー
2018-04


「幹事大好き」の4期とびラー
2018-04


最年長の70代。5期とびラー
2019-05


「とにかくやってみる」ことを楽しむ5期とびラー
2019-06


人と人をつなぐ回路をつくる、プログラムオフィサー
2020-01

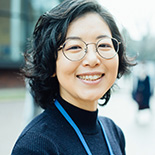
私にできることってなんだろう?「関わること」を大切にする6期とびラー
2020-10


「障害のある方のための特別鑑賞会」の先に、美術館の未来をみる6期とびラー
2020-11


「より創造的な体験」をとびラーと一緒に作り上げる、とびらプロジェクト コーディネータ
2021-04
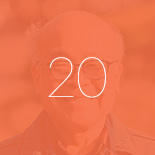

7期とびラー。「笑顔」を絶やさないお茶目な伴走者
2021-06


「できないことじゃなくてできることをやる」転んでもただでは起きない7期とびラー
2021-07


誰の意見も素直にきける「コミュ力」抜群のバランス系7期とびラー
2021-08


「生みの親」がプロジェクトとともに歩んだ10年
2022-07


Museum Start あいうえのから「循環した学び」を得た直感の人。8期とびラー
2022-08