
36
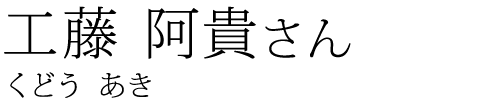
とびラーから10年後、美術館の社会共生担当へ
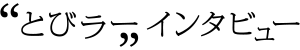

36
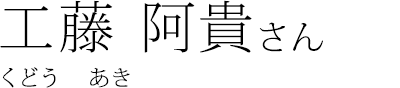
とびラーから10年後、美術館の社会共生担当へ
「いつでもどうぞ!」と言える環境づくり
工藤 2024年4月に東京都歴史文化財団が管理運営する文化施設(7館12施設1機構)に、芸術文化へのアクセシビリティ向上のための環境整備を設計・推進・統括する社会共生担当が新しく配属されました。私は東京都美術館(以下、都美)の社会共生担当として着任しました。仕事内容をひとことで言うと、都美へのアクセシビリティを向上させること。障害があってもなくても、誰もが都美にアクセスしやすくなるように、調整や整備を行っています。

工藤 たとえば手話通訳の手配や、作品の触図の制作をしています。また、やさしい日本語による野外彫刻ガイドを作成するなど、障害の有無を問わず、さまざまな方に向けたアクセシビリティを考えています。

オープンレクチャー・レクチャーvol.15「ろう者・難聴者・聴者が一緒に「 」」における情報保障の様子(2024年)撮影:とびらプロジェクトスタッフ
工藤 はい。それを、当館が主催するイベントのほとんど全てに手話通訳を配しました。情報保障を必要とする方がわざわざ事前申込をしてから来館するのではなく、いつ来ても、聴こえ方に関係なく講演会などを楽しんでもらいたいと考えたからです。2023年度から、土日に手話のできる案内スタッフが配置されていましたが、2025年度からは情報サポーターという手話での案内をはじめとして、アクセシビリティに特化した案内スタッフが開館日に毎日配置される予定です。(2025年3月現在)
工藤 最初のうちは、まだまだ認知度が低いので、依頼している手話通訳さんとどれだけ丁寧に打合せをし、資料を共有するなどして事前に準備をしても、当日手話を必要とする方がいらっしゃいませんでした。続けているうちに少しずつ認知度が上がりました。手話関連のサイト等へ広報するなど、少しずつ発信も続けています。
今まで「手話通訳は事前申込してお願いしないと付かない」と思っていた方たちに、「都美のイベントだから手話通訳付いているよね」と思ってもらえるようになってきて、参加人数だけが評価基準ではないけど、やっぱり参加者が増えているのは嬉しいです。
ろうの親子、30代くらいの女性とそのお母さんが来館されたことがあったんですが、たまたまそのタイミングで、展示室で作家さんがギャラリートークをやっていたんです。通りかかってそれを見たふたりが「ちょっと見て!手話通訳がいるよ」「ほんとだ、すごいね」って手話で喋っていたんです。一回通り過ぎて、「あれ?」って気づいて戻ってきてくれて、トークにも足を止めてくださいました。この光景を見るためにここまでやってきたんだ!と言っても過言ではないくらい、とっても嬉しかったです。ギャラリートークに毎回参加して、手話通訳さんに「ありがとう」と仰る来館者もいらっしゃいました。
工藤 触図とは、絵画作品の線や面などの要素を立体的にするなどして、触覚で作品を鑑賞する鑑賞補助ツールです。2024年、「田中一村展 奄美の光 魂の絵画」で、はじめて触図を作りました。

工藤 はい。見える人と一緒に鑑賞することを前提としていることもあるし、ロービジョン(病気や怪我などで視力や視野に障害が生じ、日常生活に不自由を感じる状態)の方が触りながら見ることなどを想定して、カラーにしました。
これを触ってもらいながら、横にいる見える人が「そこは花びらですよ、白くて光っています」と伝えると、作品のなかでどこの部分の話をしているのかが共有できます。あくまでも作品を鑑賞するための補助ツールなんです。一緒に見る、見える人のためにもカラーである必要があると思って、そこはこだわりました。
触図は「こうやって作る」というマニュアルはなくて、手探りです。来館者には、「触図を用意しているなんてすごい」と言われた反面、「こんなに多くの線があったら何だかわからない」というご指摘もあって、まだまだ試行錯誤中です。展覧会担当の学芸員や、2024年にとびラーになった全盲の方にも意見を聞きながら進めました。
美術館内部での調整も重要でした。美術館として外部に出すツールを新しくつくるわけですから、館の中での理解を進める必要があります。なぜ必要なのか、どういう使い方をするのかを、まず館の職員にしっかり理解してもらわないといけませんよね。最近は「次の展覧会でも、触図つくるよね?どの作品にする?」などと展覧会担当者から声をかけてもらうこともあって、少しずつ浸透してきているなと感じています。
特別展だけでなく、都美の所蔵作品も触って鑑賞していただくべく、現在、講堂前にあるレリーフ作品ジョゼフ=アントワーヌ・ベルナールの《舞踏》を3Dプリンタで制作中です。(2025年3月現在)
このほかに、手話による建築紹介動画、美術館に初めて訪問する発達障害の方や、来館に不安を感じる方が安心して来られるよう、絵や写真を使ってわかりやすく当館を案内する「ソーシャルストーリー」なども制作中です。(2025年3月現在)いずれはアクセシビリティに特化したウェブサイトも作りたいと思っています。
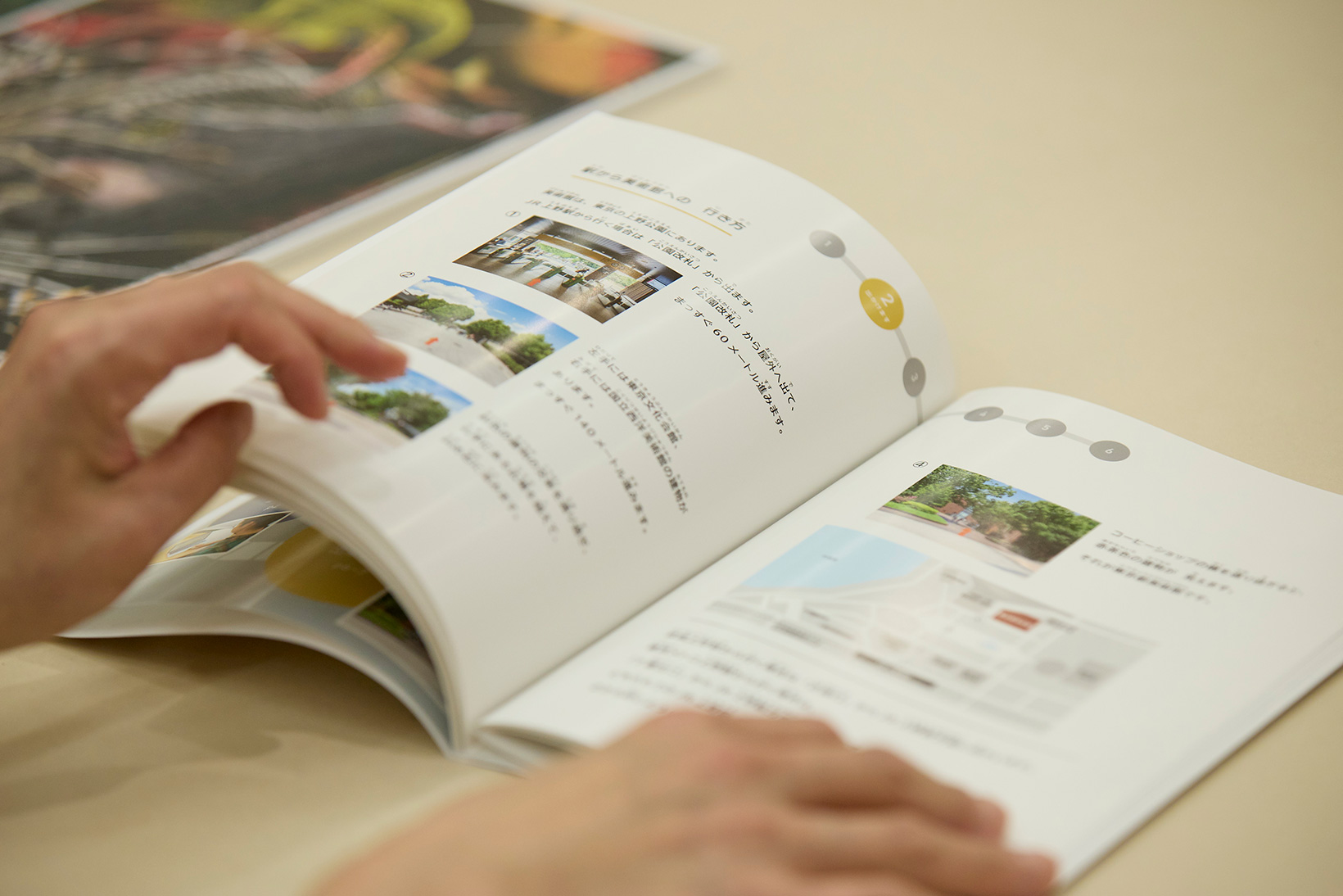
工藤 全部がはじめてのことなので、何が大変で何が大変じゃないのかもわからないくらいです(笑)。
毎月、東京都歴史文化財団内の各文化施設の社会共生担当が集まって、社会共生連絡会議が行われています。会議以外にも、仲間同士で情報を共有したり勉強会をしています。ここで気軽に相談できるのは大きいですね。
都美にはとびらプロジェクトがあって、多様なとびラーがいて。以前からアクセシビリティについて経験を積み重ねて来ています。他館の人が見学に来られたり、とびらプロジェクトのアクセス実践講座に他館の社会共生担当の方が参加しています。
<つづく>
「あの時の自分のためにやっている“べビミュー”」

「キュッパのびじゅつかん ーみつめて、あつめて、しらべて、ならべてー」展でのベビミュー実施の様子(2015年)撮影:とびらプロジェクトスタッフ
工藤 私は2期とびラーとして、2013年から3年間活動しました。友人が1年早くとびラーになっていたのですが、ちょうど障害のあるこどもたち向けのとびラボ「と・も・に」の企画が立ち上がっていて、「工藤さん、こういうことに興味あるんじゃない?とびラーやってみたら?」と声をかけてくれました。次男がまだ1歳になるかならないかの頃です。
私は、結婚する前の時期に、公立中学校の特別支援学級の介助員をしていたことがあります。もともと専門だったわけではなく、こちらも知人に「向いているからやってみない?」と紹介されました。これも何かの縁だと感じ、その翌日に現場へ見学に行きました。それから約3年間、知的障害のある子どもたちと朝からマラソンしたり、給食のおかわり競争をしながら毎日過ごしました。また、彼らの作る作品の面白さにも魅せられました。そのうち、中学校の3年間だけではなく、彼らの人生自体に関わりたいと思い、社会福祉士の資格を取るため、介助員を辞め、福祉関係の専門学校に通いました。無事に国家試験に合格して社会福祉士の資格を得たのですが、就職活動を始めた矢先に長男を妊娠して、そのまま就職できないまま2009年に出産。日々子育てに追われて、続いて2011年に3歳違いの次男も生まれて、そのままどっぷり子育てに専念して。必死に勉強して取得した資格を活かして就職することもできず、いわば肩書のない時代でした。産後鬱もかなり酷くて。もともと誰かとおしゃべりすることが大好きな私にとって、自由に外を出歩けず、ずっと自分の子供とだけ向き合うという、楽しいこともたくさんあるけれど、同時にしんどい時期でした。
工藤 私が発案したとびラボは、都美の授乳室とびラボです。
息子二人を母乳で育てていた私にとっては、外出先に授乳室があるかないかは切実な問題でした。母乳以外を息子たちが受け付けてくれなかったから、命綱だったんですね。だけど、出かけた先に授乳室が無かったり、たとえあっても殺風景で歓迎されている感じがしないと「なんでこんな思いしてまで外で授乳しなきゃいけないんだ」と気持ちが下がる経験を多くしました。息子に対しても「こんなところで、ごめんね」と、申し訳ない気持ちになってしまったりして。逆にウェルカムな感じの授乳室だと、「あなたはここにいていいですよ」と言われているように感じました。
そんな経験から、都美の授乳室に私たちのウェルカム感をいっぱいにしようと思いました。メッセージを書こうとか、イラストを描こうとか色々と考えましたが、いずれ私たちは開扉(とびラーが3年の任期を満了すること)してしまうし、どうしようかととびラボ内でたくさん話しました。
そんな私たちのアイディアがきっかけなのか、素敵なインテリアが導入されて、同伴される方向けに図録も置かれ、現在はとても心地よい空間になっています。
授乳室はハード面での環境整備についてのとびラボだったので、ソフト面でも何かできないかなと考えました。それが「ベビーといっしょにミュージアム」というとびラボに繋がりました。赤ちゃん連れの来館者と一緒に、都美のことを知り尽くしたとびラーが伴走し、作品を鑑賞するツアーです。通称「べビミュー」。
参加者はとびラーとペアになり、マンツーマンで作品を鑑賞します。赤ちゃんがお腹がすいたら途中で授乳室にご案内したり、おむつ交換できる場所をご紹介したり。ちょっと気分転換に休憩したりなど、それぞれの保護者と赤ちゃんのペースで動きます。
ツアーの目的は、赤ちゃんと過ごす家族とのアートコミュニケーションです。
子育て中は親同士のネットワークが重要ですが、その集まりの話題って、どうしてもお互いの子どものことがほとんど。特に私は、ずっと「育児脳」から離れられなくて、苦しい思いをしました。だからそこから解放できる時間をつくりたかった。作品を鑑賞しながら、「この作品いいよね」「こんなこと思い出しちゃった」と、育児から離れて、自分として誰かと話せる時間を大切にしたいと思っています。
そこで、一緒に鑑賞しているとびラーが育児アドバイスをしてしまうと、一瞬で「育児脳」に戻っちゃいますよね。なので、メンバーは育児アドバイスをしないように心がけています。

「BENTO おべんとう展―食べる・集う・つながるデザイン」ベビミュー実施の様子(2018年)撮影:とびらプロジェクトスタッフ
工藤 そうです。まさに私自身が、当時、育児以外のことを誰かとおしゃべりする時間を持ちたかったっていうのが出発点です。
工藤 任期満了後にも都美の展覧会や、他の美術館でも行っています。ありがたいことに、いまでは年間プログラムとして実施している美術館もあります。
うちの子どもたちは、もうすっかり大きくなりましたけど、あの時の自分の「孤立して、誰ともおしゃべりできない時間がつらかった」という感情や気持ちはむしろ宝物として大事にしていて、当時の自分を思い浮かべながら活動を継続しています。
<つづく>
「みんなの夢をひとつひとつ叶えていく」

工藤 はい。手話に興味を持ったきっかけは、とびラーとして参加した「障害のある方のための特別鑑賞会」でした。
特別鑑賞会でのとびラーは、その場にいて、作品を介してコミュニケーションをするのが大切な役割の1つです。当時、特別鑑賞会に毎回のように来てくれる7~8人のろう者の団体がいたんです。手話で会話しながら作品を見ていて、それがもう本当に楽しそうで。手話でおしゃべりしながら、にこにこ笑いながら作品見ているんですよ。静かなんだけど、とってもにぎやかで。
でも自分は手話がわからないのでその場に入れない。一緒に盛り上がりたいのに。手話という言語を持たない私はその輪に入れなかった。そんな自分が本当に残念で。
なんとか自分もその輪に入りたいと思って、開扉後に地域の手話講習会に通いはじめました。それ以来ずっと続けていて、今は地域の登録手話通訳者として市のイベントなどで手話通訳をすることもあります。いずれは手話通訳士を目指しています。ろう文化という世界を知って、ますます夢中になって、色々なろう者に会いに出かけています。

「きこえって何だろう?」とびラボの様子(2022年)撮影:とびらプロジェクトスタッフ
工藤 開扉してからも、ありがたいことに都美からは、アート・コミュニケータとしての活動の機会をいただいてきました。「BENTO おべんとう展―食べる・集う・つながるデザイン」や「伊庭靖子展 まなざしのあわい」のキッズデー、Museum start あいうえの の「キュッパ部」などでファシリテータとして声をかけていただいたり、ベビミューとしても展覧会でプログラムを実施する機会を頂いていて、とびらプロジェクトや東京都美術館との縁は続いていました。
仕事としては、2018年から就労継続支援A型事業所の生活相談員をしていたのですが、2021年夏に退職、その後、アート・コミュニケーション係の高齢者を対象とした事業(現在のCreative Ageing ずっとび)をサポートする臨時職員になりました。当時はコロナ禍でしたが、どんな環境でも明るく積極的に活動するとびラーたちの様子を見て、相変わらずパワフルですごい!負けていられないぞと感動したことを、今でも覚えています。
さらに翌年2022年の4月から、それまでの経験を生かして東京藝術大学の特任助手として、とびらプロジェクトのコーディネータになりました。
偶然なんですが、同じタイミングで、聞こえない・聞こえにくい3人がとびラーとして入ってきました。私はその頃も手話を続けていたし、聞こえない・聞こえにくい人たちの文化もある程度は理解していました。聞こえない・聞こえにくい人たちと、聴者の間の調整は、両方の言語がわかる私の役目かなと思いました。
ろう文化や手話への理解がまだまだ浸透していない頃は、聴者と、ろう・難聴者の間で色々なズレもありました。日々のちょっとしたズレみたいなものを、両者から受け止める。ろう・難聴者側に対しては、「こういう風に伝えたら理解が広がるんじゃない?」とか、聴者には「聞こえない世界というのは・・・」と、お互いに理解を促しつつ、とびラボの伴走や、講座の準備を具体的に進めて行きました。
ただ、手話通訳者にはならないように意識していました。
工藤 もし私が、コーディネータではなく手話通訳者になったら、すべての場に立ち会わないといけなくなりますよね。
「フラットな場」を目指すとびらプロジェクトは、とびラー同士、とびラーとスタッフとの対話を大切にしています。だから、ろう・難聴者と何か話しあいたい、何かを伝えたいと思った時に「手話じゃないとだめだ」とか、「今日は工藤さんが休みだから話しかけられない」となってほしくなかった。伝える手段は手話以外にもたくさんある。だから、とびラーやスタッフから「手話通訳者」を求められても、基本的には「あなたが直接伝えたら」「どんどん喋ればいいじゃん」と、直接やり取りすることを促しました。もちろん、その場で聞いていて話がズレているなと判断したら、お互いの言葉を仲介する翻訳者として間に入ることもありました。
そのせいかどうか、聞こえに関わらず、いい関係ができていきました。手話講習会に通い始めたとびラーやスタッフもいます。私は手話通訳者ではなく、緩衝材みたいな存在になろうとしたのだと思います。2年間、とびらプロジェクトがうまく回っていくことしか考えていませんでした。

工藤 所属はとびらプロジェクトの東京藝大特任助手から都美のアート・コミュニケーション係になりましたが、私のなかでは自分がとびラーとして活動していたころから全部地続きのような気がしています。今の仕事でたとえば「ろう・難聴者と聴者が一緒に鑑賞するのにどうしたら良いのか」を考えるとき、その根っこはすべてとびラーだった時代に生まれたものなんです。
ひとつだけ違うとすれば、今までは「こんなツールがあったらいいのに」と理想を呟くだけの立場だったのが、それを自分で段取りして実現する側になった、ということでしょうか。
私の周辺にも美術館への来館に様々な障壁がある家族や仲間がいます。具体的にその人たちの顔を思い浮かべています。産後鬱だった自分を思い浮かべながらベビミューの活動を続けているのと近い感覚です。
誰もが何のためらいもなく来館できるために、こんなことがあるといいな、と思うだけではなくて、具体的に進められる。
「あなたが手を動かしてやっていいんだよ」と言われている感じです。

工藤 あらゆる人が美術館に来て、一緒に過ごすために何が必要なのかを調べる、来にくい人が来られるためにはどんなことをすればいいか。どんなデザインをすればここに足を運びやすいか。そのためには、どんな仕掛けをしたらいいのか。そういうことを考えているうちに、いろんな発想がつながってきて。
仕事として「やらされている感」はなくて、すべての人にとっての「夢の美術館」に向かって一歩一歩進んでいるような感じですね。

東京都美術館の「バリアフリー・アクセシビリティ情報」はこちら
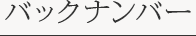


〝ゼロ期〟とびラー、主婦、2度目の大学生
2014-10


1期とびラー、区民ホール勤務、デザイナー経験あり
2014-10


とびらプロジェクト コーディネータ、立ち上げスタッフの一人
2015-01


2期とびラー、家庭と会社と3本柱
2015-01

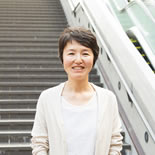
1期とびラー、家族で会社運営、もとテレビ局勤務
2015-02


大学で刑法を学び、広告業界を経た学芸員
2015-06


子育て中の1期とびラー、言葉にしない“共感”の名人
2016-02


2期とびラー、経験を持ち帰りながらテーマパークの運営会社に勤務
2016-05


3期とびラー、就活を経て出版社に入社1年目
2016-07


4期とびラー、美術館めぐりが趣味の仕事人。
2016-11


3期とびラー、タイでボランティアを8年間したクラフト好き
2017-01


現役藝大生の4期とびラー
2018-04


「幹事大好き」の4期とびラー
2018-04


最年長の70代。5期とびラー
2019-05


「とにかくやってみる」ことを楽しむ5期とびラー
2019-06


人と人をつなぐ回路をつくる、プログラムオフィサー
2020-01

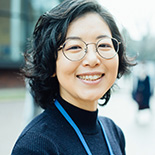
私にできることってなんだろう?「関わること」を大切にする6期とびラー
2020-10


「障害のある方のための特別鑑賞会」の先に、美術館の未来をみる6期とびラー
2020-11


「より創造的な体験」をとびラーと一緒に作り上げる、とびらプロジェクト コーディネータ
2021-04
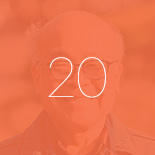

7期とびラー。「笑顔」を絶やさないお茶目な伴走者
2021-06


「できないことじゃなくてできることをやる」転んでもただでは起きない7期とびラー
2021-07


誰の意見も素直にきける「コミュ力」抜群のバランス系7期とびラー
2021-08


「生みの親」がプロジェクトとともに歩んだ10年
2022-07


Museum Start あいうえのから「循環した学び」を得た直感の人。8期とびラー
2022-08