
2025.03.17
執筆:11期とびラー 曽我千文
◇上野は日本初の都市公園
東京都美術館に行こうとJR上野駅公園口改札を出ると、そこはもう上野恩賜公園(以下:上野公園)です。東京都美術館は上野公園の中にあるのですが、たいていの場合、噴水広場を横目でみながら、駅と美術館の間を歩くだけで、公園全体の様子をみる機会は少ないのではないでしょうか。
上野公園は面積54ヘクタール。東京ドームの約11個分の広さがあり、2023年に開園150年を迎えた日本で一番古い都市公園のひとつです。上野のお山から、斜面を下った不忍池まで、実に多くの見どころにあふれ、歴史と自然を楽しむことができます。
私たち東京都美術館のアート・コミュニケータ「とびラー」も、せっかくいつも訪れている上野公園のことを、もっとよく知ってみようと「上野公園探検隊」を結成し、2022年度から2024年まで7回の探検を行いました。
◇上野公園のはじまり
上野公園があるところは江戸時代、東叡山寛永寺の境内地でした。それが明治維新後に官有地となり、明治6年の太政官布達(国の政治機関が府県に対し、公園という制度を発足させるので、「群集遊観ノ場所」などのふさわしい土地を選定してうかがい出るようにといったお達し)によって、日本で初めての公園に指定されました。
当初は社殿と霊廟、東照宮と桜を中心にした場所でしたが、その後、博物館や動物園、美術館などが建てられ、多くの文化施設が集まった世界でも希代の場所に発展しました。
江戸時代、家康、秀忠、家光の三代にわたる将軍に信頼された天海僧正によって開かれた、東叡山寛永寺には、京都や滋賀の名所に見立てた建物や景観が多く作られました。延暦寺にならって寛永年代から名を取った寛永寺。琵琶湖と竹生島を見立てた不忍池と弁天島。清水寺を見立てた清水観音堂。方広寺に見立てた大仏。上野の代名詞である花見の名所も、天海僧正が吉野山の桜を取り寄せて植えたのが始まりだそうです。
そんな上野の歴史や自然について、東京都美術館のアートスタディルームでスライドを使って、基本情報を共有した後に探検に出発しました。
2023年度には、探検のまとめとして、参加したとびラー全員で、発見したこと興味を持った思ったものを1人2つずつあげて、かるたを作りました。最初に五十音を任意に割り振られた文字を使って、詠み札の文を考えるのに苦労しましたが、楽しいこと、おもしろいものが大好きなとびラーたちの力作になりました。その「上野公園探検かるた」の一部をご覧にいれながら、探検の様子をご紹介します。
◇間違えられた公園の父
東京都美術館を出てすぐ、動物園正門の前には、ここでしか見られないパンダのポストがあります。2011年、東日本大震災の被害に悲しむ日本に明るい話題を提供してくれたリーリーとシンシンの公開を記念して建てられました。さて、ここでクイズです。「パンダのしっぽは黒でしょうか白でしょうか?」早速パンダポストで確認しました。当たった人も知らなかった人も嬉しそうです。
噴水広場のスタバの隣にある桜の木。これは上野公園で発見された新しい品種のサクラで、白花のしだれ桜です。公募で「ウエノシラユキシダレ」という名前が付けられました。ソメイヨシノより少し早い時期に白い雪が降るように咲くので、ぜひ、花の時期に見に来てください。
「真っ白な花が楽しみ。」
「貴重な木なのに、ヒョロヒョロで、枯れちゃうのが心配。」
などの声があがりました。枝から後継樹も育てられているそうです。
上野白雪しだれの少し北よりには、ボードワン博士の胸像があります。西洋医学を伝えるため来日したオランダ人の医師ボードワンは、明治政府から上野に東大医学部の前身である西洋医学所を建てる計画に意見を求められた際に、上野の貴重な緑地は公園にして残すべきだと進言したため、「上野公園の父」と言われています。ちなみにこの銅像は、上野公園開園100年に当たる1973年に、写真の間違いから、先に来日していた弟さんの像を建ててしまい、2006年になってから本人の像に替えられたエピソードがあります。
「そんなことってあるの?」
と一同大うけでしたが、オランダ領事を務めていた弟さんの像は、現在は神戸のポートアイランド北公園で海を見つめていると聞いて、ほっとした笑顔が見られました。
◇リニューアルした公園口広場
JR上野駅公園口を出た広場は、令和2年にリニューアルされました。それまで、駅の正面には、往来の激しい車道があって、信号待ちの乗降客で混雑していたのですが、当時を知るとびラーからは、
「本当にここは快適になった、前は危なかった。」
と声があがります。現在は、広場の南北に造られたロータリーで車はそれぞれ行き止まりになっており、駅を降りた来園者が、安全で快適に公園に入れるようになりました。上野駅も一緒に、改札口が北寄りに改修されて、改札から上野動物園の正門が、まっすぐ正面に見えるようになりました。
駅を降りると、左手には東京都美術館と同じく前川國男設計の東京文化会館、その向かいにはル・コルビュジェ設計の世界文化遺産に指定された国立西洋美術館があります。とびラーたちはひととき、西洋美術館で見た展覧会の話題に花を咲かせていました。
◇西郷さんは西郷さんに似ていない?
東京文化会館の裏手から桜広場に進むと、上野寛永寺の祖である天海僧正の毛髪塔があります。なんと108歳の長寿だったそうで、お墓は家康と一緒に日光東照宮にあるそうです。
隣にあるのは、上野戦争で幕府の降伏と江戸城無血開城に納得せず、上野戦争で明治新政府軍に敗れた悲劇の侍たち「彰義隊」のお墓です。
「上野戦争や彰義隊のことは今まで知らなかった」
「そんな悲しい歴史が上野にあったんですね」
と江戸時代終焉時の志士に思いを馳せて手を合わせました。
その先、上野台の先端には有名な西郷隆盛像があります。意外にも、知っていたけど見るのは初めてという人が多くいました。西郷像は「西郷さんに似ていない」という説があるのですが、西郷さんは写真嫌いだったため、有名な肖像画も弟と従弟の姿を参考にして描かれたものなので、そう言われているようです。西郷像の除幕式で、奥さんが『あれまあ!うちの人はこんなお人ではなかったのに!』と言ったのがことの起こりらしいのですが、奥さんは着流しの姿で兎狩りをしている西郷像の身なりが気に入らなかった、もっときちんとした人だったと言いたかったというのが本当のところのようです。とびラーはみな、この像が兎狩りの様子だということに驚いていました。確かに、のんびりと犬の散歩をしているように見えます。
上野のランドマーク、西郷さん像とその周辺を詠んだ探検かるた。彰義隊の墓や、花見のにぎわいも有名です。
上野に大仏があるのをご存じでしょうか。天海僧正が、京都や滋賀の風景を見立てて、江戸に再現したもののひとつが大仏です。この大仏は安政年間の地震や、関東大震災などで何度も頭部が落ち、現在では顔面部しかないため、「これ以上落ちない」ということで受験生に人気があります。「合格祈願」の文字が書かれた桜の花の形の絵馬がたくさんかけてあるのを見て、
「お顔だけになってしまってかわいそう。」
「ご利益ありそうだから受験生に教えてあげなくては。」
と知られざる名所にわいていました。
◇上野の洞窟・穴稲荷
外国からの観光客で大変にぎわう、朱塗りの鳥居が並ぶ花園稲荷神社の細い参道は幻想的で、下っていくとどこか違う世界に入っていきそうです。下りた右手に社殿があり、左手の斜面に探検隊の心が騒ぐ秘密の場所、洞窟がありました。鉄格子の扉を開けて中に入るとそこが、寛永寺を建てる際に、天海僧正が住処を失ったきつねを哀れんで掘らせた穴稲荷です。
「まさに秘密の場所ですね。扉の中に入れるとは知らなかった」
「東京の真ん中で、異次元の世界に入る気持ち」
と、どきどきしながら一人ずつ、暗く、ひんやりとした通路をそろそろと進み、薄明りに照らされた祠に、静かに手を合わせてきました。
このあたりの上野台の斜面林は、はるか昔に不忍池が海だった名残で、海岸沿いに育つシイやタブの木が多く見られる環境で、大きな木々が神社を包んでいます。
◇絶景かな清水の舞台
山の上から不忍池を見下ろすように、京都清水寺を見立てて作られたのが清水観音堂です。清水の舞台のすぐ下には、広重の「名所江戸百景」にも描かれた、太い枝をぐるりと輪の形に仕立てた「月見の松」があります。明治の初めに、台風の被害で松は失われてしまったのですが、江戸の風景を復活させようと、2012年に150年ぶりに植えられたものです。輪をのぞくと、下に不忍池の辨天堂がちょうど見え、みんな江戸時代にタイムスリップして、代わるがわるに写真を撮っていました。
桜の名所で有名な上野公園ですが、園内に50種類以上のサクラが植えられており、ソメイヨシノを中心に、早咲きと遅咲きのサクラの花を長い期間楽しめるようになっています。探検を行った2月にも、早咲きのカンザクラの花に、メジロが蜜を吸いにきていて、かわいいしぐさに癒されました。
花の蜜を吸うメジロは人気者。不忍池を見下ろす清水観音堂の月の松。辯天堂の龍の天井画に歴史を感じます
◇弁天島は発見がいっぱい
清水観音堂から階段を下ると不忍池の畔に出ます。不忍池の中央には、琵琶湖の竹生島を模して造られたという島があり、弁財天を祀る弁天堂があります。不忍池の弁天様は、八本の腕のそれぞれの手に煩悩を破壊する武器を持ち、頭上には「宇賀神」という人頭蛇身の神様を乗せています。宇賀神像はお堂の手前にもあり、今年は巳年ということもあり、関心が集まっていました。
お堂の天井には、児玉希望画伯による迫力のある龍の天井画が描かれ、とびラーが集まって拝見していると、誰からともなく対話型鑑賞が始まりそうでした。
弁天堂の周囲には、「ふぐ供養碑」、「魚塚」、「スッポン感謝之塔」「包丁塚」など、様々な供養塔や記念碑がたくさんあります。「めがねの碑」には徳川家康の愛用した眼鏡がかたどられていますし、「暦塚」は日時計になっています。
「徳川家康って眼鏡かけていたの?」
「小学校に日時計があったわ。正確に時間を示しているんですね。」
と、ひとつひとつをじっくり見てまわりながら、誰がいつ、何を思って建てたのか、碑文を読みながら楽しんでいました。
◇上野の自然とパワースポット
弁天島を西に渡ると、左手にスワンボートが浮かぶボート池、右手が上野動物園の区域の鵜池です。水辺には冬を日本で過ごすカモやカモメ、カワウなどがたくさんいて、望遠鏡を使ってバードウォッチングを楽しみました。
「人手が多いのに不忍池にはたくさん野鳥がいるんですね。」
「パンダに似ているかわいいキンクロハジロちゃんの大ファンになりました」
園内には随所に大木があり、丹精を込めて管理された季節の花壇や、所々では「いいにおい!」と花の香りに立ち止まり、普段気づかなかった上野の自然を満喫することができ、
「桜だけじゃないんですね。知らない植物などをもっと知りたいと思った」
「新しい品種の木や、植物の手入れの様子、花といっても知らないことが多かったです。」
という声も聞かれました。
望遠鏡をのぞいて初めて見る野鳥の美しさを堪能
東京都美術館に戻る途中、最後に噴水広場で上野のパワースポットを探しました。駅改札と動物園正門を結ぶ線と、東京国立博物館と桜通りを結ぶ線の交点、上野のおへそです。みんなで下を見ながらうろうろ。
「あった!これだ!」
石の舗装に小さく「+」が刻まれているのを見つけました。
「今後は都美への行き帰りには必ずや秘密のパワースポットでエネルギーchargeすること間違いありません。」
「+印のパワースポットで定期的にエネルギーチャージしたいと思います。」
と、みんなで代わるがわる+印の上に立ち、なんだか足取りも軽く、都美へと帰る探検隊でした。
◇探検を終えたとびラーたちの感想
東京都美術館に戻り探検をふりかえると、みんなそれぞれに印象に残った場所が違い、上野公園の見どころの豊かさを感じました。身近に思っていた上野公園も、みんなで探検することで知らない世界を見つけることができたようです。
「いつも通り過ぎるだけだった場所も、がぜんクッキリと見えてきました」
「上野の奥深さを改めて認識」
「行ったことのないエリア、本当に知らないことばかりで、上野をより知ることができた」
「たくさん発見をしたので、ますます上野公園が身近になりました。」
「今度1人でゆっくり上野公園を回ってみようかなと思います。」
「みなさんといっしょにおしゃべりしながらの探検、楽しい時間でした」
「季節ごとの上野を味わいながら歩いてみることの楽しさを実感」
「銅像から伝統や文化を知り、自然を感じることができた」
「時代毎のニーズなどを踏まえて公園が変化していく様子を知ることができて面白かった」
「みんなと見ると楽しい、ちょっとしたつぶやきから発見が広がりました」
3年間、とびラーと上野公園の探検を続けてきました。観察力が鋭く、楽しむことに長けた仲間と歩いていると、少し詳しいつもりになっていた公園に、こんなにも新しい疑問や発見が湧いてくるのかと、わくわくの連続でした。上野公園が奥深いのは、江戸時代から続く様々な人や自然のドラマが集積されているからだと思います。多くの文化施設が集まり、今日もたくさんの人でにぎわうのも、自然の摂理なのかもしれません。とびラーの活動も、この上野公園の歴史の一ページになっていけたらと思いました。
みなさんもぜひ新しい発見を見つけに、上野公園の探検にいらしてください。
執筆:とびラー11期 曽我 千文
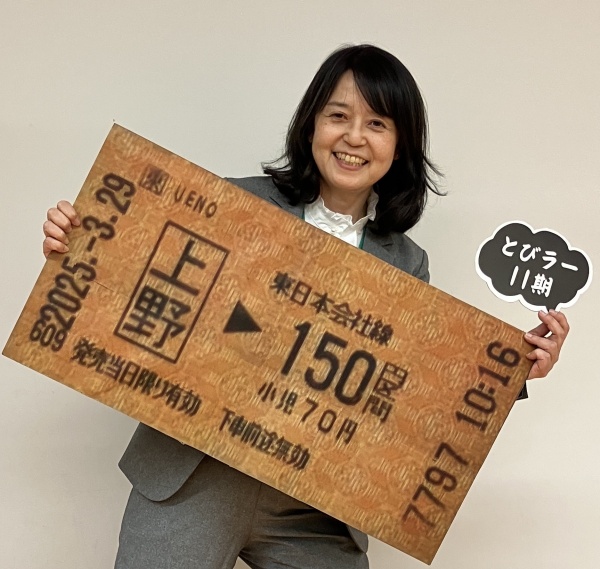 公園を造ったり管理したりする仕事をしています。公園の中にある大好きな東京都美術館でとびラーとして活動できた3年間は至福の時代でした。公園と美術館という、どちらも幸せの場所で、みんなに幸せになってもらうために歩き続けたいと思います。
公園を造ったり管理したりする仕事をしています。公園の中にある大好きな東京都美術館でとびラーとして活動できた3年間は至福の時代でした。公園と美術館という、どちらも幸せの場所で、みんなに幸せになってもらうために歩き続けたいと思います。
2025.03.01
東京都美術館では「とびラーによる建築ツアー」をおこなっており、「とびらプロジェクト」で活動するアート・コミュニケータ(とびラー)がガイドとなって、グループに分かれて対話しながら東京都美術館を散策します。今年度は6回開催しました。
この建築ツアーでは決まったコースがありません。とびラーたちは事前にお互い相談しながら、当日の館内の状況や混雑具合、天候などを想定して、コースや話す内容を考えています。しかし予期せぬことは起きるものです。コースを臨機応変に変更をしたり、参加者の興味に合わせて話題を転換したりできるように準備して、参加者をお迎えしています。
全6回の様子の一部をご紹介します。
第1回(5月12日開催)の様子
おひとりで参加する方や親子連れなど、様々な参加者がいるのも「とびラーによる建築ツアー」の楽しいところの1つです。最初にグループみんなで簡単にお話し、緊張がほぐれてからスタートします。
第2回(7月20日開催)の様子
暑さが本番になった7月。とびラーは、館内や木陰などを多く取り込むなど、暑さを考慮したツアー構成をそれぞれ考え、臨みました。
第3回(9月21日開催)の様子
どうやって東京都美術館の建物を味わってもらおうかと、とびラーは毎回考えています。実際に触ったり、じっくり眺めたりする時間を設けるグループもありました。
第4回(11月23日開催)の様子
「とびラーによる建築ツアー」は対話をしながらツアーを進めていきます。とびラーたちも参加者とのコミュニケーションを毎回楽しんでいます。
第5回(2025年1月25日開催)の様子
建物を紹介する上で、難しい言葉や聞き慣れない言葉を使う必要があるときがあります。とびラーたちはフリップや資料を用意して、参加者にわかりやすくお伝えする工夫をしています。
第6回(3月1日開催)の様子
今年度最後の建築ツアーでは、手話でお話しする方にも建築ツアーを体験してもらおうと、手話対応グループを1つ設けました。難聴のとびラーがガイドとなり、日本語対応手話を使って東京都美術館の魅力を紹介しました。ほかにも、ろう者や聞こえにくい方が参加される場合は、UDトーク(音声認識技術を使って会話やスピーチをリアルタイムに文字起こしするアプリ)を使ってガイドを実施しました。
「とびラーによる建築ツアー」では、ガイドによって紹介する見どころはさまざまです。そして、季節によって東京都美術館を囲む上野公園の四季折々の美しさも異なります。
参加するたびに新たな発見に出会える建築ツアーとなっていますので、ぜひみなさんのご参加をお待ちしております!