
2025.07.10
第1回建築実践講座|「都美の建築と歴史と楽しみ方」
日時|2025年7月5日(土) 10:00〜15:00
会場|AM:東京都美術館 講堂/PM:東京藝術大学 第3講義室
講師|河野佑美(東京都美術館 学芸員)
1925年に閉館した「旧館」の当時の様子や、1975年に「新館」として建設された東京都美術館の建設に至るまでの経緯など、東京都美術館の建物や歴史について、東京都美術館 学芸員の河野佑美さんにお話しいただきました。
また、建築ツアーが生まれた経緯や建築家ではない人がツアーを作り上げていくことについても、河野さんの経験を交えながら熱く語っていただきました。
「新館」建設にあたり、建築家として抜擢された前川國男。彼が東京都から与えられた、幾つものミッションを全てクリアして建てられた現在の東京都美術館にはたくさんの魅力があります。
そんな、東京都美術館の魅力を河野さんが撮影した写真を見て、お話を聞いて味わった後は、とびラー同士で東京都美術館のオススメポイントを紹介するシェアタイムを行いました。
自分のオススメポイントを他のとびラーと共有し、新たな見方や発見ができる時間となりました。
「初めて知った!」・「ここ私も好きな場所」・「同じ場所でも、時間と天気で見え方が違って見えるんです」と楽しそうにお話をしているとびラー達が印象的でした。
東京都美術館で実施している「とびラーによる建築ツアー」は、2012年のリニューアル時におこなった館内ツアーがきっかけで始まりました。
建築家が込めた想い、歴史、建物の色・デザインといった建築を楽しむポイントを切り口に、とびラーと対話しながら味わいます。
ガイドによって、ツアーの内容が変わるのも魅力の一つです。
そして午後は、「とびラーによる建築ツアー」を体験しました。
ガイド経験者のとびラーがガイドとなり、参加者のとびラーと都美館内を45分間で巡りました。
ツアーの後は、各チームごとにふりかえりをおこない、ツアーの感想や印象的だったことシェアしました。
今回、初めての建築ツアーに参加したとびラーは、「こんなに楽しいなんて!」・「45分があっという間だった」とお話ししていました。
最後に1日を通じての感想を共有して、私たちの拠点となる東京都美術館への関心を深めていきました。
(とびらプロジェクト コーディネータ 大東美穂)
2025.07.05
【第6回基礎講座 この指とまれ/そこに居合わせる人が全て式/解散設定】
日時|2025年6月21日(土)10時~15時
場所|東京藝術大学 美術学部 中央棟2階 第3講義室
講師|西村佳哲
内容|とびラーは、自分たちの関心を寄せ合い、アイデアを共有し、プロセスを大事にしながら活動をつくります。この回では、小さく始めるプロジェクトのつくり方や、そこに集まった人みんなの力を活かした活動について学びます。また、活動のはじめ方だけではなく、終わり方のデザインについても理解を深めます。
基礎講座最終回は「とびらプロジェクトの活動の進め方」がテーマです。
特に、とびラーはこの後「とびラボ」というとびラー同士が自発的に開催するミーティングのことで、新しいプロジェクトの検討と発信が行われる場をつくっていきます。
そんな「とびラボ」の「はじめ方/すすめ方/おわり方」や「あり方」について考えました。
講義は西村さんと、とびらプロジェクト マネジャーの小牟田さんのクロストーク形式で進みました。
「この指とまれ式」
新しい活動のアイデアをひらめいたとびラーは掲示板で一緒に活動するとびラーを募集します。3人以上集まったら「とびラボ」のスタートです。
このはじまり方を「この指とまれ式」と呼んでいます。
西村さんや小牟田さんから
・適正人数(グループサイズ)を考えること
・指を立てた人、集まった人同士の想いや視点をよく確かめ合うこと
・成功を目的化しない、プロセスを大事にすること
の3つのポイントが伝えられました。
「人数が多いと感じたり、やりたいことが違っていたりしたら別のラボに分かれてもいい」というお話に「へえー」とうなずくとびラーもいました。
今回の基礎講座も講義の合間にペアで考えたことや疑問点について話し合う時間が多くあります。早速、「この指とまれ式」について活発に話し合いました。
「そこに居合わせる人が全て式」
「とびラボ」では集まった人同士の想いや視点を確かめ合ったあと、いまここで「やりたい・できる・やるべき」アイデアを生み出し育てていきます。
一般的な活動がやるべき事や問題点からアイデアが生まれ、必要な事を考えていくのに対して、「とびラボ」はそこにいる人からアイデアが生まれます。
西村さんの「今夜冷蔵庫にあるもので、なにか美味しいものをつくる」という例えに納得したとびラーも多かったのではないでしょうか。
また、「とびラボ」をすすめる上での新たな試みとして、ミーティングの最後に内容と過程についてふりかえる時間を設けることが西村さんから提案されました。
内容のふりかえりでは、決まったこと、重要なこと、まだ検討が要ることについてを、過程のふりかえりでは、ミーティングの進め方、進み方についてを話し合います。
実際に、今回の講座のここまでの過程をふりかえってみると、
「ペアで話し合う時間があることで疑問が共有できる、けど忙しい」
「1人じゃなくて2人のクロストーク形式だからわかりやすい」
など進め方について色々な意見が出ました。
14期にはきこえない・きこえにくいとびラーがいます。聞こえやコミュニケーションの方法はそれぞれ違うため、ミーティングの進め方も一様ではありません。全員がやりやすい方法をその場にいる全員でその都度考えることが大切であるという認識を共有しました。
「解散」
活動の目的を達成して成果をとびラー自身がふりかえることができたら、その「とびラボ」は解散します。
普段の生活で「終わらせること」を意識する機会はあまりないかもしれません。
「反省会にならないように」という小牟田さんの言葉を受け、「創造的な解散」とはどういうことか考えました。
とびラボ実践編
まず、西村さんから「アイデアとは、既にあるもののあたらしい組み合わせである」というお話があり、アイデアを紐解いてみるワークに移りました。
既存のアイデアは何が組み合わさったものなのか?
たとえば歌番組のように、それぞれ思いついた身の回りのアイデアを紐解き、自分の発見を楽しそうにシェアする様子が印象的でした。
続いて、とびらプロジェクト コーディネータの越川さんから過去の「とびラボ」の事例を聞きました。
アイデアが生まれ活動へとつながっていく過程を具体的にイメージすることができたのではないでしょうか。
全6回にわたる基礎講座、お疲れ様でした!
基礎講座を終えられた今、どのようなお気持ちでしょうか?
「よし、どんどん活動していくぞ!」という方もいれば、
「まだ全然わかんない、果たしてやっていけるのか、、、」という方もいらっしゃると思います。(こちらの方が多いかも?)
東京都美術館のミッションのもと、とびラー・都美スタッフ・藝大スタッフが一体となってとびらプロジェクトの活動をつくっていきましょう!
(とびらプロジェクト アシスタント 三原凜子)
2025.07.04
【第5回基礎講座 ミュージアムとウェルビーイング】
日時|2025年6月7日(土)10時〜15時
場所|東京藝術大学 中央棟2階 第3講義室
講師|中原淳行(東京都美術館学芸員 学芸担当課長)
小牟田悠介(東京藝術大学 芸術未来研究場 ケア&コミュニケーション領域 特任助教)
熊谷香寿美(東京都美術館 学芸員 アート・コミュニケーション係長)
内容|第5回目の基礎講座では、とびラーの活動拠点である東京都美術館のミッションとその背景について学芸員から話を聞きます。また、展覧会の鑑賞を通して、ミュージアムにおけるウェルビーイングについて考えます。
・東京都美術館のミッションができるまでの背景とは?
・ウェルビーイングとは何か?
・ミュージアムってどんなところ?
東京都美術館のきのう・今日・あした
東京都美術館は2012年のリニューアルオープンに合わせて新たなミッションを掲げ、そのミッションに基づいて様々な事業を展開してきました。
東京都美術館の使命(ミッション)
東京都美術館は、展覧会を鑑賞する、子供たちが訪れる、芸術家の卵が初めて出品する、障害のある方がなんのためらいもなく来館できる、すべての人に開かれた「アートへの入口」となることを目指します。
新しい価値観に触れ、自己を見つめ、世界との絆が深まる「創造と共生の場=アート・コミュニティ」を築き、「生きる糧としてのアート」と出会う場とします。そして、人びとの「心のゆたかさの拠り所」となることを目指して活動していきます。
基礎講座第5回目の午前の時間では、ミッションの策定に携わった学芸員の中原淳行さんから、言葉に込めた想いや、中原さんの原体験となったミュージアム体験についてとびらプロジェクト プロジェクトマネジャーの小牟田さんがきき役となってお話を伺いました。
とびラーは3人組に分かれて、感想のシェアタイム。
中原さんの当時の記憶を順を追って丁寧に言葉にして話されていく様子に魅き込まれながら、自身の忘れられないミュージアム体験や、東京都美術館のミッションを改めて読んで感じたことについての話など、盛り上がっていました。
来年に100周年を迎える東京都美術館が、これから何を目指していくのかについてもお話は展開し、中原さんからの「これからが楽しみですね」という投げかけに、大きくうなづくとびラーの姿が印象的でした。
展覧会を体験する
午後は、とびらプロジェクト マネジャーの熊谷さんから「ミュージアムってどんなところ?」というテーマで、展覧会の空間は、作品といい出会いができるようにデザインがされているというお話で始まりました。
その後、東京都美術館で開催中の「ミロ展」(会期:2025年3月1日(土)〜7月6日(日))を、空間構成やストーリーに注目して、鑑賞をしにいきました。本展覧会の特徴は、個展としてミロの生涯を通した作品の変遷を体感できるところにあります。
展覧会に行く前にとびラーには熊谷さんから、
・ミロとどんな風に出会いましたか?
・どの時期の作品に一番共感しましたか?
という2つの問いをもって、50分間じっくりと鑑賞しました。
鑑賞から帰ってくると、再び3人組に分かれて、印象に残った作品について共有していきます。
「私もその作品に共感した!」「なるほど、そういう視点もあるか!」とさまざまな感想が交わされました。
ミュージアムとウェルビーイング
最後に熊谷さんから、ミュージアムとウェルビーイングがどのように繋がっているのかについて、とびらプロジェクト、Museum Startあいうえの、Creative Agingずっとびでの実践も題材にレクチャーがありました。
どの状態がウェルビーイングなのかは、人によって、国の文化によって、時々によって違うのではないかという問いかけに、自分にとっての「良い状態」はどんなときであるのかについて、改めて考える時間となりました。
活動の拠点である東京都美術館では、なぜ3つのプロジェクトを行っているのか。
東京都美術館のミッションを出発点に、ミュージアムでの市民の関わりとしてアートコミュニケータが生まれた背景とその意義について、世界的なミュージアムの潮流もふまえながら、これからの活動の拠点について考える時間となりました。
基礎講座も残すところあと1回。
今までの基礎講座での学びが積み重なって、今日の活動にも生きてきているように感じます。
次回の講座では、とびラボの特徴でもある「この指とまれ/そこにいる人が全て式/解散設定」に込められた意味について、考えていきます。
(とびらプロジェクト アシスタント 久保田夢加)
2025.06.15
【第4回基礎講座 会議が変われば社会が変わる】
日時|2025年5月24日(土)10時~15時
場所|東京都美術館 交流棟2階 アートスタディルーム
講師|青木将幸
内容|とびラーの自主的な活動には、直接コミュニケーションをとるミーティングの場のあり方がとても重要です。ひとりひとりが主体的に関わるミーティングの場をつくるために、ミーティングの理想的なスタイルや具体的な手法を、レクチャーやワークショップを通して学んでいきます。
とびらプロジェクトでは、とびラー同士が自発的に開催するミーティング「とびラボ」があります。さまざまな関心を持った多世代の人が集まってアイディアを重ねるため、とびらプロジェクトではミーティングを大切にしています。今回の講座では「グッドミーティング」(良い会議)について考えました。
午前中は青木さんの「好物は何ですか?」という問いかけから始まりました。
とびラーは少し戸惑いながらも自分の好きな物を絵に描いていきます。その後自分が描いた絵をもって歩き回り、お互いの好きな物をについて尋ね合いました。
次にジェスチャーを使っていまの状態を表現してみます。
「今日の元気は50%。昨日寝るのが遅かったから、、、」「今日は80%くらい。元気だけどマラソンは走れない!」などなど色々な声があがりました。
ジェスチャーで共有することでミーティングに参加している人全員がいまどういう状態なのかを確認することができます。
場が温まってきたところで「グッドミーティング」と「バッドミーティング」について考えていきます。
まずは、一人一人が思う「グッドミーティング」と「バッドミーティング」がどんなものかを紙に書き出していきます。
書き出した後、同じグループ内で回し読みをして共感するアイデアにハートマークをつけ、最後に1枚の紙に「グッドミーティング」と「バッドミーティング」についてグループごとに話し合ってまとめました。
また、今回の講座では事前に「これを持って行くとグッドミーティングになるかも!と思うものを持ってきてください」と呼びかけられていました。お菓子やぬいぐるみ、おもちゃ、お香などさまざまなアイテムが持ち寄られ、場を和ませていました。
考えやアイテムをみんなで持ち寄ることで「誰もが貢献できるミーティング」が生まれていきました。
午前中の最後には会議の4つの段階、「共有・拡散・混沌・収束」について青木さんからお話がありました。先ほどのミーティングを思い出しながら、4つの段階それぞれの役割や重要性について考えました。
午後は、実践です。みんなで話したいお題を出し合い、好きな話題を選んでミーティングをしました。
最後にそれぞれのミーティングで話し合った内容を全体で共有しました。
自分たちで考え、導き出した「グッドミーティング」を意識しながら進めることで、納得感を持ってミーティングを進められたのではないでしょうか。また、第2回基礎講座の「きく力」を思い出したとびラーも多かったかと思います。
とびラーの自主的な活動には、そこに参加する人全員が意見を出し合えるミーティングの場のあり方がとても重要です。
今回の内容を思い出して参加者全員で「グッドミーティング」をつくりあげていきましょう。
(とびらプロジェクト アシスタント 三原凜子)
2025.05.14
・
・
【第3回基礎講座 作品を鑑賞するとは】
日時|2025年5月10日(土)10時~15時
場所|東京都美術館 交流棟2階 アートスタディルーム
講師|熊谷香寿美(東京都美術館 学芸員 アート・コミュニケーション係長)
内容|作品の鑑賞について理解を深めます。作品が存在することによって起こる体験とは、私たちにとってどのように意義があるのか、それらを鑑賞することの意味についても考えてみます。
・鑑賞とは何か?
・複数で鑑賞することとは?
・
・
鑑賞を知る・体験する
・
作品を鑑賞することは、美術館を拠点にアートを介してコミュニティを育むとびらプロジェクトの基盤となる活動です。
基礎講座3回目では、「作品を鑑賞すること」を考えるレクチャーとともに、 美術館で実際の展覧会の作品を鑑賞しながら講座を行いました。
・
・
・
・
午前の体験
・
午前中は、とびらプロジェクトマネージャの熊谷さんからレクチャーを聞いた後、1つの作品をじっくり鑑賞する体験をします。
鑑賞するのは、講座当日に東京都美術館 公募棟で開催されていた「東光展」(会期:2025年4月25日(金)〜5月10日(土))です。
とびラーは展示室を1周した後それぞれお気に入りの作品を選び、約30分間じっくり向き合いました。
展示室から帰ってくると、自分が選んだ作品について考えたこと・感じたこと・気がついたことをグループでシェアします。
同じグループのメンバーの気づきに対して、
「そんなこと全然気がつかなかった!」「視点が面白い!」と、驚く声が多く聞こえてきました
・
・
・
午後の内容
・
午後は1つの作品を複数人でみていく体験をします。
鑑賞するのは神奈川県立近代美術館所蔵、松本竣介《立てる像》の図版を使ったアートカードです。
描かれている人物の表情や身体の部分、背景などに注目してグループで作品について話し合いました。
同じグループのメンバーの気づきを
「ああ〜」「なるほど!」「確かに、、、」と、
きくことを通して鑑賞が育っていく様子が印象的でした。・
・
・
今回の講座ではとびらプロジェクトの特徴でもあるお互いに話をききあうことのできるコミュニティでの「共同的な学び」が、複数の人で作品を鑑賞する上でも重要になることについて考えました。
・
基礎講座も折り返し地点をむかえました。
回を重ねるごとに雰囲気が和らぎ、場が盛り上がっているように感じます。
後半3回の講座では、アートを介したコミュニティのあり方・活動の作り方についてみなさんと考えていきたいと思います。
(とびらプロジェクト アシスタント 三原凜子)
2025.05.07
【第2回基礎講座 「きく力」を身につける】
日時|2025年4月26日(土)10時~15時
場所|東京藝術大学 美術学部 中央棟2階 第3講義室
講師|西村佳哲
内容|コミュニケーションの基本は、上手な話し方をするのではなく、話している相手に、本当に関心を持って「きく」ことから始まります。この回では、人の話を「きく力」について考えます。
・話を〈きかない〉とはどういうことか?
・話を〈きく〉とは? また、それによって生まれるものとは?
基礎講座の第2回は「きく力」がテーマでした。
この「きく力」はとびらプロジェクトが大切にしていることのひとつで、毎年1年目とびラーはこの講座に参加します。
西村さんからレクチャーと、とびラー同士でのシェアする時間をはさみながら講座が進んでいく進め方の説明や、「きく力」についての導入がありました。
講座では3人組になる場面が多くあります。
自己紹介が終わると「はい、解散!」と、新たな3人組になり、コミュニケーションの輪が広がっていきます。
場が和んだところでいよいよ本題です。
まずは、西村さんと、とびらプロジェクト コーディネータ 大東さんがロールプレイを行いました。
話し手の大東さんに西村さんが様々なきき方をしていき、とびラーはきき方が話し手にどのような影響を与えているのか観察します。
「それぞれのきき方が話し手に与える影響は?」
「『話の内容でなく、その人に関心をもつ』ってどういうこと?」
ところどころで西村さんから問いかけがあり、とびラーは自分の考えを書き留めていきます。
午前中の最後には3人組でそれぞれが書き留めたものを回し読みした後、考えたこと・感じたことをシェアします。
「書く→読み合う」のワンクッションにより、それぞれが自分の考え・感覚を整理する時間になりました。
午後は新たな3人組で「話し手」「きき手」「観察者」の3役をローテーションしながら、「話の内容だけに関心を向けるきき方」「内容だけでなく話し手に関心を向けるきき方」を試していきます。
最後に西村さんから「お互いに表現し合える場をつくるためには、きいてくれる人がいること、そしてきき方の質が大切」という心理的安全性のお話がありました。
今回の講座で普段の自身の「きき方」を振り返ったとびラーも多かったのではないでしょうか。
皆さんの「きく力」によってこれから様々なアート・コミュニケーションが生まれることでしょう。
簡単なようでとても難しい、「きく」とはどういうことなのか、とびラーの皆さんと一緒に考えていければと思います。
(とびらプロジェクト アシスタント 三原凜子)
2025.04.12
【第1回基礎講座 オリエンテーション】
日時|2025年4月12日(土)10時〜15時
場所|東京都美術館 講堂
春らしいお天気の中、58名の14期とびラーが東京都美術館の講堂に集まりました。とびらプロジェクト14年目のスタートです。
午前中は活動する上で必要な情報のガイダンスの後、東京都美術館を巡るツアーに出かけます。ツアーのガイドを務めるのは2年目、3年目のとびラーたちです。
最初は緊張した面持ちだった14期とびラーも、ツアーが終わる頃にはすっかり笑顔になっていました。
午後は12期、13期、14期のとびラー全員が集合し、今年度のとびらプロジェクトのキックオフが行われました。
スタッフの自己紹介の後、熊谷さんと小牟田さんから2つの問いかけがありました。
「美術館ってどんな場所?アートってなんだろう?」「とびらプロジェクトはどうありたい?」
それぞれが思いを巡らす時間になりました。
その後は3人組になって「自己紹介+どうしてここに?」のシェアタイムです。
にこやかに、時には真剣な顔でお互いの言葉に耳を傾ける姿が印象的でした。
今年度はどんなアート・コミュニケーションが生まれるのでしょうか?
12期、13期、14期のとびラーの皆さん、1年間どうぞよろしくお願いします!
(とびらプロジェクトアシスタント 三原凜子)
2025.03.17
執筆:11期とびラー 曽我千文
◇上野は日本初の都市公園
東京都美術館に行こうとJR上野駅公園口改札を出ると、そこはもう上野恩賜公園(以下:上野公園)です。東京都美術館は上野公園の中にあるのですが、たいていの場合、噴水広場を横目でみながら、駅と美術館の間を歩くだけで、公園全体の様子をみる機会は少ないのではないでしょうか。
上野公園は面積54ヘクタール。東京ドームの約11個分の広さがあり、2023年に開園150年を迎えた日本で一番古い都市公園のひとつです。上野のお山から、斜面を下った不忍池まで、実に多くの見どころにあふれ、歴史と自然を楽しむことができます。
私たち東京都美術館のアート・コミュニケータ「とびラー」も、せっかくいつも訪れている上野公園のことを、もっとよく知ってみようと「上野公園探検隊」を結成し、2022年度から2024年まで7回の探検を行いました。
◇上野公園のはじまり
上野公園があるところは江戸時代、東叡山寛永寺の境内地でした。それが明治維新後に官有地となり、明治6年の太政官布達(国の政治機関が府県に対し、公園という制度を発足させるので、「群集遊観ノ場所」などのふさわしい土地を選定してうかがい出るようにといったお達し)によって、日本で初めての公園に指定されました。
当初は社殿と霊廟、東照宮と桜を中心にした場所でしたが、その後、博物館や動物園、美術館などが建てられ、多くの文化施設が集まった世界でも希代の場所に発展しました。
江戸時代、家康、秀忠、家光の三代にわたる将軍に信頼された天海僧正によって開かれた、東叡山寛永寺には、京都や滋賀の名所に見立てた建物や景観が多く作られました。延暦寺にならって寛永年代から名を取った寛永寺。琵琶湖と竹生島を見立てた不忍池と弁天島。清水寺を見立てた清水観音堂。方広寺に見立てた大仏。上野の代名詞である花見の名所も、天海僧正が吉野山の桜を取り寄せて植えたのが始まりだそうです。
そんな上野の歴史や自然について、東京都美術館のアートスタディルームでスライドを使って、基本情報を共有した後に探検に出発しました。
2023年度には、探検のまとめとして、参加したとびラー全員で、発見したこと興味を持った思ったものを1人2つずつあげて、かるたを作りました。最初に五十音を任意に割り振られた文字を使って、詠み札の文を考えるのに苦労しましたが、楽しいこと、おもしろいものが大好きなとびラーたちの力作になりました。その「上野公園探検かるた」の一部をご覧にいれながら、探検の様子をご紹介します。
◇間違えられた公園の父
東京都美術館を出てすぐ、動物園正門の前には、ここでしか見られないパンダのポストがあります。2011年、東日本大震災の被害に悲しむ日本に明るい話題を提供してくれたリーリーとシンシンの公開を記念して建てられました。さて、ここでクイズです。「パンダのしっぽは黒でしょうか白でしょうか?」早速パンダポストで確認しました。当たった人も知らなかった人も嬉しそうです。
噴水広場のスタバの隣にある桜の木。これは上野公園で発見された新しい品種のサクラで、白花のしだれ桜です。公募で「ウエノシラユキシダレ」という名前が付けられました。ソメイヨシノより少し早い時期に白い雪が降るように咲くので、ぜひ、花の時期に見に来てください。
「真っ白な花が楽しみ。」
「貴重な木なのに、ヒョロヒョロで、枯れちゃうのが心配。」
などの声があがりました。枝から後継樹も育てられているそうです。
上野白雪しだれの少し北よりには、ボードワン博士の胸像があります。西洋医学を伝えるため来日したオランダ人の医師ボードワンは、明治政府から上野に東大医学部の前身である西洋医学所を建てる計画に意見を求められた際に、上野の貴重な緑地は公園にして残すべきだと進言したため、「上野公園の父」と言われています。ちなみにこの銅像は、上野公園開園100年に当たる1973年に、写真の間違いから、先に来日していた弟さんの像を建ててしまい、2006年になってから本人の像に替えられたエピソードがあります。
「そんなことってあるの?」
と一同大うけでしたが、オランダ領事を務めていた弟さんの像は、現在は神戸のポートアイランド北公園で海を見つめていると聞いて、ほっとした笑顔が見られました。
◇リニューアルした公園口広場
JR上野駅公園口を出た広場は、令和2年にリニューアルされました。それまで、駅の正面には、往来の激しい車道があって、信号待ちの乗降客で混雑していたのですが、当時を知るとびラーからは、
「本当にここは快適になった、前は危なかった。」
と声があがります。現在は、広場の南北に造られたロータリーで車はそれぞれ行き止まりになっており、駅を降りた来園者が、安全で快適に公園に入れるようになりました。上野駅も一緒に、改札口が北寄りに改修されて、改札から上野動物園の正門が、まっすぐ正面に見えるようになりました。
駅を降りると、左手には東京都美術館と同じく前川國男設計の東京文化会館、その向かいにはル・コルビュジェ設計の世界文化遺産に指定された国立西洋美術館があります。とびラーたちはひととき、西洋美術館で見た展覧会の話題に花を咲かせていました。
◇西郷さんは西郷さんに似ていない?
東京文化会館の裏手から桜広場に進むと、上野寛永寺の祖である天海僧正の毛髪塔があります。なんと108歳の長寿だったそうで、お墓は家康と一緒に日光東照宮にあるそうです。
隣にあるのは、上野戦争で幕府の降伏と江戸城無血開城に納得せず、上野戦争で明治新政府軍に敗れた悲劇の侍たち「彰義隊」のお墓です。
「上野戦争や彰義隊のことは今まで知らなかった」
「そんな悲しい歴史が上野にあったんですね」
と江戸時代終焉時の志士に思いを馳せて手を合わせました。
その先、上野台の先端には有名な西郷隆盛像があります。意外にも、知っていたけど見るのは初めてという人が多くいました。西郷像は「西郷さんに似ていない」という説があるのですが、西郷さんは写真嫌いだったため、有名な肖像画も弟と従弟の姿を参考にして描かれたものなので、そう言われているようです。西郷像の除幕式で、奥さんが『あれまあ!うちの人はこんなお人ではなかったのに!』と言ったのがことの起こりらしいのですが、奥さんは着流しの姿で兎狩りをしている西郷像の身なりが気に入らなかった、もっときちんとした人だったと言いたかったというのが本当のところのようです。とびラーはみな、この像が兎狩りの様子だということに驚いていました。確かに、のんびりと犬の散歩をしているように見えます。
上野のランドマーク、西郷さん像とその周辺を詠んだ探検かるた。彰義隊の墓や、花見のにぎわいも有名です。
上野に大仏があるのをご存じでしょうか。天海僧正が、京都や滋賀の風景を見立てて、江戸に再現したもののひとつが大仏です。この大仏は安政年間の地震や、関東大震災などで何度も頭部が落ち、現在では顔面部しかないため、「これ以上落ちない」ということで受験生に人気があります。「合格祈願」の文字が書かれた桜の花の形の絵馬がたくさんかけてあるのを見て、
「お顔だけになってしまってかわいそう。」
「ご利益ありそうだから受験生に教えてあげなくては。」
と知られざる名所にわいていました。
◇上野の洞窟・穴稲荷
外国からの観光客で大変にぎわう、朱塗りの鳥居が並ぶ花園稲荷神社の細い参道は幻想的で、下っていくとどこか違う世界に入っていきそうです。下りた右手に社殿があり、左手の斜面に探検隊の心が騒ぐ秘密の場所、洞窟がありました。鉄格子の扉を開けて中に入るとそこが、寛永寺を建てる際に、天海僧正が住処を失ったきつねを哀れんで掘らせた穴稲荷です。
「まさに秘密の場所ですね。扉の中に入れるとは知らなかった」
「東京の真ん中で、異次元の世界に入る気持ち」
と、どきどきしながら一人ずつ、暗く、ひんやりとした通路をそろそろと進み、薄明りに照らされた祠に、静かに手を合わせてきました。
このあたりの上野台の斜面林は、はるか昔に不忍池が海だった名残で、海岸沿いに育つシイやタブの木が多く見られる環境で、大きな木々が神社を包んでいます。
◇絶景かな清水の舞台
山の上から不忍池を見下ろすように、京都清水寺を見立てて作られたのが清水観音堂です。清水の舞台のすぐ下には、広重の「名所江戸百景」にも描かれた、太い枝をぐるりと輪の形に仕立てた「月見の松」があります。明治の初めに、台風の被害で松は失われてしまったのですが、江戸の風景を復活させようと、2012年に150年ぶりに植えられたものです。輪をのぞくと、下に不忍池の辨天堂がちょうど見え、みんな江戸時代にタイムスリップして、代わるがわるに写真を撮っていました。
桜の名所で有名な上野公園ですが、園内に50種類以上のサクラが植えられており、ソメイヨシノを中心に、早咲きと遅咲きのサクラの花を長い期間楽しめるようになっています。探検を行った2月にも、早咲きのカンザクラの花に、メジロが蜜を吸いにきていて、かわいいしぐさに癒されました。
花の蜜を吸うメジロは人気者。不忍池を見下ろす清水観音堂の月の松。辯天堂の龍の天井画に歴史を感じます
◇弁天島は発見がいっぱい
清水観音堂から階段を下ると不忍池の畔に出ます。不忍池の中央には、琵琶湖の竹生島を模して造られたという島があり、弁財天を祀る弁天堂があります。不忍池の弁天様は、八本の腕のそれぞれの手に煩悩を破壊する武器を持ち、頭上には「宇賀神」という人頭蛇身の神様を乗せています。宇賀神像はお堂の手前にもあり、今年は巳年ということもあり、関心が集まっていました。
お堂の天井には、児玉希望画伯による迫力のある龍の天井画が描かれ、とびラーが集まって拝見していると、誰からともなく対話型鑑賞が始まりそうでした。
弁天堂の周囲には、「ふぐ供養碑」、「魚塚」、「スッポン感謝之塔」「包丁塚」など、様々な供養塔や記念碑がたくさんあります。「めがねの碑」には徳川家康の愛用した眼鏡がかたどられていますし、「暦塚」は日時計になっています。
「徳川家康って眼鏡かけていたの?」
「小学校に日時計があったわ。正確に時間を示しているんですね。」
と、ひとつひとつをじっくり見てまわりながら、誰がいつ、何を思って建てたのか、碑文を読みながら楽しんでいました。
◇上野の自然とパワースポット
弁天島を西に渡ると、左手にスワンボートが浮かぶボート池、右手が上野動物園の区域の鵜池です。水辺には冬を日本で過ごすカモやカモメ、カワウなどがたくさんいて、望遠鏡を使ってバードウォッチングを楽しみました。
「人手が多いのに不忍池にはたくさん野鳥がいるんですね。」
「パンダに似ているかわいいキンクロハジロちゃんの大ファンになりました」
園内には随所に大木があり、丹精を込めて管理された季節の花壇や、所々では「いいにおい!」と花の香りに立ち止まり、普段気づかなかった上野の自然を満喫することができ、
「桜だけじゃないんですね。知らない植物などをもっと知りたいと思った」
「新しい品種の木や、植物の手入れの様子、花といっても知らないことが多かったです。」
という声も聞かれました。
望遠鏡をのぞいて初めて見る野鳥の美しさを堪能
東京都美術館に戻る途中、最後に噴水広場で上野のパワースポットを探しました。駅改札と動物園正門を結ぶ線と、東京国立博物館と桜通りを結ぶ線の交点、上野のおへそです。みんなで下を見ながらうろうろ。
「あった!これだ!」
石の舗装に小さく「+」が刻まれているのを見つけました。
「今後は都美への行き帰りには必ずや秘密のパワースポットでエネルギーchargeすること間違いありません。」
「+印のパワースポットで定期的にエネルギーチャージしたいと思います。」
と、みんなで代わるがわる+印の上に立ち、なんだか足取りも軽く、都美へと帰る探検隊でした。
◇探検を終えたとびラーたちの感想
東京都美術館に戻り探検をふりかえると、みんなそれぞれに印象に残った場所が違い、上野公園の見どころの豊かさを感じました。身近に思っていた上野公園も、みんなで探検することで知らない世界を見つけることができたようです。
「いつも通り過ぎるだけだった場所も、がぜんクッキリと見えてきました」
「上野の奥深さを改めて認識」
「行ったことのないエリア、本当に知らないことばかりで、上野をより知ることができた」
「たくさん発見をしたので、ますます上野公園が身近になりました。」
「今度1人でゆっくり上野公園を回ってみようかなと思います。」
「みなさんといっしょにおしゃべりしながらの探検、楽しい時間でした」
「季節ごとの上野を味わいながら歩いてみることの楽しさを実感」
「銅像から伝統や文化を知り、自然を感じることができた」
「時代毎のニーズなどを踏まえて公園が変化していく様子を知ることができて面白かった」
「みんなと見ると楽しい、ちょっとしたつぶやきから発見が広がりました」
3年間、とびラーと上野公園の探検を続けてきました。観察力が鋭く、楽しむことに長けた仲間と歩いていると、少し詳しいつもりになっていた公園に、こんなにも新しい疑問や発見が湧いてくるのかと、わくわくの連続でした。上野公園が奥深いのは、江戸時代から続く様々な人や自然のドラマが集積されているからだと思います。多くの文化施設が集まり、今日もたくさんの人でにぎわうのも、自然の摂理なのかもしれません。とびラーの活動も、この上野公園の歴史の一ページになっていけたらと思いました。
みなさんもぜひ新しい発見を見つけに、上野公園の探検にいらしてください。
執筆:とびラー11期 曽我 千文
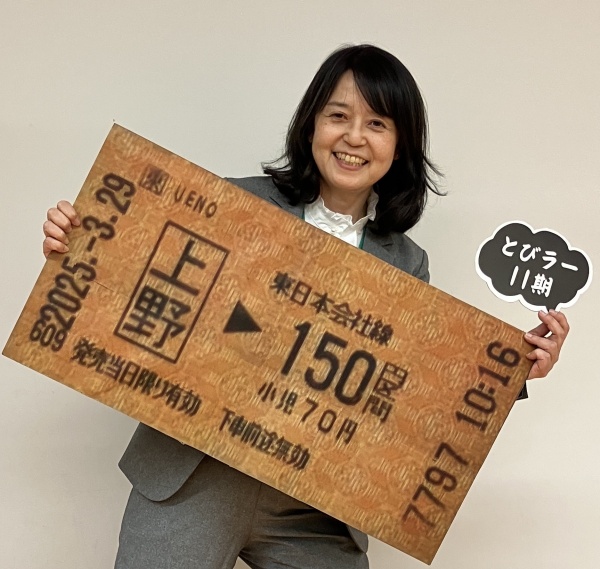 公園を造ったり管理したりする仕事をしています。公園の中にある大好きな東京都美術館でとびラーとして活動できた3年間は至福の時代でした。公園と美術館という、どちらも幸せの場所で、みんなに幸せになってもらうために歩き続けたいと思います。
公園を造ったり管理したりする仕事をしています。公園の中にある大好きな東京都美術館でとびラーとして活動できた3年間は至福の時代でした。公園と美術館という、どちらも幸せの場所で、みんなに幸せになってもらうために歩き続けたいと思います。
2025.03.01
東京都美術館では「とびラーによる建築ツアー」をおこなっており、「とびらプロジェクト」で活動するアート・コミュニケータ(とびラー)がガイドとなって、グループに分かれて対話しながら東京都美術館を散策します。今年度は6回開催しました。
この建築ツアーでは決まったコースがありません。とびラーたちは事前にお互い相談しながら、当日の館内の状況や混雑具合、天候などを想定して、コースや話す内容を考えています。しかし予期せぬことは起きるものです。コースを臨機応変に変更をしたり、参加者の興味に合わせて話題を転換したりできるように準備して、参加者をお迎えしています。
全6回の様子の一部をご紹介します。
第1回(5月12日開催)の様子
おひとりで参加する方や親子連れなど、様々な参加者がいるのも「とびラーによる建築ツアー」の楽しいところの1つです。最初にグループみんなで簡単にお話し、緊張がほぐれてからスタートします。
第2回(7月20日開催)の様子
暑さが本番になった7月。とびラーは、館内や木陰などを多く取り込むなど、暑さを考慮したツアー構成をそれぞれ考え、臨みました。
第3回(9月21日開催)の様子
どうやって東京都美術館の建物を味わってもらおうかと、とびラーは毎回考えています。実際に触ったり、じっくり眺めたりする時間を設けるグループもありました。
第4回(11月23日開催)の様子
「とびラーによる建築ツアー」は対話をしながらツアーを進めていきます。とびラーたちも参加者とのコミュニケーションを毎回楽しんでいます。
第5回(2025年1月25日開催)の様子
建物を紹介する上で、難しい言葉や聞き慣れない言葉を使う必要があるときがあります。とびラーたちはフリップや資料を用意して、参加者にわかりやすくお伝えする工夫をしています。
第6回(3月1日開催)の様子
今年度最後の建築ツアーでは、手話でお話しする方にも建築ツアーを体験してもらおうと、手話対応グループを1つ設けました。難聴のとびラーがガイドとなり、日本語対応手話を使って東京都美術館の魅力を紹介しました。ほかにも、ろう者や聞こえにくい方が参加される場合は、UDトーク(音声認識技術を使って会話やスピーチをリアルタイムに文字起こしするアプリ)を使ってガイドを実施しました。
「とびラーによる建築ツアー」では、ガイドによって紹介する見どころはさまざまです。そして、季節によって東京都美術館を囲む上野公園の四季折々の美しさも異なります。
参加するたびに新たな発見に出会える建築ツアーとなっていますので、ぜひみなさんのご参加をお待ちしております!
2025.02.08
第7回建築実践講座|「ふりかえり」
日時|2025年2月8日(土) 13:30〜16:30
会場|東京都美術館 ASR・スタジオ
この回は、建築実践講座のふりかえりや年間課題から「今後アート・コミュニケータとして建築を題材にして取り組みたいことは?」を考える最終回でした。
今年度の建築実践講座の年間課題は2つありました。
■ 年間課題① 「建築を、みる、楽しむ、伝える」
<目的>「誰かとみる」を楽しむ。
<内容>
東京都美術館以外の建築ツアーや建築関連のイベントに参加するなど、誰かと建築を楽しもう。
■ 年間課題②「東京都美術館を、誰かと、巡る」
<⽬的>「誰かを案内する」を楽しむ。
<内容>
家族や友達など⾝近な⼈に対して、東京都美術館を案内するツアーをしてみよう。館内の混雑状況、⾃分ひとりで対応できる⼈数(最⼤ 5 ⼈くらい)を考慮した上で、どんなツアーがよいか考えて実践してみましょう。
講座では、まず各々がおこなった年間課題①を思い出し「課題①をやってみてよかったこと」を考え、3つ選び、それらをグループでシェアしました。
たとえ同じツアーに参加していてもよかった観点はさまざまで、活発に語り合いました。その後はグループ内でよかったこと3つを選びました。
その後、第1回から6回までの講座内容をふりかえりました。
そして、課題①のよかったこと、課題②をやってみてきづいたこと、講座のふりかえりから「今後アート・コミュニケータとして建築を題材にして取り組みたいことは?」をそれぞれ考え、グループでシェアしました。
とびラーからのふりかえりを抜粋します。
ーーーーーーーーーー
・1年を通して、講演や実践を通して広くそして深く建築について考える機会をいただけたと感じました。特に建築ツアーはやってみてきづくことが沢山あり、これからもとびラー同士また他の施設の建築ツアーにも参加してブラッシュアップしていければと思います。また建築の人と人を繋げる役割にも気づくことができ、藝大部屋を始め、地域とのつながりをもちながら様々な人が交わる拠点にもなる可能性を感じました。
・建築だけではなく、どんなアートもそうですが、一人ではなく誰かと一緒に何かをみることは発見も多く、楽しいものです。建築を通して、そうした「とびラーとして当たり前」の感覚を多くの人に伝えるられるよう、今後も活動していきたいと思います。
・建築の使われ方はもちろんですが、その時代、その場所だからこそ生まれた建築について、土地との接続がどのように建築に表現されているのかを知り、考えることが、文化財や環境保全にもつながるのではないかと思うようになりました。
・専門家でなくても、その建築に対して自分がこれだけは伝えたいという思いがあれば、参加者は説明とともに建築を楽しむことができるのだなといろいろな建築ツアーに参加して強く感じました。
ーーーーーーーーーー
2024年度の建築実践講座の目標は「東京都美術館の建築の歴史や背景を理解し、自分の感覚を手掛かりに建築を味わう力を身につけ、美術館というパブリックな建築を介して人々をつなぐ場をデザインする」です。
今年度の建築実践講座は終わりますが、建築を味わうことに終わりはありません。それぞれの興味関心で建築を味わい、各々のペースで建築を楽しんでほしいなと思います。
そして、とびラーは3年の任期満了後それぞれのコミュニティに戻ります。この講座での学びや体験の種が、多様な人たちと「対話」を通して活動として芽吹き、広がっていくことを願っています。
(とびらプロジェクト コーディネータ 西見涼香)