
視覚伝達研究室に所属し、目に見えるものと見えないものをいかに視覚的に伝えるかを研究されているデザイン専攻・修士2年生の松田紗代子さん。学生時代から今回の修了制作、今まで取り組んできたものから今後の夢を訊いてきた。

半立体・パッケージデザインに元々興味があった松田さんは、しっかりと目的を持って制作している。しかし、学部生時代はデザインって何だろう?モノを作る意味って何だろう?と悩み模索する時期もあった。
「そもそも私にとってモノを作るという事はどういうことなんだろう?と考えながら学んでいくうちに、日本の折形に魅了されました。包んだり、それを人に送ったりする事にだんだんと興味を持ち始めたんです。中に包んでいるものを紙一枚で包む形によって抽象的に人に伝える事が出来る。日本独自の文化でかっこいいなと感じました。」
紙一枚から様々な形を折って作っていく研究。手の中で毎日触って新しい形を作ってゆくこのプロジェクトは折り紙とほとんど変わらないようであるが、毎日地道に続けるうち、一年かけておよそ四百の異なるパターンの折り方が出来上がった。
「卒業制作は、一日一包プロジェクトというものを制作しています。平面的な包む形から立体的で自然のような、有機的な曲線を出せないか?と模索していくうちに七十二候の暦の分け方を現代の暦に置き換えるという考えに辿り着いたんです。現代の暦に置き換え、手に取った人が実際に季節や自然を感じられるように紙一枚でのデザインを提案できないだろうかと考えました。一日一包プロジェクトでは、季節という概念を包むために紙の質感・大きさ・色彩を調整しながら七十二の包み方を模索しながら進めています。」
「まさか一枚の紙で出来ていないだろうと思うモノが一枚の紙だったときの“シンプル”さ“簡素さ”が日本らしいと感じるからです。完成した形から広げると一枚の紙になる、二次元と三次元を行ったり来たりしているのが面白くて。だから一枚の紙にこだわり、完成した時には見えない部分もデザインするようにこだわっています。」

出身は関西・兵庫県である松田さん。京都市立芸術大学で学部生として過ごしていた京都という町は、古くからある文化を守っていく一方で、どんどん新しいものと融合して変化していく町。古くからある伝統を、いかに形を変えながら残していくかを考えるきっかけになったのは、大学院一年生の時に参加した折形デザイン研究所・山口信博さんの講演だったという。折形の文化・歴史を知り、紙袋を作るワークショップで四角い一枚の紙を渡され、各々が自由に折る。“縦と横と斜めのグリットだけで無限に形に出来るんです”と言われた時、すごく日本的だなとインスパイアを受けたという。しかし、その根底にある、今の自分を作っているのは研究者である父であると語る。
「父は研究者で宇宙地球科学の分野を大学で教えていました。大気・海洋の起源・隕石などを研究し、世界中の化石や隕石、鉱物などを収集している父を幼少の頃はずっと側で見ていました。私のお父さんはインディ・ジョーンズなんじゃないかって(笑)。そんな父をずっと見てきたせいか、“古いものに宿っているロマン”に対する情景はありますね。自分が作品を作る上でもそのモノにまつわる歴史や文化などのバックグラウンドを含めた上でアプローチの仕方を決めて、アウトプットしていきたいと考えるのも研究者気質の父の影響だと思います。ただ作ってキレイっていうよりは、その裏側まで見つめて、そこにきちんと知識を持つ事もデザインをしていく上で専門性というか、プロとして必要なことなのかな、と思います。」
一日一包プロジェクトの他に、様々なものに積極的に活動してきている。形をただ作るデザインより、過程から遺していく事を考える。古くからある伝統・文化をいかに現代風に融合させ、形を変えて後世に遺していくか。デザインにおいてコンセプトや構造的な面から、社会で上手く働くデザインを考える一方で、アウトプットとしてのデザインの両立を考えながら制作していた。
「電子回路を銀のインクで刷れる技術を開発した会社の方と子供向けのワークショップをした時は、和柄自体が回路になるように設計し直して、光りながら回る風車をデザインしました。ずらりと並んだ光の風車が夜店の懐かしいような雰囲気を作り出して、子供も大人も楽しんで頂けたと思います。また、指先の凹みや圧を繊細に感知できるセンサーを開発した方の、それを使って新しいものを開発するというコンペでは、伝統工芸をそのセンサーによって後世に遺していく事は出来ないだろうか、という仕組みの提案をしました。その職人さんがいなくなったら失われてしまうであろう指先の動きを、センサーを使ってデータ化したものをパッケージングして集めていくんです。伝統技術がデータとして遺っていれば、未来に再現できる可能性もあります。そういったアーカイブ活動にも活かせると感じました。」
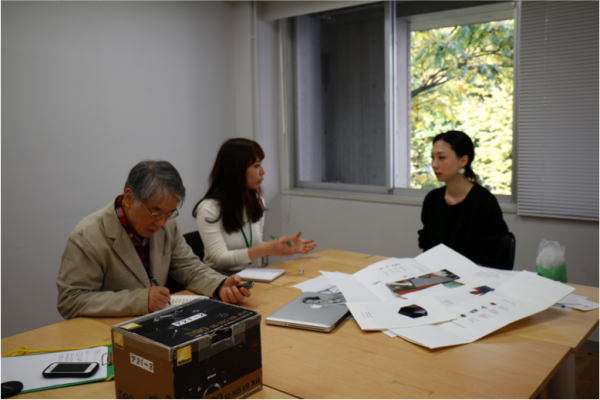
視覚伝達研究室に所属している紗代子さんは、視覚障害者の方や外国人の方など日本独自の文化を取り入れたデザインを手に取る際に、何かしらの障害がある方々も含めてデザインを発信していきたいと考えている。そういったデザインを志したきっかけは、本の装丁やポスター、パッケージなど至る所にあるデザインの中で、ちょっとでも良いデザインに巡り会うと心が“ポッ”と豊かになる瞬間を自分でも少しでも多くの人に発信していきたいという強い願いからである。
「外国人向けの日本酒のギフトパッケージをデザインした時は、日本酒の濁りや色をみて楽しむ利きちょこに注目しました。多くの外国人は大吟醸と書かれていても分からないし、利きちょこも持っていません。そこで伝統的な蛇の目文様を酒質に合わせて展開し、瓶の奥に藍色と白のコントラストでデザインしました。そうする事で利きちょこがなくても楽しめますし、視覚的にも味がイメージできます。また、視覚障害の方向けに服の色や模様を凹凸のあるタグで分かるようなデザインもしました。装飾的であって機能的なデザインから、コンテンツの魅力や自分のアイデンティティーを視覚的に感じてもらえたらな、と思っています。」
「目に見えるものと見えないものをいかに視覚的に伝えるかは永遠のテーマですね。今の時代、パソコンで何でも出来ます。でも、インターネット上ではぺたっとした情報で機械的で冷たく、リアルに感じる事が出来ないと思います。一方で、印刷物になるとざらざらしていたりつるつるしていたり、ここにあるものでしか通じ得ない伝達があると思っています。包装紙などは持って帰って家で使う時間までかもしれないけれど、私は三次元としての魅力を区別化して、こだわっていきたいです。毎日デザインの事を考えて、良いデザインに触れて目を鍛える。毎日手を動かして、手を鍛える。そういう風に努力しているからいざっていう時にプロとして良いモノが出せるものなのかな。これからも考え続けているからこそ表現できるデザインを大事にしていきたいです。」
執筆:赤城命帥(アート・コミュニケータ「とびラー」)
2016.01.06