
2020.07.25
第2回鑑賞実践講座
「ファシリテーション基礎(1)」
日時|(A日程)2020年6月29日(月)9:30~16:30
______(B日程)2020年7月25日(土)9:30~16:30
場所|zoom(オンライン)
講師|三ツ木紀英(NPO法人 芸術資源開発機構/ARDA)
◎概要
・全とびラーに開かれた講座。朝から夕方まで1日中×2日間で「ファシリテーション基礎⑴⑵」をとびラーたちが“合宿”的に学ぶ。
・Visual Thinking Strategiesのファシリテーションの基礎を学ぶ
・講師:三ツ木紀英(NPO法人 芸術資源開発機構/ARDA)2012年のとびらプロジェクトスタート当時から鑑賞実践講座を担当。今年は初のオンラインでの講座実施となった。
1日目の「ファシリテーション基礎⑴」では、主に以下の4つの内容を軸に講座が進行されました。
■講師:三ツ木紀英さんのこれまでの活動について(自己紹介として)
■鑑賞の場の観察「ファシリテーションのポイントは何か」
■観察したことをグループでディスカッション、参加している全員での共有。
■ファシリテーションの実践とふりかえり
2020.06.22
第1回鑑賞実践講座
「ミュージアム体験とは?」
日時|2020年6月22日(月)13:30~16:30
場所|zoom(オンライン)
講師|稲庭彩和子(東京都美術館)
鑑賞実践講座では「作品やモノを介して人をつなぐ場をデザインする」ことを目的とし、1年間で計7回の講義を行います。とびラーが目指したいことは次の3つです。今年は特に、これらをオンラインの講座で行っていく、初めての挑戦となります。
第1回の講師は、稲庭彩和子さんです。これからとびラーが鑑賞の場づくりを学んでいくにあたり、まずはじめに「ミュージアムでの体験とは何か」、「わかること・鑑賞することとは何か」について考えを深めていきました。
2020.01.20
鑑賞実践講座・第7回
「1年間のふりかえり」
日時|2020年1月20日(月)13:30~16:30
場所|東京都美術館アートスタディルーム
講師|稲庭彩和子さん(東京都美術館学芸員)、三ツ木紀英さん(NPO法人 芸術資源開発機構(ARDA))
本年度の鑑賞実践講座で、とびラーは体験・観察・考察・実践を通して、Visual Thinking Strategiesのファシリテーションを理解してきました。またVisual Thinking Strategiesについて学ぶことで、作品を鑑賞すること、またアート・コミュニケータとしてのあり方への理解を深めてきました。
<Visual Thinking Strategiesファシリテータの“編集的”はたらき>
ファシリテータは、複数の視点から語られる鑑賞者の意見を中立的な立場で「編集」する作業をしています。編集をする際は、鑑賞者の言葉を言い換えたり、それぞれの発言を繋げるなどの整理をしたり、まだ言葉になっていない思考の部分を言語化しながら、複数の人の眼で一緒に作品をみる状態を作っていきます。
この3つの質問と編集的なはたらきが現場でどのように使われているか、実際のVisual Thinking Strategiesの活動の動画を見ながら紐解いていきました。より精緻に「言葉」に注目するため、動画の中の対話を文字に起こしたペーパーがとびラーに配布され、そのペーパーに編集された箇所を書き込んでいきます。
Q:例えば「木がある」「空がある」という発言など、鑑賞者が見つけたものが一目瞭然な場合も作品の中に根拠を聞いたり、発言を掘り下げることはできるのでしょうか。
A:さっきのワークがヒントですが、「木がある」の発言は、文脈に意味があるのでそれを言語化します。どんな発言も鑑賞者の何らかの発見が含まれています。対話の流れをよく聞いて、それを言語化してあげる。言語化していくうちに新しい発見が生まれて「作品のどこから?」と作品の中に根拠を聞けるものが出てきたりします。映像の中でも「椅子がある」と発言した子に対して、そこまでの文脈の中でその子の気づきを眺め、「形に注目したんだね」とすくいあげて他の子にも共有しています。
Q:映像では、子どもの「カビ」という発言とそこまでの話の中で出てきた「色」をひっかけて、色の問題に関連性を見出している。ライブの現場でここまで瞬間的にできるものでしょうか?
A:論理的ではなく、ビジュアルで考えています。論理的に覚えていたり思考しているわけではなく、作品を感じながら対話が進みます。みんなで感じていることをファシリテータ自身も感じている。何に着目して「カビ」という言葉になったのか、それをつないでいっています。
Q:とびラボメンバーとVTSをしたとき、Q1(作品に対する鑑賞者の解釈を促す開かれた質問)の使い方について考えました。「何が起こっていますか?」を使わず「何が描かれていますか?」と問いかけた結果、鑑賞が深まらなかった。
A:「何が見えますか?」は解釈を促すのではなく事実を見つけることを促す質問だからだと思います。ある程度時間があるなら、何が描かれているかを発言し始めたときに「見ている」という状況ができるので、その状態を作るには意味のある質問ではあると思います。かたち、描かれているもの、で発言がとどまっているなら、目に入ってきたものを鑑賞者がどんな風に感じるか、鑑賞者の解釈を促す。出てこない、と焦らず、解釈の道筋を立ててあげると良いと思います。
Q:初回の講座で「テキストではなくビジュアルを通して考える視覚的思考法」と、Visual Thinking Strategiesについて説明がありました。そのポイントについて、より詳しく知りたいです。
A:Visual Thinking Strategiesは、日本では「対話による鑑賞」「対話型鑑賞」と翻訳されているので、「対話」「言語」に意識が向かいがちです。Visualでもって考えるとは、Visualが含んでいる多くの細かな情報、Textにすると表現されずに落ちていってしまう情報を使って考えを深めていく思考法です。例えば、人の表情など、「寂しい」「切ない」「悲しい」と人によって様々な言葉で表現されるものでも、そこに実際のVisualがあれば、それを一緒にみながら理解を深めていけます。いわゆるLogical Thinking(論理的思考法)とは逆に位置する思考で、ロジカルだけではたどり着けない多様性を含んで思考できる方法ではないかと思っています。
(東京藝術大学美術学部 特任助手 越川さくら)
2019.11.11
鑑賞実践講座・第6回
「ファシリテーション実践〜スペシャル・マンデーに向けて〜」
日時|2019年11月11日(月)13:00~17:00
場所|東京都美術館アートスタディルーム
講師|三ツ木紀英さん(NPO法人 芸術資源開発機構(ARDA))
次に、Visual Thinking Strategiesの実践を行います。
2019.10.21
鑑賞実践講座・第5回
「ファシリテーション事前準備」
日時|2019年10月21日(月)13:00~17:00
場所|東京都美術館アートスタディルーム
講師|三ツ木紀英さん(NPO法人 芸術資源開発機構(ARDA))
Visual Thinking Strategiesのファシリテータは、事前の準備にたくさんの時間をかけます。鑑賞者について知り、鑑賞者に合わせて作品を選出します。当日の現場が始まる前からファシリテーションは始まっています。今回はその「事前」のファシリテーション準備についてみなさんで考えていきます。
<作品選びのポイント>
まず、講師の三ツ木さんから、作品の選び方についてレクチャーがありました。
「認知心理学者のアビゲイル・ハウゼンがまとめた『美的発達段階』の考え方では、アート作品の鑑賞などを通した美的体験における発達の段階が、5段階あることが示されています。この美的発達段階の考え方を元に、第一段階・第二段階の鑑賞者(美術館に来館するほとんどの人がここに含まれる)が鑑賞を深めやすい作品の選定について考えます」
「まず物語性を見出しやすいか、という視点が作品を選ぶ時に有効です。特に子どもなど、第一段階の鑑賞者は自分の知っていることに基づいて見たものを理解しようとしたり、作品の中に物語を見出そうとするという傾向があるためです。それだけではなく、多義性(1つの答えではなく、様々な見方をできる)を感じられる作品であるかどうか、興味を刺激したり、理解可能なきっかけがあるかという視点も大切です」
鑑賞者の段階に合わせた作品の内容から始まり、実際の展示室で鑑賞しやすい位置にある作品か、また1作品目と2作品目のシークエンス(連続性)などにも気を配って作品を選定することが重要とのお話もありました。作品選びのポイントを知ったところで、グループになって実際に作品を2作品選んでみました。
また、選んだ作品について全体で発表し、気づいたことを共有しました。
<事前準備:「ひとりVTS」>
「事前準備では、まずファシリテータ自身が作品をよく見て、作品の魅力を掴んでおくことが大事」と三ツ木さんは言います。
「ひとりVTS」と呼ばれる準備では、まず作品をよく見て、様々な要素を付箋に書き出していきます。なるべく多くの視点で作品を見ることが重要です。次に書き出した意見が主観的解釈なのか、客観的事実なのかで分類し、主観的解釈の意見に対しては、「作品のどこからそう思ったか」を自分自身につっこんで質問して作品の中に根拠を求めます。
その後、それぞれの意見をグループ化し、グルーブに「小見出し」をつけたり、グループごとの関係性を見たりして全体を把握します。
<Visual Thinking Strategies実践>
最後はいつもの通り、実践を行いました。
次回からは、ファシリテーションの事前準備で「ひとりVTS」を行い、作品について、より深くその魅力に迫っていくVisual Thinking Strategiesをしていければと思います。
(東京藝術大学美術学部 特任助手 越川さくら)
2019.08.26
鑑賞実践講座・第4回
「展示室で学ぶ場づくり〜スペシャル・マンデーに向けて〜」
日時|2019年8月26日(月)13:00~17:00
場所|東京都美術館アートスタディルーム・「伊庭靖子展 まなざしのあわい」展示室(ギャラリーA・B・C)
講師|三ツ木紀英さん(NPO法人 芸術資源開発機構(ARDA))、鈴木智香子さん(Museum Start あいうえの)
9月に、とびラーたちは実際に「スペシャル・マンデー」で学校来館の子どもたちと鑑賞を行います。今回は、Museum Start あいうえのの担当者からスペシャル・マンデーのプログラムについてレクチャーを聞いた後、展示室で実践を行います。
<スペシャル・マンデーとは>
「スペシャル・マンデー」は、とびらプロジェクトと連動する「Museum Start あいうえの」の学校来館プログラムです。このプログラムで、とびラーはVisual Thinking Strategiesのファシリテータとして子どもたちの鑑賞に伴走します。
担当者の鈴木智香子さんから、来館前〜当日〜事後のプログラムの流れや、とびラーが親でも先生でもない「斜め上の関係」の大人としてこのプログラムに参加する意義、子どもたちの鑑賞に伴走する際に大切な心得、また当日のプログラムの流れなどについてお話をいただきました。
<スペシャル・マンデー体験>
スペシャル・マンデーの一連の流れを、まずはとびラー自身が体験しました。
はじめに、展覧会のアートカードでお気に入りの作品を選びます。自分が実際にみたい作品を決めることで、展示室でのモチベーションを高めます。
次に、展示室に移動し、会場をぐるっとみて回ります。美術館の展示室がどんな場所になっているか、会場全体を把握することで、安心して作品を鑑賞する気持ちを作ります。
展示室の実際の作品をVisual Thinking Strategiesで鑑賞します。
実際の作品の前で行うと、作品保全のために気をつけることや、近づいたり離れたりした時の見え方の違い、グループの立ち位置など、新たな課題が見えてきます。
グループで鑑賞した後は、ひとりで鑑賞する時間です。Visual Thinking Strategiesでグループ鑑賞を行い、鑑賞の感覚を養った子どもたちが、ひとりの時間にどのように作品と対話をしているのかに思いを馳せました。
体験の後は、再びアートスタディルームに集合し、これまでの体験を振り返ります。
<作品研究>
Visual Thinking Strategiesは、知識によらず、鑑賞者自身が自分の目で見たことからスタートし、複数の人と意見を交換しながら作品の鑑賞を深めて行く手法です。Visual Thinking Strategiesファシリテータは、どのような事前の準備を行なっているのでしょうか。詳しくは、次回、第5回の講座で詳しく扱いますが、今回はグループワークを通して事前準備の基礎的なやり方を体験しました。
<Visual Thinking Strategiesファシリテーション練習>
講座の最後は、いつも通り、実践の時間です。今回はいよいよ、実際の展示室でこれまでの気づきを元に実践を行いました。
展示室を歩いて観察と実践と振り返りを行い、頭も体も心もフル回転の4時間を終えました。力を使い切った!疲れた!と、とびラーの声が聞こえていました。
講座は折り返しを迎え、9月のスペシャル・マンデー実践を経て、後半戦へと突入します。とびラーのみなさん、引き続き、よろしくお願いします!
(東京藝術大学美術学部 特任助手 越川さくら)
2019.08.11
鑑賞実践講座・第3回
「ファシリテーション基礎⑵」
日時|2019年8月5日(月)、8/11(日)9:30~16:30
場所|東京都美術館アートスタディルーム
講師|三ツ木紀英さん(NPO法人 芸術資源開発機構(ARDA))
ファシリテーションの基礎を学ぶ夏期集中講義の2日目です。2日間の日程で、鑑賞の場を作るファシリテーションの基礎を学びます。この集中講義は、鑑賞実践講座を選択していないとびラーにも公開されています。月曜日に行われるA日程(7/29、8/5)と、土日に行われるB日程(8/10、8/11)合わせて100名以上のとびラーが参加しました。
鑑賞に適した安心・安全・集中の場を作り出すために、「ファシリテータがどんな振る舞いをしているか?」、映像視聴や体験を通して、観察→思考→実践→ふりかえりのサイクルを繰り返しながら講義が進められました。
<キーワードの振り返り>
前回、とびラー自身が発見したVisual Thinking Strategiesのキーワードを元に、自分のノートにまとめを行うところから第3回目がスタートしました。そのキーワードの何が大切なのか、ノートに記入することで言語化していきました。
<映像分析>
子どもたちがVisual Thinking Strategiesのプログラムで鑑賞を行なっている場面を映像で視聴し、実際の子どもたちの反応や展示室の様子などを元に、より多くの情報を観察、分析していきました。作品を鑑賞する前に、鑑賞者(子どもたち)との関係性をどのように作るのか、など、作品の前やそれ以外のファシリテーションの実際の様子から、学校来館のプログラムのイメージが深まりました。
<グループ鑑賞実践>
今回も、最後は実践の時間です。ここまでの気づきを元に、前回よりも大きな作品画像を使ってより実践に近いVisual Thinking Strategiesを行いました。前回のミニサイズの鑑賞実践に比べ、場全体により目配りを行うことが求められます。全員が作品をじっくり見れているか、参加できていない鑑賞者はいないか、など心配りをすることで、場が整えられ、鑑賞が深まっていきます。
三ツ木さんからは、
「学校来館のプログラムでは、1人残らず全員に美術館を好きになってほしい。そのために何ができるか、ぜひ考えてみてください」
とお話があり、とびラーたちが頷いていました。
集中講義の二日間を終え、とびラーたちはファシリテーションの基本のキを学びました。次回はいよいよ、展示室での鑑賞の場づくりについて体験を通して学んでいきます。
(東京藝術大学美術学部 特任助手 越川さくら)
2019.08.10
鑑賞実践講座・第2回
「ファシリテーション基礎⑴」
日時|2019年7月29日(月)、8/10(土)9:30~16:30
場所|東京都美術館アートスタディルーム
講師|三ツ木紀英さん(NPO法人 芸術資源開発機構(ARDA))
ファシリテーションの基礎を学ぶ夏期集中講義の1日目です。2日間の日程で、鑑賞の場を作るファシリテーションの基礎を学びます。この集中講義は、鑑賞実践講座を選択していないとびラーにも公開されています。月曜日に行われるA日程(7/29、8/5)と、土日に行われるB日程(8/10、8/11)合わせて100名以上のとびラーが参加しました。
鑑賞に適した安心・安全・集中の場を作り出すために、「ファシリテータがどんな振る舞いをしているか?」、映像視聴や体験を通して、観察→思考→実践→ふりかえりのサイクルを繰り返しながら講義が進められました。
<アートカード体験>
NPO法人ARDAの鑑賞ファシリテータによるアートカード体験(様々な作品が印刷されたアートカードをゲーム感覚で鑑賞する)を行いました。ファシリテータの振る舞いや鑑賞者の状態に注目してアートカード体験を観察します。気づいたことを書き出し、その気づきを元にグループディスカッションへ。その後全体でも共有しました。
ファシリテータが行なっている「言語」的な働きかけや、「非言語」的な振る舞いまで、観察によってとびラー自身がVisual Thinking Strategiesファシリテーションのキーポイントや鑑賞者の変化を発見していきました。
<Visual Thinking Strategies体験>
1つの作品を複数の人でじっくりと鑑賞するVisual Thinking Strategiesを三ツ木さんのファシリテーションで体験し、その様子を観察しました。ここでも観察した内容をグループ→全体で共有し、ファシリテータの振る舞いが鑑賞の場や鑑賞の質にどのように影響していたかを話し合いました。
<ミニファシリテーション実践>
ここまでに発見したファシリテーションのキーポイントを、発見ホヤホヤの状態でまずは実践してみました。見るとやるとでは大違い。実際にファシリテータとして場を作ろうとすると、緊張感が出てしまったり、なかなかすぐに「できた!」とはいきません。それでも鑑賞の場を作り出す楽しさを味わい、様々な意見を聞くことを楽しみながら、まずは多くのとびラーが最初の一歩を踏み出しました。
講師の三ツ木さんからは、
「Visual Thinking Strategiesをしようとすることで、ファシリテーションの基本である、『参加者全員をみる、きく、感じる』ということを意識するようになります。そして、できるようになるには、たくさんの実践をすることです!」
と、何よりも実践あるのみ!という言葉がとびラーに送られました。
Visual Thinking Strategiesを学ぶことが、とびラーの基本として大事にされる、きく力、作品に親しむこと、安全安心な対話のための場を作り出すことに繋がっていくことと思います。
(東京藝術大学美術学部 特任助手 越川さくら)
2019.07.08
鑑賞実践講座・第1回
「アートを誰かと一緒にみる力の幅を広げ、アートや文化の共有の仕方を多面的に考える」
日時|2019年7月8日(月)13:30~16:30
場所|東京都美術館アートスタディルーム
講師|稲庭彩和子さん(東京都美術館学芸員 アート・コミュニケーション係長)
冒頭、稲庭さんから、これからの美術館の役割が語られました。
「多様な文化や価値観が肯定的に扱われ、それを鑑賞する(Appreciate/正しく受け取る)ことができる場としての美術館。そこでは鑑賞するための積極的なコミュニケーションを通して共同的に学び合う場がある。そういう未来を目指していきたいと思っています」
そして、今年の鑑賞実践講座の目標を発表します。
⑴見る力をつける
視覚を使って物事を捉えることの幅を広げるには、ある程度のエクササイズが必要になります。佐伯胖さんという認知心理学者のテキストを紹介し、作品を鑑賞する見方に「Appreciation」と「Evaluation」という方法があると、稲庭さんは説明します。
「Appreciationは主観を大切に見ていく見方、Evaluationは批評的に分析して見ていく見方です。美術館のキャプションはEvaluation的な見方で書かれていることが多いです。どちらもバランスをとって見ていくことで鑑賞が深まっていきます」
読書をする時、読み終わって「面白かった!」と感じるだけでなく、じっくりと分析的に“精読”する方法があるように、作品を見る時にも、深く味わったり、読み解くように見ていくことができます。その方法を一度学ぶと、自分でも作品を深く楽しんでいくことができるようになります。
では、どのように作品を“精読”することが可能なのでしょうか。まずは、作品がどのような“要素”から成り立っているのか、複数の人の目で見て考えるワークを行いました。
<この作品にどんな“要素”があるか、考えてみてください>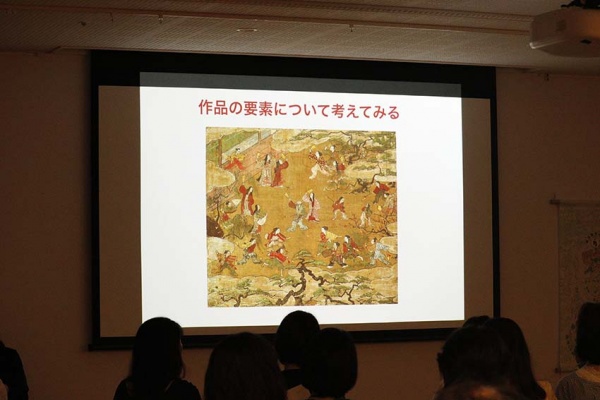
ー どんな“要素”があるか…?
聞きなれない質問を問いかけられ、一斉にとびラーの頭の上に「?」が浮かびます。
作品の上に視線が注がれ、次第にみんなの口が開き始めました。
「全体が雲に囲まれているなと思いました」
稲庭さんが、意見を受け取ります。
「はい。雲に囲まれている。ここに描かれている“状況設定”についての意見ですね」
その意見を皮切りに、作品の中で“起こっていること”や、“どんな物に何で描かれた作品か”など、様々な視点・要素が語られました。その意見を稲庭さんが【それは作品のどの要素か】という視点で分類していきます。
<作品の要素>
「たくさんの人が遊んでいてぶつかりそう」→【状況設定】
「羽子板大会」→【テーマ】
「全員着物を着ている」→【描かれている人物の服装】
「何でできているか、描かれているか」→【画材】
「おそらく日本」→【国】
「色あせている感じ。これは屏風?掛け軸?」→【支持体】
「俯瞰した視点で描かれている」【作品が描かれた視点・画角】
「赤いモチーフが多い」→【色彩】
「作者が自分が描きたいと思ったのか、それとも依頼されたものか」→【作品が生み出された背景】
作品の中には、描かれたものやストーリー、画材や構図、作者の意図などの“要素”が幾重にも重層的に含み込まれています。どんな要素に気づくかは人それぞれ違い、その視点のバリエーションが、複数の人で作品を見ることの面白さにもつながります。また、他の人と鑑賞をすることで自分以外の人の視点にきづき、主観と客観を分けて見ていくことができるようになります。
⑵場づくりの基本を知る
目標の2つ目に紹介された「鑑賞」のための場づくりについて、
「安心と集中が大切です」
と稲庭さんは言います。
「作品の中に入っていくということは、気持ちが「開いている」状態でないとできないことです。自分を守りたいという心理状態、「閉じている」状態では、「appreciationの波に乗る」ことができません」
この講座の中でとびラーは、ともに鑑賞する人々が気持ちを開いて集中している状態になれる鑑賞の場づくりについて学びます。
⑶アート・コミュニケータのあり方への理解を深める
この講座では、VTS(Visual Thinking Strategies)の考え方も学びながら「見る力」を身につけることを目指します。どんな人と、どんな場所で共に作品を見るのか。それぞれの鑑賞の「場」を作っていくことも重要です。この二つを学ぶことを通して、「とびらプロジェクト」の考え方やミッション、「こんな方向性でみんなでやっていこう」という哲学やあり方を理解していくことを目指します。
<実際の映像を見て考える>
講座の後半では、子どもたちが作品を鑑賞することを通して、コミュニケーションをしたり、自分の考えを創造していく、実際に行われたプログラムの映像を観て意見交換を行いました。
とびラーからは、
「一緒に鑑賞していく人同士の関係性が大事になってきそう」
「鑑賞とは何か。経験によって精度が上がるように思う」
「今までは作品を“消費”していた。実物を目にすることで満足していた。AppreciationもEvaluationも現時点で自分には足りていないかも」
「子どもたちが、作品に出会いつつも“作品に出会う自分自身”にもう一度出会い直しているということが動画を通してわかった」
などの感想が発表され、稲庭さんとのセッションが行われました。
「作品を鑑賞すること」について考えることで、アート・コミュニケータとしてのあり方を学ぶ1年間の講座。講座の中、そして実践の場を通してとびラーもスタッフも一緒に学んでいければと思います。
(東京藝術大学美術学部 特任助手 越川さくら)
2018.10.29
この日は11月に実践する「スペシャル・マンデー・コース」に向けての練習会!
とびラーがファシリテーションをたくさん実践する機会としました。
講座の流れ:
1)全員で作品鑑賞:VTSのポイントを思い出そう
2)グループごとに作品鑑賞:4チームに分かれてコーチング
コーチ役は、講師の三ツ木紀英さんに加えて、ARDAより近藤乃梨子さんと桑原さんが来てくださり、そして東京都美術館 学芸員の河野さんの4名が各グループに入って行いました。
3)スペシャル・マンデー・コースに向けて
<近藤乃梨子さんのファシリテーションによる作品鑑賞>
近藤さんは、実は2期とびラー。
とびらプロジェクトで鑑賞実践講座を選択し、鑑賞の場づくりを突きつめ、ARDAとして活動したりこの夏には「おべんとう展」のファシリテーター運営などを行ったりするまでに、活動の幅を広げている方です!
<そして4グループに分かれてのファシリテーション実践>
・各ファシリテーターは<対話8分+ふりかえり15分+移動2分=25分>という流れでやりました。
・ふりかえりは、以下の4ステップで行いました!
ーーーーーー
①ファシリテーターの意気込み(今回気をつけたポイント、やってみての感想など)
②ファシリテーションでよかったところを言う
③ファシリテーションでイマイチだったところを言う
④ファシリテーターの次なる意気込み(今後の課題など)
ーーーーーー