
心地よい冬晴れの 12月18日、東京藝術大学中央棟の美術教育研究室に安島茜さんを訪ねた。研究室には、制作中の 4 枚の作品が並んでいた。
まず目に飛び込んできたのは、綺麗な白と伸びやかで勢いのある線。そして、そこに置かれた鮮やかな色彩。それは、今までに見たことのないような光や空気、モチーフの描き方だった。絵に惹きつけられながら、インタビューを始めた。
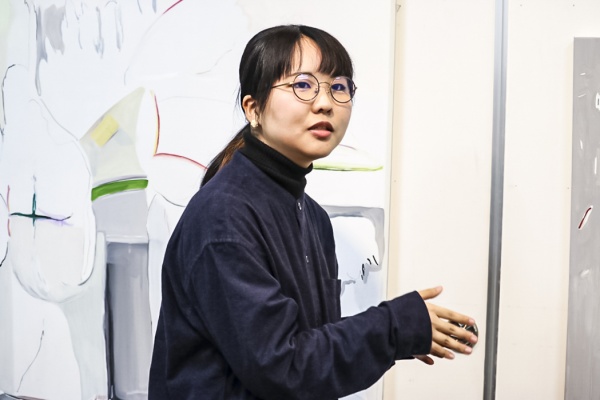

■制作は、絵と私のオセロゲーム
― どのように制作をされているのですか?
「まず、写真を撮って、それを見ながら何枚も下絵を描きます。写真に写っている全てのものを描くのではなく、いい形や色を厳選して絵にします。そこから大きくするのですけど、実際大きくしてみると、その日の気分とか、大きくしてみたら違う面白いところが出て来たとか、あまり計画通りに行ったことがないです。でもそういうのが楽しいです。」
描きたいものを選んで描くというのは、絵を描く時には珍しくないことだが、安島さんの作品は、その選び方に独自性がある。どう厳選するかは、どこまで削ぎ落としたら本質に迫れるかという、引き算の美学のようでもある。それゆえ真白いキャンバスの上の、抽出された色や線の放つ輝きが際立っている。
「今日はこう描くぞと決めてもそういかない。絵と自分が常にやりとりをしていて、自分が全部操っているわけではなくて、半分絵に振り回されていたりもしているのが、結構面白かったりするなと思っています。ここを描いてみたら、それで絵が変わってくるので、『おっ、こう来たか』とか、絵と私でオセロゲームをやっているような感じです。」
安島さんのお話を聞いていると、作品と真剣に向き合い、抜き差しならぬ対戦をしている彼女の姿が目に浮かぶようである。作家が作品を全部操っているのではなく、作品自体が主張する生命あるものとなって、作家と対等な関係になっているという捉え方が面白い。

― このように写真を見て厳選して描くスタイルになったのは、いつ頃からですか?
「大学に入って、田舎から都会に出てきてからです。小学生の頃は、虫眼鏡で植物を見て写生をしていました。植物は枯れるので、写真を見て描くということは、子どもの頃からもあったのですが、見たものから何を抽出するかが少しずつ変わってきています。見たものを見たままにリアルに描くということよりも、その時の感情や内面的なものを描きたいと思うようになり、具象度よりやや抽象度の方が上がってきたのが、4年前くらいです。」

■絵は「なんでも受け止めてくれる大きな器みたいなもの」
― 修了展の作品についてお話を聞かせてください。
「作品のタイトルは、《母親を呼ぶように》です。“母親”というのは、私の母親とか誰かの母親とか特定の母親ではなくて、もっと大きな括りとして、私の母親にとっても母親だし、私にとっても母親だし、という『大きな存在』『みんなを包む大きな優しさみたいなもの』をイメージしています。
絵を描いているときの楽しさとか幸せな気分というのは、そういう『大きな優しさ』『なんでも受け止めてくれる大きな器みたいなもの』が目の前にあって、私がどんな状況にあっても、どんなに今日はダメだとか、ちょっと一回人間しんどい!みたいなそういう辛い時であっても、絵という大きな器が『なんでもどうぞ!』と寛容に受け止めてくれていて、描いていてすごく救われているなあと思っているのです。絵ってそういうものではないかなと思い始めてから描き始めたシリーズです。
モチーフは、実家に生けてあった花。母親が仕送りの中に入れてくれたものをアパートで生けた花。散歩中に見つけたもの。家から持ってきた花など。実際に在るものを自分で撮影して描いています。」
美しい自然に囲まれて育った安島さんは、生き物や植物に心惹かれるという。小さい頃から見ていたものへの愛しさや親しみが、作品の底流に流れている。
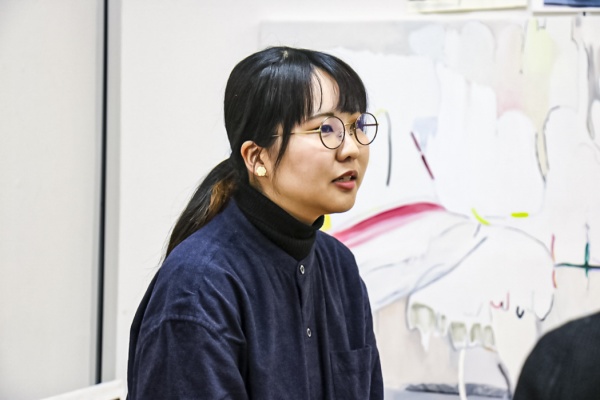

― 気持ちのいい伸びやかな線ですね!お花が広がっていて、樹も枝を広げて、勢いのよさに生命感を感じます。
「中心から広がっている放物線が好きなのだと思います。
描いている時の気持ち良さを大事にしています。あまり元気でない時は、描けなかったりします。」

― ドローイングを描いてから絵を描かれていることが多いですか?
「ドローイングを描いて、まず、線の気持ち良さを土台として、大きな枠組みを作ってから、その上に感情をのせて遊んでいきます。」
絵具箱の中には、油絵具とアクリル絵の具。その他にクレヨン、色鉛筆、水彩色鉛筆、墨、筆ペンも。線の描き分けは、直感的に決まっていく。墨の濃淡や滲み、カリッとした線やしなやかな線などが、モチーフの生き生きとした表情や空気感を描き出す。


― 白が綺麗で、印象的ですね。
「白が好きなんです。真白のキャンバスが綺麗だと思っているので、『お邪魔します!』って思って描いています。白を綺麗に描きたいというのは、結構意識しているかもしれないです。」
― 白は光なのですか?
「それが、混在していて、ここは光だけど、ここは地の白い色で、周りとの色の関係で白が見えるところもあるし、光が当たっているから白いところもあるし、どちらかにしてしまった方がいいのではという話もあったりするのですが、そこは曖昧にしておきたいと思っています。」
■苦しみも含めての楽しさ
― 今までに絵を描いてきて、苦しかった時はありますか?
「基本ずっと苦しいです。でも、それが楽しいというか、そういうのもひっくるめて好きなので楽しいです。幼稚園の時には、みんながブドウを描く時に、私だけ違うのを描いて、みんなに『それ違うよ!』と言われ、周りと違うしんどさを、人生の一番始めのしんどさとして覚えています。中学高校になると、周りに評価されたいがために必死で描き、誰かに一言『変だよ!』と言われるとすぐに描き直していました。すると絵画教室の先生に、『そういうのは、自分で決めるんだよ』と怒られ、その通りだなと思いながらも苦しいなあと思っていました。今でも描きたいのにうまくいかないと苦しいのですが、その分、描けた時の喜びは大きいです。」

― 子どもの頃、絵を習われていたのですか?
「5年生から通うようになった絵画教室の先生は、あんまり技術的なことを言うような先生ではないのですが、無言のメッセージをいっぱいいただきました。先生も自然とか文化とか民俗とかから受けている影響が強い方で、その先生の影響も自分の今の絵には大きくて、見たものを見たように描くだけではなく、もっと私の内側のものを出して描いていくということの、背中を押してくださったような感じがしています。私が優等生に描こうとしていたので、絵が縮こまってつまらなかったと思うんですね。そこで、私がいい子に描いていると先生が私の隣に来て、『クレヨンというのはな、こうやって折って使うんだよ!』と言って私のクレヨンをポキッと折って描いてみせる。パッションのある先生で、そういうショック療法をいっぱい受けて、私の心がどんどん開いていき、解放されていった感じがあります。」
― 好きな芸術家はいますか?
「最初に、マーク・ロスコです。高校生の時に千葉の川村記念美術館にあるロスコ・ルーム(ロスコの作品だけが飾られている展示室)に行って衝撃を受けました。それまでは写実的なものをやっていたのに、初めて抽象的な絵に出会って、『私のお母さんここにいたの!!』みたいな、巨大な救いみたいな、豊かな気持ち、不思議な気持ちになりました。
サイ・トォンブリーとか、抽象度が高いけれども揺さぶられるものがある、子どもだった時の感覚を引っぱり出してくれる、そういう作家に結構惹かれます。
あとは、絵本作家の荒井良二さんもすごく好きです。」
― 今、一番幸せを感じる瞬間はどんな時ですか?
「今は、絵を描いている時です。絵を描くのも幸せですが、普通に暮らしている時に、小さい幸せがいっぱい繋がっていくこと。趣味の散歩で綺麗な光を見たり、何か見つけたりとか、いい景色に出会ったり。白菜を半分に切ってパカッと割った時にその断面の美しさを見た時。朝起きたときのカーテンから射す光が部屋の壁に写っている形を見た瞬間とか。」
― 光の表現に特徴があるように感じていたのですが、普段から光をよく観察されていますか?
「確かに光を見ている気がします。多分無意識に光を観察している感じです。植物も好きでよく見ているのですが、気がつくと植物の向こう側から射している光を見ています。」

■幼児はなぜ絵を描くのか?
― 美術教育研究科では、作品と論文の両方が課せられているようですが、修士論文は、どんなテーマで書かれたのですか?
「幼児はどうして絵を描くかです。どんなきっかけでいつから絵を描くのが嫌いになるのかも気になって。どういうものに背中を押されて絵を描くのかがわかると、支援しやすいと考え、明らかにしたかったのです。」
― 論文の結論は、どうなったのでしょうか?
「楽しくて遊びで描くと言うのは簡単だけど、実は、周りに見て欲しい、認めてもらいたいというメッセージが結構強くあると思います。描いて終わるのではなく、描いたものを誰かに見せて認めてもらう、飾ってもらえた、褒めてもらえた、自分一人でやれたというのを『認められたと思うこと』でゴールなのだと、自分なりにわかりました。子どもが成長していく上で、あなたはそのままでそこにいていいのだ、ありのままでいていいのだと感じることが大切です。」
「周りと同じようにできるとか、平仮名が誰よりも上手に書けるとか、掛け算九九が誰よりも早く出来るとか、お利口に座っていられたとか、静かに出来たとか、そういう側面で評価されていることが、今すごく多いです。でも、やはりそれだけだと危うさを感じます。実際それが出来ない子たちが否定されて沈んでいくのは、危険だと思うんです。生まれながらに個性や得意不得意があって、生きていくのがみんなのやっていることなので、成績などの判定は、彼らの尊厳には全く関係がない。無意識でも彼らが安心して、彼らが『自分は何何が苦手だけど、みんなと一緒にいていいんだ』とか、そういうふうに思うきっかけになる場所がもっと増えないと、実力主義になって危険だと思うんですね。絵を描く時間は、そういう評価や実力、点数を抜きにして、『あなたがやったことはまず認める』というものだと思っています。」

■「好きなことを一人で」から、「好きな分野で人と関わって」へ
― 藝大大学院での2年間は、どんな時間でしたか?
「自分と向き合ってじっくり考えた時間だったと思っています。学部の時は、課題・教職の授業・教育実習・美術教室のことなど、目の前のことに必死だったけど、この2年間は、ワークショップなど実践的なこともやったのですけど、そこから自分はどう思ったのか、本当にこのままでよかったのかなど考えました。自分は、なんで絵を描いているのだろうとか、美術教育でどういうことをやりたいのかとか、じっくり考えた、入り口に立てた時間だったと思います。」
― もともと美術教育を目指していらっしゃったのですか?
「作家になりたかったのですけど、それだけでは食べていけないからと思って、教員免許も勉強していました。ところが、教員になるのに何か足しになると思い、児童館や美術館で子ども向けのボランティアをやってみたら、それが楽しくて、喜びになりました。それまで、『私は一人で好きにやっています』と思っていたのですが、自分の好きな分野の中で与えたり与えられたり人と関わるのが、感覚として鮮明に感じられたのがすごく嬉しくて、どっちもやりたいなと思うようになりました。それまでは、絵を描くことの比重が大きかったのですが、今は美術教育的なものと半分半分くらいになっています。」

■作家としても教育者としても
― この先の計画や将来の夢は?
「絵は、ずっと描いていきたいなあと思っています。それは、有名になりたいとかではなく、誰に何か言われようとも言われなくとも、作家としてずっと描いていきたいです。
美術教室をやりたくて、目標は自分の教室を持つことですが、NPO などでも広く活動できるところに入っていきたいです。」
― 論文に書かれることとご自身で制作されることとは、通じているところがありますか?
「そうですね。子どもの時の方が感性も敏感で、今よりもすごい速度でいろいろなものを見て感動して刺激を受けていたなあと思っていて、それは忘れたくない。子どもに対する憧れと尊敬とがまずあるので、子どもたちのいい美術の環境をということで論文を書いているのですけど、自分の絵も、型や技術やセオリーみたいなものから抜け出して、子ども的な感性を持って描いていきたいと思っています。」
― 本日は、ありがとうございました。作家としても教育者としてもご活躍されることをお祈りしています。修了展で、完成した作品を鑑賞させていただくのをとても楽しみにしています。
「絵は、全てのものを包み込んでくれる優しくて大きな器だ」と捉えている安島さんが、美術教育の場で実践しようとしていることは、絵を通して子どもたちのありのままの存在を受け止めていくことでもある。美術教室で子どもをよく見てきた安島さんだからこそ、評価主義の社会で子どもたちの置かれている状況に危惧を抱き、子どもの感性を大切にし、その一人一人の存在を認めつつ育てていこうとしているのだろう。そんな先生に出会えた子どもたちは、おおらかに自己表現をし、自己肯定感を抱いて成長していくことだろう。
安島さんには、導いてくださる先生や彼女のやりたいことを認めて応援してくださるご家族がいらっしゃった。絵の先生が、「人にどう評価されるかを気にせずに、内面を解放していいのだ」と背中を押してくださったように、これからは安島さんが誰かの背中を押す番になっていくだろう。いつの日か、安島さんの美術教室から、未来の先生がまた生まれていくのではないだろうか。
そして、安島さんの作品世界に魅了された私たちは、今後の作家としてのご活躍も楽しみにしている。

取材|原田清美 鈴木重保 ふかやのりこ 深田未来(アート・コミュニケータ「とびラー」)
執筆|原田清美
 とびラー3年目。とびラーになって嬉しかったことの1つに、藝大生インタビューや卒展修了展さんぽ、藝祭さんぽを通して、素晴らしい作品とそれを創造するアーティストに出会え、作品の生まれる背景を知り、その感動を来場者の方と共有できたことがあります。これからもアートと人をつなぐ活動をしていきたいです。
とびラー3年目。とびラーになって嬉しかったことの1つに、藝大生インタビューや卒展修了展さんぽ、藝祭さんぽを通して、素晴らしい作品とそれを創造するアーティストに出会え、作品の生まれる背景を知り、その感動を来場者の方と共有できたことがあります。これからもアートと人をつなぐ活動をしていきたいです。
2020.01.25