
2024.03.30
執筆者:小野関亮吉

東京都美術館の正面入り口エスプラナードにある、大きな銀色の球体。シンボルのような存在のこの彫刻は、井上武吉の《my sky hole 85-2 光と影》(マイスカイホール)という作品です。とびラーの多くは、この作品への愛着を込めて「マイスカ」と呼んでいます。
大きな球体は全体が鏡面になっていて、上から下へ、斜めに貫通する穴が開いています。マイスカの前に立つと、自分や建物を映してみたり、穴をのぞき込もうとしてみたりと、何かしらのアクションを起こしてしまう、魅力あふれる作品です。
この作品は、ステンレス製の球体と鉄製の台座で構成されています。2つのパーツの関係をよく見てみると、台座の形が球体の影のように見えると気付かれる方が多いのではないでしょうか。素材の質感から見ても、全方位に光を反射するピカピカの球体と錆びた赤茶色の台座のコントラストが、まさに「光と影」を感じさせます。
球体部分があまりにも目を引くため、影部分はなかなか注目を浴びることがないかもしれません。私たち「太陽とマイスカととびラーで作るラボ」は、この影の部分に関心を寄せるとびラーが集まったとびラボです。
東京都美術館の作品紹介の動画<https://www.youtube.com/watch?v=1n0-t8jhEKk>でも語られているように、球体を貫く穴の角度は、作品の基本設計が行われた1984年12月8日正午の太陽光の角度となっていて、またこの日時に球体が作る影の形に沿って鉄の板でできた台座が付けられているとのことです。
台座が球体の影を表していることに、間違いは無いようです。
12月8日は作者である井上武吉の誕生日でもあることから、とびラーの間では、「作者の誕生日の正午に、球体の影が台座の形と一致するらしい・・・」と、まことしやかに囁かれていました。
しかし、実際に12月8日に影の形を観察してみても、影は台座の範囲を大きくはみ出し、一致することはありません。作品が制作された場所(一説によれば鎌倉の工房)と、現在の設置場所が異なるから重ならないのではないか?あるいは、制作されて以来の歳月の間に太陽高度が下がったのではないか?などと、さまざまな憶測が巡りました。
だとしたら、今の場所では、球体の影と台座の形はいつ一致するのだろうか?球体の影と台座がピッタリ重なる角度の太陽が出るその日を、私たちは検証し切れずにいましたが、ある日突然、1人の来館者の方からいただいた情報により実態が明らかになったのです。

その方(ここではTさんとさせていただきます)は、以前「とびラーによる建築ツアー」<https://www.tobikan.jp/learn/architecturaltour.html>に参加されました。その際に、当時のとびラーとの雑談の中で「作者の誕生日の正午に、球体の影が台座の形と一致するらしい」という噂を聞いたことを覚えており、実際に12月8日に来館して観察されたのだそうです。
そして影と台座が重なっていないことを確認しました。ではいつなら重なるのだろう?と興味を持ち、調査を始めることにしたそうです。Tさんは、マイスカの座標、球体の高さ、台座の長さなどのデータを揃えました。そして、台座と球体と太陽が一直線に並ぶ時の太陽方位、台座の先端を球体の影の頂点が通過する時の太陽高度、その両方が重なる日時を計算で割り出しました。
するとその日時は、「立冬」と「立春」であることを突き止めたのです。
僕たちがTさんの存在を知ったのは、「エスプラナードで会いましょう」<https://tobira-project.info/blog/20231216_esplanade_de_aimashow.html>というとびラボの準備をしている時でした。

2023年に実施した「エスプラナードで会いましょう」の様子。
たまたまお声がけしたとびラーがTさんのお話をうかがっていると、興味を持ったとびラーが集まりました。中にはメモを取るとびラーもいました。するとTさんは、後日この研究と観察の資料をとびらプロジェクト宛に送ってくださったのです。
そこには、作品の座標、採寸データ、太陽方位と太陽高度の数値が実に詳細に書かれていました。さらにそれだけでなく、球体の影が台座の形と一致した状態を含む、前後数日間の観察記録が、写真と共に記されていたのです。この資料さえあれば、今後は誰でも球体の影が台座の形と一致する日時を分単位で知ることができます。みんなで資料を回し見ながら、個人でここまで深く研究されている方がいるのかと驚きました。
Tさんが導き出した、台座と影が一致するタイミングが二十四節気の「立冬」と「立春」であるという事実から想像するに、作者の(あるいは作品の設置に関わった何者かの)何らかの意図を感じます。そしてそれを、観察によって解き明かしたTさんの情熱には敬服するばかりです。
Tさんの研究結果を提供していただいた以上は、とびラーとして、人と作品、人と人、人と場所をつなぐ活動に発展させたいと思いました。とびラボでは、一年に二度しか起こらないこの現象に合わせて何ができるのか、Tさんの資料の数々を目の前に広げやりたいことのアイデアを出し合いました。
自然が相手のため、天候次第では影が出ないこともあり得ます。それゆえに、一般の方を公募で事前に募集したりイベントとして広く告知したりするスタイルは不向きです。それよりも、ふらっと美術館に来てみたらなにやら人が集まっていて、聞けば今日は野外彫刻作品の台座と影の形が一致する日なのだと。思わずそこに居合わせた人たちと「へー」と盛り上がったよ。そんな風に、たまたま出会った人と人が作品を介してつながれる、このラボではそういう一時を作りたいという意見がでました。具体的にどのように実現できるのか、思案し続けています。
マイスカの影に注目したことで、私たちは、エスプラナードで見られる他の野外彫刻作品や建物、自然が生み出す様々な形の影の美しさにも気づきました。
4棟が立ち並ぶ公募棟の四角い壁面には、巨大な三角形の影ができます。反対側に位置する企画棟からは、その前を人々の影が行き交い、なんともドラマチックな光景を見ることができます。無意識に明るいところに目が行ってしまうのが人間の性かもしれませんが、影に注目することでトリックアートや切り絵を見ているような感覚になります。世界の裏側に入ったようなこの不思議な感覚を、みなさんにもぜひ味わってみてほしいです。


台座と影の形が重なるその日時が近くなると、このとびラボに参加したとびラーを中心に誘い合って、マイスカの前に集まっています。そして来館者の方も何人か興味を持ってくれて、一緒に鑑賞することもできました。今のところこのとびラボでできたことは、作品にできた影を他の人と一緒に鑑賞した、作品だけでなく影の形や現象が面白いことを誰かと共有しただけです。でも少なくともとびラーの中では、徐々にこれらのことに興味を持つ人が増えてきているように感じています。
この野外彫刻と影の観察の面白さが他の来館者の方にも知れ渡り、特に「立冬」と「立春」にたくさんの人が集まり、マイスカの影と台座が重なる瞬間に歓声が起こるような景色が見られたらいいなと思います。その時は、その場にコミュニケーションの輪が広がるような何かができるといいですね。例えばハイタッチでもいいし、例えばご来光を迎えた時のようにみんなで合掌したりするのも面白そうです。
そして、マイスカの影には実はもう一つ面白い仕組みがあることも、Tさんが教えてくれました。
「立冬」と「立春」を挟むある時期(おおよそ11月上旬から2月上旬まで)には、マイスカを貫通する穴を通り抜けた光が台座の上で様々な形に変容します。台座の中央に光が集まった時は、驚くほど強い光の塊を見ることができます。

光を受けた立体、その影、さらに影の中の光。マイスカは動きませんが、太陽の光を身に受けることで、季節や光などの常に動いているものの方を見せてくれる、マイスカはそんな作品でもあるのだと知ることができました。この1作品だけでも年間通して観察する面白さがあることを、Tさんの活動から教わりました。
これを読んでいただいた方が東京都美術館に来られた時、マイスカの周りをぐるりと回って影に思いを馳せていると、どこからか現れたとびラーと出会うかもしれません。その時は、太陽とマイスカととびラーとみなさんで、その一時を楽しみましょう。

執筆者:11期とびラー 小野関亮吉
普段はゲームソフトの開発現場でプロジェクトマネージャーをしています。公私共に人と関わる機会が少なくなっていることを感じ、コミュニケーションが生まれる仕組みやコミュニティ作りに関心を持つようになりました。美術館は作品を鑑賞するだけでなく、誰かかと出会える場所であることを伝えていきたいです。
2024.03.28
『とびdeラヂオぶ~☆』はとびラボです。
活動期間:2023年7月~2024年3月
頻度 :月に1~2回
■「とびLOVE#1」のゲスト・スタッフ越川さんととびラーで試聴する様子
■趣旨 美術館に興味のない人や足を運んだことのない人のきっかけをつくりたい。
( “すべての人に開かれた「アートへの入口」”に足をかけてほしい!)
■ラジオをツールとしたのはなぜ?
このとびラボは、「とびラーのなかでラジオをきく人が思っていたよりたくさんいたので、『ラジオとアートコミュニケーションをテーマに話してみたい』」というラジオの仕事に携わっているとびラーの思いがきっかけとなり始まりました。話していくなかで、ラジオは話し手と聞き手が1対1でつながるメディアであること。その強みを生かしラジオを通して 「東京都美術館の魅力を知ってもらいたい!」「東京都美術館に関わる様々な人の話や推しポイントを我々メンバーがききたい!知りたい!」ということになりました。
■これまでのラボの流れ

▼なりきり期…集まったメンバーで自身がラジオDJになったつもりで、好きな音楽を選曲し自己紹介。
また、ある日のラボでは「マティス展」が開催中だったので、マティスの作品をイメージして各々音楽を選曲してみました。そのようにしてみたことで、音楽とアートという組み合わせでできることについて話が膨らみました。
▼迷走期…ラジオを介してしたいこととは?となったとき「東京都美術館のミッションに立ち返ろう」「興味のある人は自ら情報を取得するけど、そうでもない人たちにも知ってもらうきっかけをつくりたい」「中高生の放送部と一緒になにかできないか?」など、思いばかりがどんどん膨らみ迷走してしまったのでスタッフに相談したところ、結局わたしたちは「ラジオ番組が作りたいんだ!」という明快な答えにたどり着きました。とはいえ、ラジオ番組を制作したことがないメンバーがほとんどだったので、どのような形で実現できるのか、録音や進行も試しながら、まずはとびラー同士で聞けるような番組を制作してみようということになりました。今回の企画の内容は①美術館に関わる様々な人(警備員さん、ショップ店員さん、来館者など)の話を聞きたい。②とびラー内コミュニケーションの活性に役立てたい。この点に関しては、約130人のとびラーそれぞれが様々な活動に取り組んでいるため、お互いが知り合うきっかけが意外と少ないと感じました。そこで、ラジオというメディアを通してとびラー同士がお互いを理解する機会を作りたい。そうすることで、とびラー同士のコミュニケーションがより活性化し、活動の幅が広がるのではないかと考えたのです。この思いを形にするべく始動しました。スタッフにも相談し、まずは身近なスタッフやとびラーに美術館についての話を聞くという、インタビュー番組の制作が決定しました。
▼制作実践期
方向性が決まり、さっそく「とびLOVE」というタイトルの番組制作にとりかかりました。この番組タイトルには、愛してやまない東京都美術館への思いを語ってほしい・聞きたいという意図をこめました。番組の長さは10分程度で、移動中やすきま時間に気軽に聞けるよう、また内容は、話してくれる人の人柄が少しでも伝わるものにしようと決めました。
制作過程…基本的にインタビュアーが話してみたい人に自ら依頼するところからスタートします。収録はハンドサイズのレコーダーを使用しました。ヘッドホンをつけて、音声がうまく録れているか音のバランスを確認しながらの作業です。初めての収録の時はドキドキでした。収録場所はとびラーの主な活動場所であるアートスタディルーム。初めのうちは部屋の静かな場所を選んでいましたが、進めていくにつれて同じ部屋でミーティングしている他のとびラーの声も番組のエッセンスとして収録するようになりました。
編集作業も、とびラーが担当。番組にはオープニングテーマやエンディングテーマもつけ、場面転換に使用する番組のタイトルを乗せた「ジングル」は、ギターを弾けるラボメンバーが作りました。また、番組タイトルをラボメンバーの子どもや、ゲスト出演者に言ってもらい、その声を乗せたバージョンのジングルも制作。様々な声が番組にいろどりを添えることになりました。出来上がった番組はラボメンバーで試聴し、カットしてもいい部分について話したりして最終的な番組の形に仕上げます。そして、とびラーには聞こえない・聞こえにくい仲間がいるので、文字でも番組の内容が楽しめる「文字版」を制作することにしました。番組の最終版が出来たところで文字起こしを行いそれをもとに文字版を制作します。文字版もラボメンバーで最終チェックをして完成です。完成した番組はダウンロードで聴取できるようデータをアップし、とびラー全員が聞けるようにお知らせをしました。
番組について…第2回目からはゲストにインタビューする人と、番組のオープニングとエンディングの案内役(ナビゲーター)を分けることにしました。そうすることでインタビュアーが変わっても番組の始まりと終わりをいつも同じ声でおとどけできるので番組自体の統一感がでました。また、全5回を通して共通していることはゲストの人となりが分かるインタビューだということです。いつも接しているスタッフがアートと関わることとなったきっかけや、とびラーがなぜとびらプロジェクトに応募しようと思ったのかについて触れることで、距離が縮まった感じがしたり、普通に接していただけでは触れられなかったかもしれない考えや思いを知ることができたりと毎回“驚きや感嘆、新しい発見”があるこのインタビューはとても個性豊かです。インタビュアー×ゲストの化学反応はもちろんですが、インタビュアーによって雰囲気が変わるのです。そして、録音に際しては、他のラボも開催中の部屋で協力してもらいながら実施。番組内でBGMのように様々な声が聞こえてくるのもとびラーの日常が感じられます。

文字版について…聞こえない・聞こえにくいとびラーとも番組の雰囲気や出演してくれたゲストについて共有したいという思いから、目でも楽しんでもらえるようにするため、ただの文字起こしではなく、収録時の様子を書き足したりしています。そうすることよって、聞こえるメンバーにも音だけでは伝わらない部分を伝える手段にもなりました。
番組を聴いたとびラーからの感想…番組ナビゲーターを担当したとびラーの口調のファンという人、「みんなの好きなことが集結してできている感じがいい」「(ゲストの)活動の様子や思いがきけてよかった」「文字版は、音だけでは伝わらなかったところまで知ることができる」などの声が寄せられています。聴いた・見た感想をきけるのもラボメンバー以外のとびラーが関心を寄せて支えてくれているからで、励みになっています。このやりとりがとびラー同士のコミュニケーションにもなっているはずです。
■『とびdeラヂオぶ~☆』は数多く存在するとびラボのなかのひとつのラボです。
我々とびラーが愛してやまないラブの対象・東京都美術館に来てみてほしい。そのきっかけになるようなことを発信したい!と思いつくままに意見を出し合い、膨らませ、想像してきました。たどり着いたのは、まずは身近な気になる仲間の美術館への思いを聞いてみようということでした。このラボを通してゲストの話をきけばきくほど、もっと他の人の話もききたい!という、ききたい欲が湧いてきました。
ラボメンバーからは「妄想から始まってだんだん具体的になって、これからどう発展するか楽しみ」「スタッフやとびラーの人となりをラジオを通してとびラー内に発信できたことで、親しみがわき接するときの心持ちが変化した」「番組を聴いて寄せられた感想を通して、出演してくれたとびラーだけでなく感想をくれたとびラーの人柄もわかった」「寄せてもらったメッセージからどんな思いで聴いてくれているのか想像をかきたてられ励みになった」という声があがっています。また、文字版については「全く予想していなかったが、その場の雰囲気まで伝えられるものになった」「聞こえない・聞こえにくいとびラーにも届けたいと考えて出来た文字版が、聞こえるとびラーにも音で伝わる以外の部分を感じてもらえることにつながった」「文字というのは形も音に通じるものがあると思う」「それぞれの人の持っている個性にあった文字があるように、番組らしいカラフルな文字版があると視覚的によりうまく伝わるのではないか」などの見解もでました。
番組も文字版もまだまだ可能性を秘めているとメンバー全員が感じているところですが、10期のとびラボメンバーが開扉するのを機にいったん解散。
スタッフ、とびラー仲間はもとより、その輪を広げて美術館に関わっている様々な人々に話をききたい。そして、知りたい、知らせたい。このラボを通して美術館と人とをつなげたい思いは広がっています。
・とびラブはつづく・・・。乞うご期待!!
執筆:

柴田 麻記(12期とびラー)

染谷 都(12期とびラー)
2024.03.27
【ラボ実施の経緯】
とびラー11期の菊地と、とびラー10期の金城。
11期と10期で期が異なる私たち。
複数のとびラボで一緒に取り組む過程を経て、個性が違う私たちで一緒にラボを行ってみようという話になりました。
ラボを行うなら自分達も楽しく取り組みたいという想いから、「アートと自分達が好きなもの・得意なことを掛け合わせてラボを行ってみよう」と2人で話し合いました。
金城は化粧が好き。
菊地は歴史が好き。
化粧の歴史から見るアートの世界は、今までの自分達の見方とは異なる視点から、アート鑑賞に膨らみと広がりを与えるきっかけになるかもしれない。
そんな想いから、「化粧史×化粧師」ラボを企画・実施しました。
化粧史×化粧師ラボは、2部構成で進めました。
①化粧史:化粧とアートの歴史を参加者が調べてきて発表する時間。
②化粧師:化粧品業界でお勤めの方がおり、眉毛カットを体験する時間。
💄化粧史:アートと化粧の歴史を学ぶ💄
2回にわけて開催しました。
1回目は、菊地が、化粧とアートの歴史について参加者への講義を行いました。
1回目の集合写真
1回目はZOOMを併用し、遠隔でもラボに参加できる設計にしました。
2回目は、参加メンバーが各々「化粧とアートの歴史」について資料を作成。作成した資料を元に発表し合いました。
自分が興味を持った「化粧が印象に残るアート作品」について、参加者には歴史を背景として資料を作成してもらいました。
発表は1人あたりの持ち時間を決め、順番に行いました。
参加メンバーで2回目実施の際に作成した資料の一部を紹介します。
日本の化粧とアートの歴史から、世界の化粧とアートの歴史まで、幅広く見ていきました。
「化粧の歴史」に触れた後、歌川国貞の《今風化粧鏡》と、ロバート・フレデリック・ブルームの《化粧する芸者》の2作品を見てみました。
江戸時代は、首筋をたしなむという表現があったほど、うなじの色気に重きを置いていた印象。
絵師は斜め後ろから描き、鏡を通じて対象者を描く構図が多い。
歴史を知りアートを見ることで、その時代に定義された美しさに着目して鑑賞する新たな視点を得られました。
💄化粧師:性別を問わず、化粧に触れてみよう体験💄
化粧関係の仕事に携わっているアート・コミュニケータがいたので、性別問わず化粧に触れられる眉毛カットと眉毛プロポーションのレクチャーを行っていただきました。
男性も女性も、眉が整うと印象が変わりますね。
眉毛を整えてもらった後の方が、表情が明るくなった印象です。
化粧史×化粧師ラボを実施し、アートと別ジャンルの掛け合わせの可能性を感じました。
男性の参加者も数名おり、このラボ実施まで化粧の観点からアートを見たことがなかったとのこと。
性別によらないアートの見方を1つ体得したという感想もありました。
眉毛カットでは、第三者を通して装うことを楽しみました。
装うことは人の視線を意識する行為の意味合いもあり、眉毛カットの様子を見守られることは、まるで自分が作品となり鑑賞者から見られているようだ、との声もありました。
アートと自分が興味・関心のあることを掛け合わせると、新しいアートの見方と出会える。
日常で接するものとアートを掛け合わせると、新しい世界が芽吹くかもしれません。
このラボを実施し、化粧の歴史は深く、西洋と東洋で化粧への異なるアプローチの仕方が絵画に反映されていることに気づきました。
古代エジプトでは、瞼に塗る顔料は日差しから目を守る効果もあったとのこと。
「綺麗に装う」だけではなく、「その時代の実用性も兼ねる」という観点から化粧を見ると、歴史を知る、アートを見る楽しさが広がりました。
発表の場を設け、共有したからこそ発見できた楽しさでした。
自分が楽しいと思ったことを、発信していく。
やりたいと思ったことに対し、誰かが興味関心をよせてくれる場がとびらプロジェクトであると感じたラボでした。
2回目の集合写真
眉毛を整える企画があったため、全員活動場所に集合しました。
執筆:
とびらプロジェクトに参加して、美術館は作品を見るだけではなく、アートを通してつながるコミュニティスペースであることを知りました。より多くの方に、アートとつながりを楽しんでもらいたいです。
個人的に美術を楽しんできましたが、とびラーになり、皆で作品を見る楽しさに目覚めました。その楽しさを十分堪能するには、人の話を「じっくり聞く」ということが大切だということも教えてもらいました。(会社の会議に参加するたびに、全員、鑑賞実践講座で鍛える必要があるな、強く感じる日々です。)
2024.02.13
消しゴムはんこラボ。
消しゴムを彫ってはんこを作るラボ、と思われるかもしれませんがそれは活動の一部です。
作品を鑑賞してそれをモチーフにはんこを彫り、「障害のある方のための特別鑑賞会」の参加証送付用封筒に押し、参加証を封入し、特別鑑賞会でその封筒を展示して、来館者の方々に見て頂き、感想を聞くラボです。長いですね。
「障害のある方のための特別鑑賞会」とは障害のある方がより安心して鑑賞できるように、東京都美術館の特別展の休室日に開催する鑑賞会です。申込んだ人には参加証をお送りしていますが、よりウェルカムの気持ちをお伝えしたいと思い、特別展に関連するはんこを作成し、送付用の封筒に押して送付しています。
今年度は「マティス展」、「永遠の都ローマ展」、「印象派 モネからアメリカへ ウスター美術館所蔵」で実施しました。
「マティス展」の特別鑑賞会の様子はコチラ
「永遠の都ローマ展」の特別鑑賞会の様子はコチラ
まずははんこのモチーフとなる作品を選びます。
展覧会で作品を鑑賞しながら、またはチラシや公式ホームページから彫りやすそうな、いえ、彫りたいと心が動く作品を選びます。
作品を選んだらどの部分を彫るのかデザインを決めます。
封筒に押すサイズは9×7cmです。これに収まるように縮小したり、一部分を切り取ったりします。
同じ作品でも切り取り箇所や表現に個性が現れます。
例えばチラシにも使われたこちらの作品。
同じ作品を元にしたのに、彫ったモチーフはこんなに違います。
このようにバリエーション豊かなはんこが出来ました。
そしてメインの彫り押し作業です。
初めて消しゴムはんこを彫る人も多かったですが、道具は100均でも揃えられ、
中学時代の彫刻刀を数十年ぶりに取り出す人もいました。
また道具を一度に揃えられない場合は、ラボのメンバーに借りて仕上げたりもしました。
線を彫るのか残すのか、どの線を生かすのか、おのおの作品と対話をしながら、黙々と彫り進めます。カニでも食べているのかと思うほどの無言の時間が流れます。彫っているところの写真はいつも頭頂部しか映りません。
彫り方はとびラー同士で教え合います。何期も前のとびラーから受け継がれている技もあります。事前にYouTubeの動画を観て勉強してくる人もいました。
彫れたらいよいよ封筒に押します。
図案を反転して彫っているので、押して初めてどんな作品かわかります。
また、インクの色や押し方でもイメージが変わります。
こうしてはんこの押された参加証送付用の封筒が完成しました。
様々なはんこができました。
並べると壮観です。
線そのものを彫る、線の周りを彫る、の違いや、一色で表したり、浮世絵のように色を重ねたり、同じモチーフでもこんなに違ったはんこになります。
違いを楽しむのも、消しゴムはんこの面白さです。
完成した封筒に参加証を入れる封入作業もスタッフと一緒に行っています。どんな方のお手元に届くのか、喜んでもらえるのか、どきどきしながら作業をします。
また、今年度から特別鑑賞会当日に消しゴムはんこを押した封筒の展示を行いました。
今まで参加証の封筒を受け取られた方から、押されたはんこについて「これは誰が彫っているの?」「みんな同じ絵柄なの?」「他にどんな絵柄があるの?」というお声を頂いたので、来館者の方々に消しゴムはんこを紹介しようとなったのです。
先ずは机上で展示のレイアウトを考えます。
その後、車椅子の方にも見やすいよう、目線を考慮して位置を調整していきます。
そして特別鑑賞会当日。
全ての封筒を展示したボードをアンケートコーナーに設置して、来館者を迎えました。
特別鑑賞会の申し込み方法は、Webフォームと、メール、はがきの3種類です。
メールとはがきで申し込んだ方には、参加証を封筒でお送りしますが、Webフォームで申し込んだ方は、参加証がメールで届くので、はんこが押された封筒の存在を知りません。8割以上の方がWebフォームからの申し込みなので、はんこが押された封筒をここで初めて見る方が大多数です。
また、封筒をお持ちの方も、他にどんな絵柄があるのか興味深げに見てくださいました。
封筒の絵柄や、モデルの実物の作品の感想を語ってくださったり、同じ作品でも彫る人によって表現の違いがあることに気付いてくださったり、多くの方が足を止めてくださいました。
今まで届いた封筒を全部取っておいている方、届いた封筒のはんこをイラストに描いてくれた方もいらっしゃって嬉しい驚きでした。
中には封筒が欲しいから次回はWebフォームではなく、はがきで申し込むと言う方もいらっしゃいました。嬉しい反面、時代に逆行して頂くのも気が引けるので、Webフォームで申し込んだ方には、封筒の代わりにはがきサイズの紙に押したはんこをランダムで1枚お土産として持って帰って頂きました。
裏返しにした紙を1枚引きます。どんな絵柄かは引いた後に表を見てからのお楽しみです。絵柄を見た方からは楽しげな歓声があがっていました。
消しゴムはんこラボは長く続いているラボですが、その時々で形を変えながら活動をしています。封筒の展示はコロナが明けた今年度から始めたことでしたが、今まで聞けなかった来館者の方たちの感想やお話を伺える貴重な機会となりました。
消しゴムなんて初めて彫るというとびラーも大勢参加してくれました。また、彫らなくてもボードの作成や封入作業に参加してくれたり、鑑賞会で来館者にボードの案内をしてくれるメンバーもいて、展示を盛り上げてくれました。
印刷かと見紛うほどの繊細なはんこを彫る人も、味がある太い線のはんこを彫る人も、彫らない人も、はんこを通じて作品と鑑賞者に向き合う。それが消しゴムはんこラボです。
美術館で作品を観た感動を何かに残したいと思ったそこのあなた、文章、模写の他に消しゴムはんこも一つの選択肢にぜひ加えてみてください。

執筆: 篠田綾子(10期とびラー)
超絶技を繰り出す人もいる消しゴムはんこラボで、初めての人も気後れせずに参加できるような大雑把なはんこを彫っています。上手くなくても楽しければいいんです。
2023.12.16
「みえない人」も「みえる人」も、お互いがいるから、みえること、気づけることがあります。「みえない人」と「みえる人」そして「とびラー」が、作品鑑賞を通じて障害の有無に関わらずフラットに対話することで、新たな発見や気づきを分かち合いたい。この企画は、そんな思いからスタートしました。
半年近くにわたる活動では、とびラーは実際に「みえない・みえにくい」状況とはどういうことなのかを考えることから始め、みえる・みえないの垣根を越えてフラットに対話し鑑賞するにはどうすればよいか、議論を重ねていきました。
プログラムの骨格が決まると、当事者(視覚障害者)の方と一緒にトライアルを行い、そこで出た意見も反映しながら、安心・安全かつ、みんなで楽しめるプログラムへとブラッシュアップしていきました。
そして、いよいよ本番当日! 一般応募いただいた「みえない人・みえにくい人」と「みえる人」をお迎えしてプログラムを開催し、たくさんの気づきと発見に満ちあふれた時間となりました。
■開催日時: 2023年12月16日(土)
■参加人数: みえない人・みえにくい人(視覚に障害のある方):6名
介助者:4名
みえる人(晴眼者):5名
とびラー:17名
■会場:上野アーティストプロジェクト2023『いのちをうつすー菌類、植物、動物、人間ー』展、アートスタディルーム
■プログラム概要:「みえない人・みえにくい人(+介助者)」と「みえる人」、とびラーによる4〜6名のグループに分かれ、アイスブレイクを経て『いのちをうつすー菌類、植物、動物、人間ー』展の3作品をそれぞれ鑑賞。その後、一緒に鑑賞したことでの発見や気づきをシェアする。

<開催に至るまでのプロセス>
「みえない」「みえにくい」って、実際はどういうことなのでしょう?鑑賞会を企画するにあたり、まずは「みえない」「みえにくい」方がどのように作品を楽しんでいるのか、また、みえる人とどのように共有できるのかを考えました。そこでの気づきから「めざすゴール」や「実現のためのアイデア」を検討していきました。そこで「一緒に作品を味わい、お互いの違いを意識することなくフラットに対話することで、みえない人もみえる人も楽しめる場をつくる」ことを目指そうと決めました。
そうして作ったプログラムを、実際に視覚障害者の方を招いた2度のトライアルを行い、実践するうえでの意見や、アドバイスをもとにブラッシュアップしていきました。
本番の1か月前に展覧会が開幕してからは、実際に展示フロアでの作品鑑賞や移動の動線を何度もシミュレーションし、メンバー全員が各々の役割と持ち場で準備を進めていきました。
開催直前には、目指している対話の場づくりをもう一度思い起こして、「安心・安全な場」そして「楽しむこと」を大切にしようと確認し、開催当日を迎えました。
<開催当日の様子>
1.開会~アイスブレイク
冒頭でとびらプロジェクトとプログラムの概要を説明し、「言葉が大切なコミュニケーション手段なので、今日は感じたこと気づいたことをたくさんお話してください」と大切な思いをお伝えして、プログラムがスタートしました。
先ずはお互いのことを知り、発言しやすい場をつくるために自己紹介。話す人と聞く人を明確にして、触覚という共通の体験を入れて話すとよいのでは、というアイデアから、今回の展覧会のモチーフにもなっている鳥のぬいぐるみを持って話すようにしました。自然と和やかな雰囲気になり、鑑賞への期待感も高まりました。さあ、展示室へGO!
2.作品鑑賞
展覧会場は2つのフロアに分かれ、ゴリラ、鳥、牛、馬、キノコ、草花といった様々な動植物をモチーフにした絵画、彫刻、写真などの作品が展示されていて、各グループ毎に3つの作品を順番に鑑賞していきます。作品と作品の間の移動時間には、展示室全体の空間について、言葉で説明しながら、楽しくおしゃべりします。鑑賞作品が会場全体の中でどのように展示されているのかを伝えることで、みえない人の理解につながっていきました。
また、みえない方それぞれのみえ方に応じて、鑑賞時の立ち位置なども工夫するように配慮しました。参加者の状況を見ながら、適宜休憩も入れて鑑賞していきました。
ご主人や娘さんと一緒に参加された80代のみえない女性。介助者のご主人はアイスブレイクではおとなしい感じでしたが、アホウドリをみて「抱きしめたい」と思いがけない胸キュンの一言!グループ全体が打ち解けて、一気に対話が弾んでいきました。
また、あるグループのみえにくい人は、何とか作品をみてみよう、感じてみようと、作品に近づけるギリギリまで近づいて食い入るように鑑賞されていました。そのあまりの熱心さに、みえる方も感動されて、言葉でその場を補うように発話が増えていき、徐々に対話の場ができていきました。
最初は緊張していた参加者も、作品鑑賞が進むにつれて、みえる人がどのように伝えればみえない人にわかりやすいかを考えて一つ一つ丁寧に話しかけたり、みえない人も説明や問いかけに対して積極的に気づきや質問をするようになっていきました。2作品目、3作品目と鑑賞を重ねていく中で自然に発言が出るようになり鑑賞が深まっていく様子がはっきりとわかりました。そのような姿を見ると、「フラットに対話をし、みんなでみる」という鑑賞は実現できたと思われます。
それは何度も現場で確認した事前の準備と、みえる・みえないに関わらず相手に寄り添う気持ちを持って接したことにより達成できたのだと思います。
1時間の鑑賞タイムを終えて、参加者の皆さんも充実した笑顔でアートスタディルームに戻ります!
3.シェアリング~閉会
アイスブレイクと同じテーブルでのシェアタイムでは、参加者の皆さんの表情もイキイキとしていて、感想話に花が咲きました。例えば、ゴリラの作品では、「一つ一つの表情に喜怒哀楽があるように繊細で豊かに感じられるようになった」というグループもあれば、「みえにくい人にはゴリラの顔は黒い毛玉にしかみえなかった」という感想が出たグループもありました。
みえない人・みえにくい人がどのように対象を見ているのか、対話により得られる共通の体験を分かち合う喜びと難しさなど、他のグループの話を聞くことで、さらなる発見や気づきにもつながり、ふだんみえているようでみえていなかったものに気づいたり、みえていないものをありありと感じられた時間になったようです。
<参加者の感想>
終了後に記入いただいた参加者のアンケートから一部をご紹介します!
・「みんなの見る目が人によってちがう。自分1人だと絵を見ることが難しいけど、みんなと一緒なら見ることができる」(みえない人)
・「見える人から説明してもらうことで鑑賞のきっかけをもらえる。見える人→見えない人への一方向ではなく、会話の中から作品鑑賞が生まれてくる感じがした」(みえない人)
・「アートはみえる、みえないということは関係なく、一緒に鑑賞することで自分自身で発見があった。今までなかなかいけなかった美術館に行こうと思うきっかけになった」(みえにくい人)
・「見えていると思っていたら、実は大して見ていなかったことに気づいて驚きました」(みえる人)
・「見えない人に対して絵を伝えるために、分かりやすい言葉を選ばなければならないことに気づくことができた。見える・見えないの0か100ではなく、見えないのはグラデーションだと気づいた」(みえる人)
・「自分の見方の高さを少し変えるだけで、ものの見方、伝え方はこんなにも深くなるのだと実感しました。ちょっとした変化でコミュニケーションはもっと深まるのですね」(介助者(みえる人))
・「みなさんの感想をお聞きしていると、作家さんの「ここを見てほしい」という意向がちゃんと伝わっているんだと思いました。それをみなさんがきちんと受けとめていることに感動します。生命は美しいとあらためて感じます」(介助者(みえる人))
また、ファシリテーターを務めたとびラーからはこんな声がありました。
=======
「最初は見える人が見えない人に説明をしていましたが、鑑賞が進むにつれ、見えない人の質問によって鑑賞がさらに深まっていくことに皆が気づいて、見える人も見えない人もお互いの立場を平等に感じているように思いました」
「見える人の素直な感想が、見えない人の質問を生み出しだんだんと垣根のない空間なっていきました。和やかで温かい時間を一緒に過ごすことができました」
「描かれているゴリラのイメージについて話した時に「会社のボス的な存在なのでは?」となりました。
Aさん:「俺についてこい」 みたいな感じかな。
Bさん:う~ん…きっと部下には何も言わないと思う。
Cさん:背中で語るタイプですね。
皆さんの想像していたのは昭和タイプのボスだったのかもしれません」
「馬の作品の印象をみんなで話す中で、みえない人の「何となく不穏な感じを受ける」というひと言から競走馬の悲しいエピソードが引き出され、より鑑賞が深まる体験ができました」
=======
たくさんの感想をいただき、もう少しシェアタイムの時間があればとの声も多くいただきました。「みえる人」の中には、今回の体験をきっかけにアート・コミュニケータに関心を持っていただいたり、「みえない人」で、美術館でまた鑑賞してみたい、新しいことにチャレンジしてみたい、と前向きな発言をされている方がいたのが印象的でした。参加者それぞれが何かを感じて、新しい視点が生まれていたようです。
みんなでみて フラットに対話をして 鑑賞を楽しむ。
みえない人とみえる人の対話を通じて、お互いの視点によってよりよく作品を味わうことを目指した「みんなでみる美術館」。
みえる・みえないをハードルと考えるのではなく、その人の特性の一つとしてとらえ、お互いの違いを楽しむ、そんな場になる一歩を踏み出すことができました。
今回の実践を次のインクルーシブな場へとつなげていき、またみんなで一緒に分かち合えますように。
東京都美術館では、たくさんの参加体験型のプログラムや、障害のある方のための特別鑑賞会なども開催されています。また皆さんとご一緒できることを楽しみにしています!

10期とびラー 安東豊
アートを介して対話することで、人と人との多様な価値観や想いがつながり、新しい世界がみえてくる。そんな出会いや化学反応の場に立ち会い、寄り添える喜びを感じています。

10期とびラー 飯田倫子
「遠くに行くならみんなで行け」そんな言葉の意味を強く感じたラボでした。みんなで取り組んだからこそ、「みんなでみる」ことが実現できたと思っています。
2023.12.16
東京都美術館には「エスプラナード」と呼ばれる空間があります。上野公園から正門を通ってすぐ、レンガ色の建物に囲まれた広くて開放的なスペースのことです。館内の建物に入るまでの散歩道となっているその空間は、この美術館の建築的な特徴にもなっています。
とびラーにとっては、来るたびに通るなじみ深いエスプラナード で、来館者に楽しんでもらえるような何かをしたい!と思い立ってとびラボを始めたのが8月のことでした。
具体的に何をするかやその目的については、とびラボに集まったとびラーみんなで考えることにしました。
まずはエスプラナードについて各々が思うことや期待することを話し合ってみました。「せっかくの素敵な空間なのに来館者にあまり意識されずに素通りされているのでは?」「野外彫刻がたくさん展示してあるのにあまり見てもらえていない」「美術館に来た人に展示を観るだけでなくプラスアルファの楽しみをここで提供したい」などの意見が出ました。
そして今度はエスプラナードでやってみたいことのアイデアを自由に出し合いました。
「パラソルや椅子を置いてのんびり過ごしてもらいたい」「レッドカーペットを引いてゴージャスな気分で歩いてもらう」「広い空間を生かしてファッションショーをおこなう」「建物の壁でナイトシアターをやる」「コーヒーを無料でふるまう」などたくさんの案が出てきました。エスプラナードという空間を舞台に、みんなで妄想を広げる時間がとても楽しくどんどんアイデアが広がりました。
次のミーティングでは、たくさんの案の中から本当に自分たちがやりたいこと、ここでやるべきことはなんだろう、と考えてみました。
そこでみんなの意見が一致したことは「エスプラナードを通るどなたでも気軽に参加できる」、そして「アートや美術館をより親しみやすく感じて欲しい」というものでした。
エスプラナードはこの美術館の入り口だからこそ、すべての市民にとってアートへの入り口になるような体験を提供したいと考えました。
その目的をはたすためにできることはなんだろう?と、今度はみんなで実際にエスプラナードに出て来館者の様子を観察することにしました。
美術館に来る多くの人は自分が観たい展示や用事を済ませるために、建物の中にまっすぐ入っていきます。帰りもあまり寄り道をせずに上野公園へと出かけていき、エスプラナードはその通り道となっています。
けれど時折、美術館の正門の前で記念写真を撮る人や、エスプラナードで一番目立つ大きな球形の彫刻《my sky hole 85-2 光と影》に興味を示して鏡のような表面に映り込む自分の姿を覗き込む人たちがいました。
その様子を見てみんなで考えたことは、わたしたちとびラーが来館者に声がけして少しの間立ち止まって話をしたり、エスプラナードを一緒に散歩してみてはどうか?ということでした。
会話を生むきっかけとして、記念写真を撮ってあげたり道に迷っている方の案内をしてみる。そこからコミュニケーションをとれたら、来館者に楽しい思い出を提供できて、美術館に親しみをもってくれるかもしれない。それいいね!とエスプラナードで自分たちがおこなうことを現場で決めました。
また、来館者に声をかける際に、他の来館者とは違うここで何かをする人だと分かる格好をした方が声をかけやすいのでは?と考えました。広いエスプラナードで少し目立つように背の高い帽子をかぶるのと、写真を撮る役割を示すカメラのマークを入れた腕章をつけてはどうか。
するとその場で持っていた紙を折って小さな帽子を作ったとびラーがいました。それをみんなでかぶってみることで、エスプラナードで自分たちがやりたいことのイメージが一気に固まりました。
そうと決まったら手先が器用なとびラーたちがあっという間に帽子や腕章を手作り。自分たちが衣装をまとうことで気分も大きく盛り上がり、これで来館者に喜んでもらいたい!と意欲満々で実施の日を迎えました。
その日は12月とは思えないぐらいの暖かい晴天で朝から美術館に来る人もちらほら。午前10時から声がけを始めました。
しかし最初は緊張し、まっすぐ建物に向かう人に足を止めてもらうことへ少し躊躇しました。けれどこれまでみんなで話し合ってきたことを実践する大きなチャンス、と勇気を振り絞ってエスプラナードを通る人にどんどん声かけをしていきました。そうすると意外と足を止めて話を聞いてくれる人がいました。
この日は特別展が開催されていない時期でしたが、市民が応募して作品を出品する公募展を観に来た家族連れや友人グループが多くいました。「記念に写真を撮りましょうか?」と彫刻や門の前で話しかけると「じゃあせっかくだから」とスマホやカメラを手渡してくれました。中には手作りの衣装をまとったとびラーと一緒に撮りたいと言ってくれるグループもいてうれしくなりました。
「はい、チーズ!」と撮影した後、「今日はなにを観に来られたんですか?」とうかがうと「孫の書作品が入選したので家族で観に来たの」「友達が撮った写真作品が飾られてる」などと話す方が多く、「入選おめでとうございます!」と伝えると照れくさそうにしつつ「ありがとう!」と喜ばれました。そこからアートにまつわる家族の素敵な話や作品への熱い思いを聞いたりして来館者と一緒に会話を楽しみました。
また、置いてある野外彫刻の説明をすると他の作品も観たいと言ってくださる方もいて、ぐるりとエスプラナードを案内しました。
声がけや会話の内容もとびラーそれぞれ得意な話し方があり、エスプラナードのあちこちで笑顔の輪が同時にいくつも出来ていました。中には一人の方とじっくり話し込むとびラーもいて、美術館に来たそれぞれの人のストーリーを聞けるとても良い機会になりました。
行きがけにお話しして展示を観た帰りにまた寄って話かけてくれる方や、「今日ここに来て良かった」と言ってくださる家族もいました。
二時間半の間に合計110組以上のグループとお話ししました。時間が来ても止めるのが惜しい気持ちになりましたがこの日は一旦終了。またやりたいね、とみんなで話しながらエスプラナードを後にしました。
今回の活動を通して、ミュージアムにある「場」から発想して、場と人、人と人を結ぶアートコミュニケーションについてとびラー同士で考えることができました。
また、実際に来館者に声がけして会話をすることで、いろんな方がアートや美術館を身近に楽しまれている様子を知ることができました。
美術館に来る方に楽しんでほしいと始めたことですが、私たちが来館者から美術館の魅力を教えてもらうという、とても良い経験になりました。
今回のとびラボでは最初に目的ややることを決めずにスタートしましたが、いろんなとびラーが自分で企画を提案したり衣装を持ち込んだりみんなで自主的に動いて一つのプログラムを形作ることができました。
例え少しのスペースでもアイデアしだいでコミュニケーションの「場」をつくる活動は、他の美術館や文化施設でもできるかもしれません。またどこかでいろんな人との出会いを楽しみたい、そう思えるとびラボでした。

10期とびラー 池田智雄
美術館・博物館・郷土資料館や音楽ホールなど、人が文化の楽しさを求めて集まる場所が好き。そこがもっと楽しくて親しみやすい場所になるようなことを自分たちでできたらうれしいです。
2023.12.10
・東京都美術館の正門を入ると一際目を引く大きな銀色の球体。
・これは東京都美術館の収蔵品の一つ《my sky hole 85-2 光と影》。彫刻家・井上武吉の作品です。この大きな球体に映り込む風景や自身の姿を楽しんだり、大きく開いた穴から差し込む光に魅了される多くの来館者にいつも囲まれています。
・
・東京都美術館で活動するとびラー(アート・コミュニケータ)も例外ではなく、これまでもこの彫刻を題材としたとびラボ活動が多く企画されました。とびラーは愛を込めて、「マイスカイホール」略して「マイスカ」と呼んでいます。マイスカ愛溢れるとびラーが集まったこの活動は、マイスカを通して野外彫刻作品の新たな鑑賞方法や魅力を発見するとともにとびラーどうしの親睦を深めるため、井上武吉の誕生日(12月8日)を祝う意味もこめて以下のような内容で実施しました。
・
・とびラーどうしの親睦を図る場づくりをみんなで考えて楽しむ。
・マイスカの魅力を語り合う。
・美術館の楽しみ方を考え体感する。
・
・では、早速どんな活動だったのか、見てみましょう。
実施日 2023年12月10日(日)11:30~14:00
・
🔶流れの確認
・マイスカには自然環境に影響される興味深い仕掛けがあります。その一つがマイスカに貫かれた穴から溢れる太陽の光が作る像(日射像)。作者の井上武吉さんの誕生日に太陽光がマイスカの穴を貫くように設計されています。
・太陽の動きにつれて差し込んだ光が作る像はどんどん変化していきます。活動の最初はこの太陽光の観測、光の像の観測です。観測に先立って注目ポイントや観測の流れなどを全員で確認しました。
・
・
・
・
🔶観測
・
・いよいよ実際にマイスカへ移動して観測です。少しずつ日射像が現れ、半月の状態に。刻々と変わる像に目が離せません。
・
・
・
・
・1分ずつ写真を撮って光の円の「成長」を確認。半月から満月状態に、そしてまた形が変わっていく・・やっぱり地球は動いている。観測しつつマイスカトリビアを披露したり、マイスカから感じたことをおしゃべりしたり。
・
・
🔶誕生日会〜球体の食べ物を持って集まろう
・
・
・観測の後はみんなでランチタイム。井上武吉さんの誕生日を祝う意味でマイスカのような球体の食べ物を持って集まりました。銀紙で包んだまんまるのおむすび、プチトマト、チョコレートや飴玉など思い思いの球体の食べ物が集まりました! マイスカを模して台座まで再現したチョコやマイスカの穴の部分を具で表現したおむすびなど楽しい工夫がいっぱいのまるい食べ物の数々についつい撮影会に。
・
・
🔶観測日記
・
・ランチをしながらちょっと真面目に、マイスカを観測・鑑賞しての気づきをシェアしました。
・
・
・刻々と変わっていく日射像。穴を通ってくる光がとても明るくなる瞬間があった。
・日射像の周辺の渦が美しかった。
・マイスカの上に輝く太陽がちょうどマイスカに掛かって、ダイヤモンドリングのようだった。
・マイスカはその球体の上に周囲の風景や空が映り込む。そこまで含めての作品であり、時間や季節、見る角度によって常に新しい作品となっている。
・逆光になるマイスカはどこかから飛来している感じ!
・美術館に来た多くの人がマイスカで一旦立ち止まり写真を撮ったり写り込みを楽しんだりしている。こんなに愛される作品はないかも。
・
・
🔶もう一つの仕掛けのこと
・
・マイスカには台座があります。ですが台座が作品の一部だと気づいている人は案外少なそう。
・1年に2度、この台座とマイスカの影とが一致する現象を見ることができます。地球の自転と公転の関係で重なる日は毎年変わるようです。そして今回の活動でも体感したように刻々と変わる太陽の位置から、影と台座がピッタリと重なるのは一瞬。天候にも左右されるので、見られたらとても幸運です!
・
・展示を見る他にも、東京都美術館でこんな楽しみ方もしてみてはいかがでしょうか。
・
・
・
🔶マイスカのミュージアムもあります
・
マイスカをモチーフに作品を創ることもあります。そんな作品を所蔵するため、「マイスカイホール・バーチャル・ミュージアム」をとびらプロジェクトの共有ドライブ内に設けて、随時とびラーが作品を収納しています。2022年2月22日22時22分に創設しました。下の画像のような作品が展示されています。
・
🔶マイスカからの贈り物
・
・この活動を通じて、わかったことは、みんながマイスカのことが大好きで、そしてマイスカからさまざまなインスピレーションを得ていることです。
・この作品の製作の歴史・作者についてなどの作品研究をしてみて、井上武吉さんによるマイスカ彫刻が全国のあちらこちらにあること、そして太陽の動きを計算に入れて立地していることなどもわかりました。仲間のことを思いながらマイスカから連想される球体の食べ物を考えたり、作品から受けたインスピレーションをもとに新たな作品を作ってみたりもしました。
・たった一つの野外彫刻作品を観察する、鑑賞する、それだけのことからこんなにも豊かな広がりがあります。
・
・野外彫刻作品の特徴でもある時間や空間の移り変わりで刻々と変化する美しさをじっくりと時間を追って見つめることで、その作品の奥にある独特の味わいにも気づくことができました。
・一つの作品を囲んで、様々な角度から作品にアプローチすることで作品についてより深く知り、親しくなることができます。みんなで作品を見ることの楽しさも感じることができます。
・他者の発見を知ることで、新たな視点が自身の中に生まれ、そこでの共感は人と人との繋がりも深くし、鑑賞の幅が広がります。これらはマイスカからの贈り物です。私たちのマイスカさん!ありがとう!
・
・
執筆:
矢野聡子(とびラー10期)
以前は美術館は1人で行って、
藤牧功太郎(とびラー10期)
とびラーになって作品の見方は多様であること、
2023.12.08
◆はじめに
夜間開館日にライトアップされた東京都美術館の美しさ・建築の魅力をともに味わいたい、そんな思いでツアーを開催してきました。12年目を迎えるこのラボ、今までの良さを受け継ぎつつも、刷新してきたこの1年の様子をお届けします。

夜の公募棟。ヤカンツアー参加者だけが入ることができる。
◆実施概要
・開催年月:2023年6月・9月・12月(計7回)
・参加人数(延べ人数):参加者124名 とびラー59名
・開催時間:19:15-19:45(6月)19:05-19:45(9月~)
・テーマ及びコース:ガイドを担当するとびラーがおススメをご案内
◆ツアーの様子
ツアーでは、夜ならではの建築や空間の見どころを30~40分で紹介しました。ここでは、2023年12月に2回開催した「トビカン・ヤカン・カイカン・ツアー@ローマ展」の様子をお届けします。
夜の空気感や光はもちろん、発見やまなざしをともにしているシーンなど、参加者の皆さんととびラー20名の一期一会のステキなひとときをご覧ください。
<開始前>
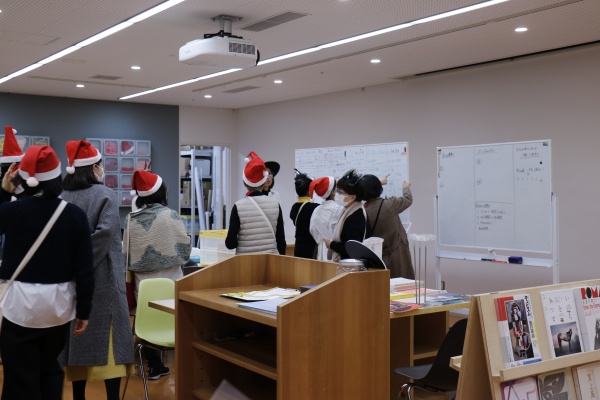
本番前の事前準備風景。コースの共有やチームごとの最終打合せも入念に

準備を整え、さあお迎え!

ぞくぞくとお客様がいらっしゃる。受付後に、各チームへご案内
<ツアー>
ツアーのテーマ・コースはガイドによってまちまち。ちなみに、ローマ展2回目で各ガイドが用意したテーマは
「夜のおしゃべり都美散歩/光に照らし出された都美空間を楽しむ/夜ならではのトビカンの陰影を楽しむ/100年保つ建物とその夜景/夜の都美をみんなでみてみよう!/色と光の調和」と多彩です。
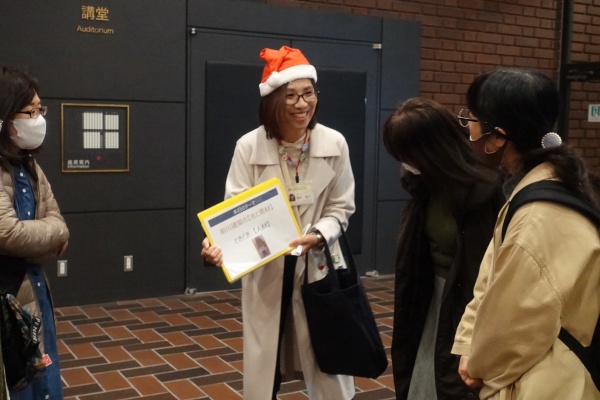
ツアーテーマを伝えてスタート

反射する光を堪能

エスプラナードを散策

天井やライトを愛でる

椅子も愛でる

素材をジェスチャーで説明

通称おむすび階段にて何やら楽しそうな様子

公募棟より何やら発見

お話もはずむ!

素敵なツアーを終えて控室へ
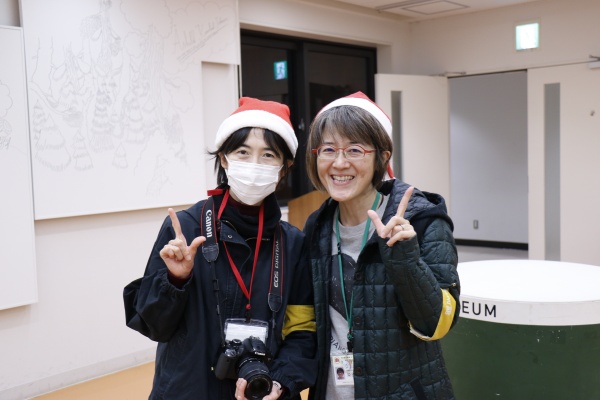
撮影班もお疲れさま!
◆過去から受け継いできたこと
11年続いているラボの良さを継承する、特に①シンプルな運営②ツアーの知見を貯めていくことを改めて大事にしようと話し合い、スタートしました。
①シンプルな運営
とびラーも家庭に仕事に忙しい人が多いので「金曜夜に2時間だけぱっと集まって集中して準備→ツアー→振り返り→解散」という流れができていました。この流れをよりブラッシュUPして、短い時間で楽しめるようにしました。
②ツアーの知見を貯めていく
ツアー実施には、ガイドやサポートはもちろん、受付や撮影など各役割の連携が欠かせません。過去の実施例を集めて知見集をつくりました。自分たちの知見も加えつつ、秘伝のタレ化を目指して更新中です。
◆今年のメンバーで変えてみたこと
よりツアーを手軽に楽しんでいただくために、①アンケート廃止②ツアー時間延長③当日呼び込み、この3点を刷新。アフターコロナも追い風になりました。
①アンケート廃止+②ツアー時間延長
ツアー時間を10分延長。参加者から「もう少し長いと嬉しい」とお声をいただくことが多く、我々ももう少しご案内したいという想いがありました。そこで、準備時間を短縮し、アンケートもツアー後に感想をいただくことで代用。ゆったりと夜の散策を楽しむことに繋がりました。
③当日呼び込み
アフターコロナでツアー人数などの安全対策が緩和され、キャンセルされた枠を当日呼び込むことにしました。たまたま通りかかって、たまたま一緒になった人と楽しむ、そんな偶然のめぐり合いもデザインできました。
◆予行演習
今年は新たに8人のガイドがデビュー。本番により良い状態でお客様を迎えられるように、とびラーが参加者役となり模擬ツアーを実施しました。

6月の大雨の中、練習会に集まったメンバー

雨の夜も、地面に光が反射してとてもキレイ

模擬ツアー終了後に、本番に向け温かく愛あるフィードバック
◆終わりに
毎回終了後に、良い点・改善点を皆で共有し、次にきちんと活かす。よりよいチーム・ツアーにするために、密度濃い振り返りを繰り返しました。その積み重ね、のべ59名のとびラーで作ってきた2023年のヤカンツアーでした。
次年度以降も、メンバーや環境の変化に合わせて進化し続けるラボになりそうです。今後もこのヤカンツアーは続いていくことと思います。ぜひ、ご参加をお待ちしています。

ランチMTGで振り返り。ヤカンツアー@マティス展の解散回

新しいメンバーも増えました。ヤカンツアー@荒木珠奈展の解散回

毎年恒例のクリスマスコスチューム。ヤカンツアー@ローマ展2回目終了後
◆おまけ
一緒に建築を見ることが楽しすぎて、今年からラボメンバー限定「オマケツアー」を打ち上げとセットで開催。マティス展では神田駅~東京駅、荒木展では東京駅~有楽町駅の近代建築を巡りました。発見して、伝え合って。建築って楽しい。

オマケツアーの様子

10期とびラー 橋本啓子
2023.12.03
◆はじめに
家庭や職場で忙しい大人を対象に、日常から少し離れ、美術館で心が豊かになる時間「大人のOFF」を一緒に楽しんでほしい。1回限りではなく2回会うことで、より繋がりを深めてほしい。この企画は、そんな願いを込めてスタートしました。
同じく家庭や職場で忙しいとびラーも、緩急つけて楽しみながら準備を進め、開催当日は参加者の皆さんと一緒に、美術館での「大人のOFF」を存分に味わい、繋がりを深めることもできました。準備~本番までの3か月の道のりをお届けします。
◆開催概要
◎日程・内容
STEP1:2023年11月26日(日)「とびラーお薦めのアート鑑賞」
STEP2:2023年12月3日(日)「前川國男設計のモダニズム建築ツアー」
◎参加人数
STEP1:参加者13人 とびラー19人
STEP2:参加者14人 とびラー17人
◆準備~本番までの3か月
1.どんな人に、どんなふうになって欲しいのか?
9月中旬、22名のとびラーが集い、方向性をすり合わせることからスタート。密度濃い話し合いを経て、目指すゴールは「忙しい大人に、美術館での楽しみ方を広げ心地よさや解放感を味わい、新しい発見や出会いを持ち帰ってほしい。そうすることで元気になって、また東京都美術館に来たいと思ってほしい。」となりました。
2.どんな内容にするか?
「忙しい大人」が参加したくなる内容とは?目指すゴールに到達するために、どんな経験をしていただくと良いのか?またもや、考えることが山積み。笑いながら考え、走りながら形を整えていきました。最終的には、「アート・建築を介して、いつもと違う体験や交流を」をテーマに、その機会を2日間で提供することにしました。
3.トライアルで内容を最終確認
用意した内容で、本当に参加者に楽しんで頂けるのか、不安と期待を抱えつつ、11月19日(日)にとびラー向けのトライアルを実施。参加者役のとびラーのおかげで、たくさんの改善点が見つかりました。
4.そして、本番
<STEP1>
①アイスブレイク(アートカードで関係探しゲーム)
オープニングで我々が「大人のOFF」を企画した想いを伝え、いよいよスタート。ゲームが始まるとあちらこちらから笑い声が。あっという間に皆さん打ち解けられ、また、作品をよく観るウォーミングアップにもなりました。
②「上野アーティストプロジェクト2023 いのちをうつす ─菌類、植物、動物、人間」展を鑑賞
いよいよ鑑賞へ。まずはグループで鑑賞、その後、個人で鑑賞しました。グループ鑑賞では、作品を介して感じたことや考えたことを伝え合い、作品をより深く味わう様子が見られました。
③感想共有
鑑賞から戻ってきて、心に残った作品の共有をしました。「ひとりで見るより、みんなで見る方が何倍もよく見られた」「とにかく感動!」「細かい描写がすごい」「今年見た展覧会で一番良かった」「もう一度行きたい」など、熱量高く語られていました。
終了後、ご希望の方と一緒にランチをしました。お弁当組5名はアートスタディールームで、レストラン組5名はMUSEへ。とびラーも一緒に、和気あいあいと色々な話に花が咲き、楽しいひとときでした。
<STEP2>
紅葉が美しく快晴の翌日曜日。リラックスしながらのお迎え準備。参加者の皆さんも前回と同じグループなので「久しぶり~」「あの後、展覧会行ってきましたよ」など、開始前から盛り上がっていました。そして、全員が揃ったことを拍手で喜びつつスタートしました。
①建築系カードで都美ツアーの準備
「都美カード」(各チームで用意した東京都美術館のイチ押し写真)で気になるカードを1枚選び、その理由を伝えあいました。また、「どこだろうカード」(建築部材等の写真、大吉くじ入り)もくじ引き形式で用意。ツアー前の準備も整いました。
②都美ツアー
選んだ「都美カード」と引いた「どこだろうカード」を手に、いざ70分の都美ツアーへ。上野公園にとけこむ前川建築で、まなざしを共有し、発見しあい、大人のOFFを満喫しました。
③感想共有&ティータイム→2日間を振り返る
ティータイムでほっと一息。ツアーの余韻を残しつつ感想を共有。「何度も来ていたが建物の良さを始めて知った」「前川建築の奥深さにハマった」「カードを持って美術館を歩き回り写真を撮るのが楽しかった」など、楽しそうにお話されていました。
エンディングは、この2日間の様子をムービーにして全員で鑑賞。皆さんとてもいい表情でご覧になり、誰からともなく大きな拍手で終了しました。終了後もしばらく歓談タイムが続き、集合写真を撮ることになりました。それが、冒頭の1枚です。
◆終わりに
参加者の皆さんがとびラーと一緒に良い場を作ってくださり、目指したゴールに到達できたように思います。アンケートも全員から「とても満足」を頂きました。2日間実施したことで、人と人、人と東京都美術館の繋がりがより深くなったとのお声も多く挙がりました。
最後に、少しだけ手前味噌ですが、我々22名はみんながフラットに持てる力を発揮するとても良いチームでした。
参加者の皆さんもとびラーも、家庭や仕事から少し離れて、東京都美術館で「大人のOFF」を一緒に楽しめたことを感謝いたします。また来てくださいね!
 10期とびラー 橋本啓子
10期とびラー 橋本啓子
2023.10.08
執筆者:小野関亮吉
同じとびラーといっても背景は人それぞれで、持っている興味関心もさまざまです。学びたいことや実現したいことの方向性が違えば、活動内容も変わってきます。
でもせっかく同じ時期にとびラーになったのだから、一人ひとりのことをもっと知りたくなりました。そこでこんなとびラボを「この指とまれ」しました。
※この指とまれ とは?
とびラーは、新しい活動のアイデアがひらめいたら「この指とまれ!」で他のとびラーを集めてチームを作ります。はじまるときには3人以上からスタートします。

人生の中で、一度に100人以上の人たちと出会う機会がどれくらいあるでしょうか?
それも同年代や同業種ばかりではなく、むしろ共通点を見つけることが難しく思えるような多種多様な人たちと。
私は入学や入社というライフイベントからだいぶ時間が経ってしまった年代ですが、この年齢になってからこれほど多くの人たちと知り合い、ともに活動できる機会に巡り会えるとは思ってもいませんでした。さらにそのステージは、東京都美術館であり、時には東京藝術大学のキャンパスの時もあります。とびラーとしての活動が始まった頃は、地に足のつかない思いだったことを思い出します。
とびラーになるとまず、美術館やアートコミュニケーションに関する基礎知識を学べる講座を受講します。基礎講座が始まると、徐々にとびラーたちの名前と顔が一致してきて、ここに集まった人たちがどんな人なのかをもっと知りたいし、私のことも知ってほしいと思いました。
知りたいのは、経歴や職業ではない。今興味のあることや大事にしているものなどから、その人の「人となり」を感じたいと思いました。しかし、いくらとびラー同士といってもねほりはほり尋ねるわけにもいきません。そこで、自然と「人となり」を伺い知れるアイテムって何だろう?と考えて、本に注目しました。
誰の本棚にも、捨てられない本や、忘れられない本、もう一度読みたい本があるでしょう。その中からお気に入りの1冊を持ち寄って、その本と自分とのエピソードを語ってもらったら、その人自身に近づけるのではないかと考えました。
「この指とまれ」をする時のメッセージには、
「本の内容や、どんなにすばらしい本か、ということではなく、
どうしてその本を手に取ったのか?
どうしてその本を大事にしているのか?
その本からどんな影響を受けたのか?
・・・といったこと。つまり、
あなたの好きな「本の話」ではなく、本が好きな「あなたの話」をしましょう。」
というメッセージを込めました。
そして、集まったとびラーたちと、時間配分や順番の決め方、進行役や記録役などの役割分担も相談し、参加するとびラーみんなの語りに耳を傾け合う時間を設計しました。
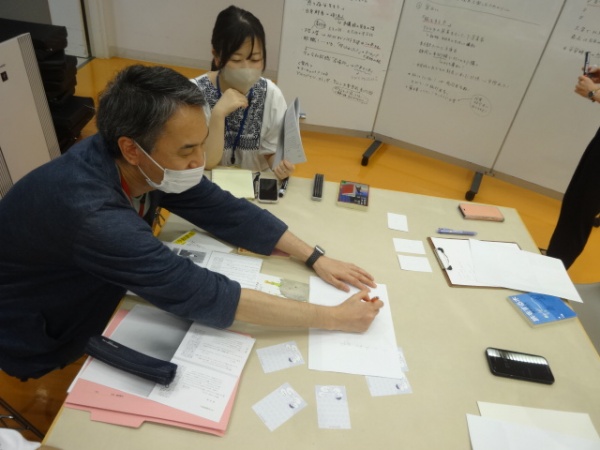
話し合いを重ねている様子
「とびラー文庫」は、計3回開催しました。
以下は参加したとびラーたちが、お気に入りの本を片手に話してくれたことを要約し、どんな人かを一言で表したものです。この記事を読んでくださっている方々にも、とびラーがどんなにバラエティ豊かな人たちの集まりであるかを感じてもらえたら嬉しいです。
・予備校講師の本の中の言葉から勇気をもらい、人生の大きな選択をした人
・ずっと同じ作家の小説を読み続け、作品ごとのスタイルの変化も楽しんでいる人
・一人旅には必ず本を一冊持って行く人
・古典文学から当時の恋愛事情や風習に興味を持った人
・中高生向けの哲学書を読んだ時に、周囲と自分との距離感を感じたという人
・カフカの作品だけでなく、人物像や作品をとりまく様々な考察を楽しむ人
・1930年代~1950年代頃のよく眠れる小説が好きという人
・スポーツを上達したいと足掻いていた頃に出会った本が、今でも自分の支えになっている人
・大きな地図の上で、自分が行った場所の距離感やスケール感を感じている人
・歴史に詳しく、歴史考証、科学考証がしっかりされた重厚な小説が好きな人
・絵本を読んで、自分の認識や価値観に鏡を向けられたように感じた人
・音楽を聴くように文章そのものを味わっている人
・ずっと読んでいたブログが書籍化され、その作者とのつながりができた人
・道を極めた染色家の思想や哲学に感銘を受けた人
・借金まみれの作家に関わった女性たちの気持ちを想像して、自分事のように怒ったり悲しんだりしている人
・建築界を舞台にした小説の登場人物に実在の建築家を重ねて楽しんでいる人
・長く続く歴史小説シリーズの怒涛の伏線回収にたまらない快感を覚えている人
・落ち込んだ時や疲れた時に何度も読み返す本が付箋だらけになっている人
・家出願望のあった思春期に、本の中に解放感を感じた人
・受刑者の詩集から、閉ざされた状況の中でも自由な感性が開かれる喜びを感じた人
・平凡な日常の学園生活を描いたマンガにどっぷりはまってしまった人
・ある“絵描き”が楽しそうにスケッチする様子から、自分の生き方を考えさせられた人


各々持ち寄った本をプレゼンテーションしている様子
こうして改めて並べてみても、どのお話からも一人ひとりが経験してきたことの厚みを感じます。そしてエピソードを語る声色や表情は、ある人は淡々と、ある人は情感豊かで、それぞれの独特な空気が表れていました。その人の好きなものや記憶に触れることができるアイテムを媒介にして、今目の前にいる人の「人となり」を感じられる機会となりました。願わくば、全てのとびラーのお話をきいてみたい。そう思えたとびラボでした。

とびらプロジェクトでは「対話」が大切にされています。そして対話のための安心安全な場づくりについても、考える機会がたくさんあります。
この「とびラー文庫」では、一人が語り手となり、その他は聴き手となってゆっくりと話を聴き、その後に感想を言ったり質問したりする構成にしました。参加者は聴いている時間の方が随分と長いことになるのですが、皆が誰の話にも興味深く聞き入り、共感や驚きなどの反応を示していました。互いに関心を持っていることが態度にも表れており、受け入れてもらえる安心感のある場になっていたのではないかと思います。
また、「本」というモノを媒介としたことで、その人の趣味嗜好に加えて、その人がどんな経験をし、どんなことに感動してきたのかを知ることができました。ストーリーや思い出を纏う本というアイテムは、「人となり」を感じたいテーマとの相性が良く、対話を濃密にする効果があり、この場を共有したことによる親近感につなげられたました。
冒頭でも書いたように、同じとびラーでも興味関心は様々で、活動内容も人それぞれです。
とびらの活動に限らず、日常の中で自分とは考え方の違う人もいるでしょうし、意見がぶつかり合ってしまうこともあるかもしれません。しかし、間にモノを置き、モノを一緒に眺めながら互いの声に耳を傾け思いを巡らせ合うと、その人の価値観がゆっくりと自分の中に浸透してくるような感じがします。そして人と深く知り合うことは、自分とは違う感性を持つその人のことも、愛おしく感じられるようになるのだと思います。
誰かともう少し知り合いたくなった時、皆さんならどんなモノを選びますか?

執筆者:11期とびラー 小野関亮吉
普段はゲームソフトの開発現場でプロジェクトマネージャーをしています。公私共に人と関わる機会が少なくなっていることを感じ、コミュニケーションが生まれる仕組みやコミュニティ作りに関心を持つようになりました。美術館は作品を鑑賞するだけでなく、誰かかと出会える場所であることを伝えていきたいです。